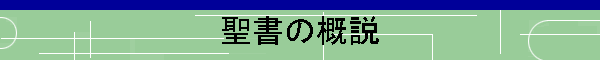
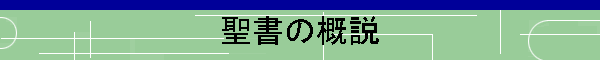
聖書の系統的な学びのために、以下の順序でお進みください。
1.聖書コース《栄光から栄光へと》(創世記から黙示録までの概略全20課)
2.本コース(聖書66巻各書巻の要約)
3.聖書の通読(毎年1年で1回、旧新約聖書を読み通す)
実際には、本コースを参照しながら聖書通読をしていかれると便利です。
![]()
![]()
世界のベストセラー、聖書。
それは『神のことば』と呼ばれ、その中に天地万物を創造された神ご自身のお考え、御思い、また心情が表わされている。人生の至高の目的は、神を知り、人にも知らせることにあると云われる。聖書は、私たちが神を知るために神御自身の選ばれた手段にほかならない。
神のみこころの中心にはイエス・キリストがおられる。そして、このお方を世に生まれさせるために、神は一つの民族をお選びになった。こうして、旧約聖書と新約聖書は一つに結びつく。
「旧約聖書は一つの民族について記している。
新約聖書はひとりの人について記している。
その民族は、この世界にその人をきたらせるために、神が創始され、育成されたものである。」(ヘンリー・ハーレー)
その民族の呼称は、ヘブル民族、イスラエル民族、あるいはユダヤ民族。
その人の名は、神御自身が人となられたお方、ナザレのイエス。
歴史の主要な舞台となった『聖地』は、カナンの地、パレスチナ、イスラエルなどと呼ばれてきた。
聖書は神の契約の書であり、その中心的な主題は、イエス・キリストによる人類の贖い(救い)である。
「それから、イエスは、モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事がらを彼らに説き明かされた。」 (ルカ24・27)
「わたし(イエス)についてモーセの律法と預言者と詩篇とに書いてあることは、必ず全部成就する・・・」(ルカ24・44)
「あなたがたは、聖書の中に永遠のいのちがあると思うので、聖書を調べています。その聖書が、わたし(イエス)について証言している・・・」(ヨハネ5・39)
聖書六十六巻は、凡そ千六百年の期間にわたり、約四十人の著者によって書かれたが、すべての書は一つの主題のもとに完全な調和を保っている。 また、そこに記されている真理は永遠に変わることがない。人間を超える一つの意志が、千数百年にわたって数十人の聖書記者たちを動かしてきた。
「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。」 (Ⅱテモテ3・16)
神の霊感については、次のように言い表わされよう。
「聖書は、原典において、神の完全な霊感によって記されたもので、絶対に誤りのない神のことばである。」
旧約聖書の原典はヘブル語で書かれた(一部アラム語)。紀元前百年頃、旧約聖書がギリシャ語に翻訳された。七十人の学者によってなされたので、それは七十人訳聖書とも呼ばれている。新約聖書の原典はギリシャ語で書かれた。旧約聖書からの引用は、主として七十人訳によっている。各国で使われている聖書は、これらの原語からの翻訳である。
現在までに数多くの翻訳がなされているが、その理由は・・・
1.各国の人々にとって、母国語の聖書が必要である。実際に聖書は数千の言語に訳されている。
2.同じ国語にも変遷があり、新しい世代の人々には、新しい言葉づかいの翻訳が必要となる。
3.原典に忠実な聖書。旧新約聖書の原典は実際には存在しない。過去において、我々人類の目に触れることが出来たのは写本である。そして、筆写には誤りの機会もあるので、写本は古いものほど正確とされる。従来、現存する最古の写本よりも更に古い写本が発見される度に、考古学者や聖書学者によって原典に近づく努力が続けられ、その成果に基づいて、原典に更に忠実な翻訳聖書が望まれて来た。
4.意訳聖書。
聖書には歴史的、地理的、言語学的な背景があり、直訳によっては現代に通じ難い場合が少なくない。
このようなわけで、今までに数多くの翻訳聖書が発行されてきた。英語では、英欽定訳聖書、米改訂訳聖書が特によく知られ、近年になって新国際訳聖書が出版された。日本語では、過去に元訳聖書(文語)、文語訳聖書、口語訳聖書、新改訳聖書等が発行され、意訳聖書としてはリビング・バイブル(英、和訳)、現代訳聖書がある。また最近、プロテスタント、カトリック関係者共同による新共同訳聖書が出版されている。
![]()
「初めに、神が天と地を創造した。」(1・1)
聖書は、神の存在を証明しようとはしていない。神の存在を前提として始まっている。神の存在は、歴史における事実である。
「信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです。」(ヘブル11・6)
人はどこから来て、どこへ行くのか?その答えは、聖書の中にある。
神は、人間を御自身のかたち(イメージ)に創造された。(1・27)
人は永遠に創造の神とのコミュニケーションを保ち、被造物の世界を治めるべき役割を与えられていた。また、人類最初の男女は完全な夫婦のモデルとなる筈であった。
「それゆえ、男はその父母を離れ、妻と結び合い、ふたりは一体となるのである。」(2・24)
ところで、神は人に一つの戒めをお与えになっていた。
「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。」(2・16、17)
この神の命令に対する違反が、人類の運命を全く変えてしまう。それは、ひとりの人(アダム)の故意の不従順から始まった。こうして、全世界に罪とその結果である死が入って来た。(ローマ5・12)
神の祝福を受けた最初の家庭に、一体何が起きたか?神との断絶、夫婦の不調和、そして、兄が弟を殺すという悲劇。(3・8、12、4・8)
地上に人の悪が増大し、それゆえに神は当時の世界を大洪水によって裁かれた。 生き残ることを許されたのは、ノアとその家族、そして、一緒に箱舟に入ることのできた限られた生き物だけである。ノアの三人の息子はセム、ハム、ヤペテで、彼らから全世界の民は分かれ出た。(9・19、10・32)
創世記十二章以後の残りの部分は、一つの民族の始まりを扱っている。真の神から離れてしまった人類の救いのために、特別の使命を担わされた神の選民である。そして、このヘブル民族の先祖として選ばれた人物がセムの子孫アブラハム(最初の呼び名はアブラム)であった。(別資料《イエス・キリストの系図》)
旧約聖書の中において、同じ神についての最も重要な名前が二つある。
(1)神(エロヒーム)
全能の力をもって無から有を生み出す創造の神の名。約2600回使われている。
(2)主(ヤーウェ)
人間の生活に関わり、人類の救いを成就される契約の神の名。約6800回使われている。
この『主』が、アブラハムを、彼の生まれ故郷であるカルデヤのウルから呼び出し、カナンの地(現在のイスラエル)に導いて来られた。この時以来、ここが聖書の主要な舞台(聖地)となる。
召しに従ったアブラハムに、主は仰せになった。
「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。・・・・地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。」(12・2、3)
主なる神は、御自身の主権によって人をお選びになり、こうして祝福の約束は、アブラハムの子イサク、更にその子ヤコブへと引き継がれることになる。(26・4、28・14)
この祝福とは、彼らの子孫としてメシヤ、すなわち全人類の救い主イエス・キリストが世に来られるということである。このことは、徐々に明らかになって行く。
十二章以下は、主として、族長アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの歴史である。
ヤコブ、後のイスラエルに十二人の息子が生まれ、彼らがイスラエル十二部族の祖先となった。
ヨセフは或る事情でエジプトへ売られたが、やがて出世して総理大臣になる。これは、彼の同族である神の選民が、危機の中で生き延びるための神の計らいであった。
私たちは、
アブラハムの生涯を通して、 『信仰』について、
イサクの生涯を通して、『従順』について、
ヤコブの生涯を通して、『葛藤』について、
ヨセフの生涯を通して、『摂理』について、学ぶことができるであろう。
![]()
カナンの地に飢饉が続き、ヤコブ(イスラエル)とその家族はエジプトへ下った。総勢約七十名であった。彼らの子孫は四百年余りエジプトに滞在することになる。その間にイスラエル人の数は百万名以上に増大していた。
新しいエジプトの王パロは、イスラエルの民の著しい人口増加を恐れ、彼らに過酷な労働を課した。そして遂に、自分のすべての民に命じて言った。
「(ヘブル人の家に)生まれた男の子はみな、ナイルに投げ込まなければならない。」(1・22)
このような状況の中で、イスラエル十二部族の一つ、レビの家系にひとりの男の子が生まれた。 神の不思議な摂理の中で、彼はパロの娘の子として王の宮殿で育てられた。その名はモーセ。後に旧約聖書最大の指導者となる。
モーセの生涯は、四十年ずつ三つの期間に分けられる。
(1) 40才まで
パロの王宮で、エジプト人のあらゆる学問を教え込まれた。
(2) 40〜80才
出エジプト─イスラエル人のエジプト脱出─の指導者としての使命を自覚。しかし、同胞に受け入れられぬまま、パロの手を逃れてミデアンの地に身を寄せた。そこでミデアンの祭司の娘と結婚し、ふたりの男の子をもうける。この期間、彼は羊飼いとしての生活を送った。
(3) 80〜120才
神の山ホレブ(シナイ山)で主の御声を聞く。この時、神ご自身が直接にモーセをエジプトへ遣わされた。
これより後、約四十年にわたり、エジプト脱出から荒野を通って約束の地カナンの入り口に至るまで、彼はイスラエルの指導者として神の民を導くことになる。
エジプトに帰ったモーセは、兄のアロンと会い、ふたりはエジプトの王パロのところへ出かけて行って言った。
「イスラエルの神、主がこう仰せられます。『わたしの民を行かせ、荒野でわたしに仕えさせよ。』」(5・1、7・16)
しかしパロの心は強情で、イスラエルの民を出て行かせようとしなかった。神は、モーセを通して数々のしるしと不思議を行ない、エジプトに災害を送られた。その数は十回に及ぶ。(7〜11章)
最後のしるしが『過越』である。イスラエルの民は、主なる神の命令に従って子羊をほふり、その血を家のかもいと二本の門柱につけた。朝まで、だれも家の戸口から外に出てはならないことになっていた。
真夜中になって、主はエジプトのすべての人と家畜の初子(ういご)を打たれた。エジプトには激しい泣き叫びが起こった。死人のない家がなかったからである。しかし主は、イスラエルに対しては、かもいと二本の門柱にある血をご覧になり、その戸口を過ぎ越して行かれ、滅ぼす者がその家にはいって、打つことがないようにされた。(12章)
この事件は、歴史的な事実であるとともに、新約聖書の時代における贖い(救い)の型を表わしている。神の御子イエス・キリストは、私たちのために過越の小羊となられた。(Ⅰコリント5・7)
神は、私たちの心の戸に適用された御子イエスの血を見て、罪人である私たちのところを過ぎ越してくださるのである。
さて、紅海を渡り、エジプトを脱出したイスラエルの民は、シナイの荒野にはいり、そこに一年近く宿営した。
この間の重要な出来事。
1.指導者モーセの、シナイ山での神とのコミュニケーション。
2.十戒を中心とする神の律法がモーセを通して与えられたこと。
3.幕屋の建設。時に応じて移動できるように設計されていた。神の臨在する(そこに住まわれる)所として定められ、会見の天幕とも呼ばれた。礼拝の中心の場所である。
こうして神の民イスラエルの、国家としての体制が整う。
神によって立てられた指導者モーセがいた。
神から与えられた律法(憲法)があった。
そして、神ご自身が民の真中におられることを象徴する幕屋が建設されたのである。
「そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。」(40・34)
![]()
レビはイスラエル十二部族の一つ。幕屋の奉仕のために、神の任命を受けていた。本書は、主に彼らの務めについての律法が記録されているので、表題のように呼ばれている。これらの律法は、イスラエルの民がシナイの荒野に宿営している時に与えられた。レビ記は、礼拝のためのハンドブックである。
神によってあがなわれた者の第一の務めは、神の御前に近づき、神と交わり、神を礼拝することである。
ささげ物に関する律法(1〜7章)
五種類のささげ物。全焼のいけにえ、穀物のささげ物、和解のいけにえ、罪のためのいけにえ、罪過のためのいけにえ。
罪が処理されなければ、人は神に近づくことができない。ただ一つの方法は、身代わりの犠牲による。
「血を注ぎ出すことがなければ、罪の赦しはないのです。」(ヘブル手紙9・22)
これらは、私たちのために完全なささげものとなられたイエス・キリストを暗示している。
「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。」(ヨハネ1・29)
祭司の務めに関する律法(8〜10章)
犠牲は、祭司を通して神にささげられた。そして、レビ族のアロンの家系の者が祭司になることが定められていた。祭司は、神と人との仲介者であり、この務めもまた、偉大な大祭司であられるイエス・キリストを指し示している。(ヘブル2・17、4・15)
今日、動物の犠牲も、祭司も必要ない。キリストご自身が完全な犠牲となられたから。そして、神と人との間の唯一の仲保者、完全な大祭司として、父なる神の右の座でとりなしの務めを続けておられる。(ヘブル7・25、10・12)
私たちは、イエス・キリストによって、そして、このお方を通してのみ、神に近づくことができる。(ヨハネ14・6、ヘブル人4・16)
きよめに関する律法(11〜27章)
神を礼拝する者には、霊肉両面でのきよさが要求される。
「主であるわたしが聖であるから、あなたがたも聖なる者とならなければならない。」(19・2)
この律法が、霊的生活だけでなく、肉体のきよさにも留意していることは興味深い。衛生的な見地から食生活に注意することは、神の民にとって特に大切である。(11章)
過去の歴史の中で、ユダヤ人の長寿は、この衛生に関する律法の正しさを証明してきた。
主の例祭。(23章)
定期的に行なわれる儀式。重要なことを回想し、記憶し、それを子孫に伝えることによって、真の礼拝者として、神との正しい関係が維持されるよう配慮されていた。
七種類の祭りが記されている。
① 安息日
②過越─種を入れないパンの祭り。過越は血による贖いについて語っている。
③初穂の祭り。
なお、25〜27章には、土地に関するユニークな戒めについて記されている。
1.安息の年
2.ヨベルの年
これらの律法は、神の選民イスラエルを、近隣の諸国民の生活様式や習慣から分離するために神によって制定されたものである。このようにして、彼らは、真の神への礼拝と奉仕のために聖別(区別)された国民となることが期待されていた。
![]()
本書は、いわゆるモーセ五書(創世記〜申命記)の第四番目の書。イスラエルの人口調査─民を数える事─が二回記録されていることから、民数記と呼ばれている。
本書の重要な思想は「奉仕・訓練」である。
或る人は、モーセ五書を次のように要約している。
1.創世記には、堕落した人間が描かれている。
2.出エジプト記には、贖われた人間が描かれている。
3.レビ記には、礼拝している人間が描かれている。
救われ、神を礼拝する魂が奉仕の資格を持つ。
奉仕には秩序が欠かせない。イスラエルは、一年近くシナイの荒野に留まっていた。その間に、律法が与えられ、幕屋が建設された。これから約束の地カナンに向かって行進が始まろうとしている。そのために、会見の天幕を中心とする様々な奉仕が組織化された。
第一回目の人口調査(1・46)
場所はシナイの荒野。
二十才以上の男子で、軍務につくことのできる者の総数は603,550人。男子と女子と子供全部を合わせると、二百〜三百万人はいたであろう。
イスラエル人は整然と旅立った。
主の契約の箱が先頭に立って進む。神がともにおられた!(1〜10章)
ところで、11章以下は、神の民の中に見られた反抗の精神で満ちている。民のつぶやきは、すでに出エジプト記の中に始まる。
「私たちをこの荒野に連れ出して・・・・飢え死にさせようとしている。」
「なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。・・・渇きで死なせるためか・・・。」
「ああ、肉が食べたい。・・・・何もなくて、このマナを見るだけだ。」(11・4)
モーセの姉ミリアムと兄のアロンは、妬みから彼を非難している。(12章)
13、14章の出来事は、イスラエルの民の運命を大きく変えた。この時、彼らは約束の地の国境近くカデシュ・バルネアまで来ていた。カナンの地を探るために十二名の斥候が遣わされた。そこはまことに良い地であったが、強大な敵がいた。はたして、その地を占領することができるであろうか。
ヨシュアとカレブの二人は言った。「必ずできる。」
しかし、残りの十名は敵を恐れて、「できない。」
全会衆はこの声に従った。この結果イスラエルは背信の罪を負い、四十年近く、なお荒野を放浪することになる。
次いで、モーセとアロンの指導権に対するコラの反逆。
その罪の結果は実に恐るべきものであった。それは神ご自身への反抗を意味したからである。モーセとアロンは神によって立てられた指導者だった。(16、17章)
再び会衆のつぶやき。そこには水がなかった。この時、モーセは民のゆえに、彼自身大きな失敗をする。モーセが彼の杖で岩を打つと、たくさんの水がわき出た。しかし、彼は不用意にも自らを神の立場に置いてしまったようだ。
主はモーセとアロンに言われた。
「あなたがたはわたしを信ぜず、わたしをイスラエルの人々の前に聖なる者としなかった。それゆえ、あなたがたは、この集会を、わたしが彼らに与えた地に導き入れることはできない。」(20・12)
またも民のつぶやき。イスラエルの多くの人々が蛇にかまれて死んだ。
モーセは主の命令により、一つの青銅の蛇を作り、それを旗ざおの上につけた。もし蛇が人をかんでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると、生きた。(21・9)
これは、イエス・キリストの十字架による救いの型とされている。(ヨハネ3・14、15)
第二回目の人口調査(26・51)
場所はカナンの国境、ヨルダンのエリコをのぞむ対岸のモアブの草原。
数えられた者の総数は601,730人で、第一回目に登録された者の内で、この数に含まれているのはヨシュアとカレブの二人だけである。残りの者は、不信の罪ゆえにすべて荒野で死に絶えた。祭司アロンも死に、その務めは彼の子エルアザルに引き継がれた。
モーセの指導権もヨシュアに受け継がれることとなった。そして、新しい世代の者たちが約束の地に入ろうとしている。
イスラエルの数々の失敗にもかかわらず、神はなおもこの民に目を留めておられた。それは、神がアブラハムに約束された通りに、彼の子孫がメシア─救い主─を生み出すという使命を負わされていたからである。
![]()
申命記はモーセ五書(創世記〜申命記)の第五番目で、書名は『第二の律法』という意味である。これは、四十年ほど前にシナイにおいて与えられた律法が、ここに再び回顧され、説明されているのでこのように呼ばれている。新しい律法が含まれているという意味ではない。
モーセはイスラエル人を、エジプトから約束の地(カナン)の境にまで導いて来た。シナイにおいて律法を与えられた成人のうち、ヨシュアとカレブの二人を除くすべての民は荒野で死に絶え、今やモーセ自身の世を去るべき時も近づいていた。これから、新しい世代の人々が、ヨルダンを渡り約束の地に入ろうとしている。それゆえ、これらの若い民に対して、イスラエルの過去の歴史が回顧され律法が強調される必要があった。
ヘンリエッタ・C・ミアーズ著『旧約聖書の概説』によれば、モーセ五書の内容は次のようにまとめられている。
1.創世記は、選ばれた民イスラエルの始まりについて語っている。
2.出エジプト記は、民が一つの国民にまで組織されることと、律法の付与について述べている。
3.レビ記は、この民のあるべき神礼拝の仕方を告げている。
4.民数記は、この民のさすらいの物語を示している。
5.申命記は、約束の地に入るための最後の準備について語っている。
申命記について特筆すべきことは、これが、私たちの救い主イエス・キリストの愛読の書であったことだ。主イエスは、ナザレの村における少年時代より、本書に特別に親しまれたに違いない。
公生涯に入られた直後、荒野でサタンの誘惑に遭われたときに、主はこの書から引用され、神のことばによって敵との戦いに勝利を収められた。(マタイ4章、ルカ4章、申命記6、8章)
或る註解者は、モアブの地でなされたモーセの勧告を三つの言葉に要約している。すなわち、「想い出しなさい」、「従いなさい」、「注意しなさい」。
想い出しなさい─イスラエルの放浪生活の回顧(1〜4章)
神の民は、いま約束の地の国境にいる。
四十年ほど前、イスラエルの人々はシナイから十一日間の旅の後に、カナンの地に入れるはずであった。十一日の日程で済む旅に四十年!遠回り、同じ所の堂々巡り、人生における遅々とした歩み。これらはすべて、真の神に対する不信仰の結果である。
私たちが神に全く信頼するとき、神はその信仰を通して働かれる。しかし多くの場合、神の民の不信仰のゆえに、神は力あるわざを現わすことができない。
従いなさい─律法の回顧(5〜27章)
神は、その民が永久にしあわせになることを熱願しておられた。それゆえ、主はイスラエルの人々に、神のすべての命令を守るようにと云われたのである。彼らにとって、四十年間に及ぶ荒野の歩みの全行程は、そのための神による訓練であった。(申命記8章)
ところで、18章には『モーセのようなひとりの預言者』について記されている。彼に聞き従うようにと・・・。
『ひとりの預言者』とはイエス・キリストを指し示している。モーセが書いたのは結局このお方のことであった。(ヨハネ5・46、使徒7・37)
注意しなさい─イスラエルの未来の預言(28〜33章)
ここでモーセは、従順の祝福について語り、同時に不従順の呪いについて民に警告している。
28章は驚くべき預言の書である。彼らは結局、不従順の道を選んだ。旧約聖書の時代から近代に至る、ユダヤ人の異国への捕囚、全世界への離散と想像を絶する悲惨な運命は、この預言の厳粛な成就と云えよう。
しかし、なお未来への希望の約束は残されている。
モーセの死(34章)
神の人モーセは、約束の地を見渡すことのできるピスガの頂きに登り、そこで百二十歳の生涯を終えた。今日に至るまで、その墓を知った者はいない。神ご自身が彼を埋葬されたからである。
モーセは死んだが、神の働きはヨシュアに引き継がれて行く。
![]()
ヨシュア記からエステル記までの十二の書巻は歴史書として分類されている。
本書は、イスラエルの民が約束の地─カナンの地─を侵略し、部族ごとに土地を分割した際の記録である。この時の指導者がヨシュアであるところから、このように呼ばれる。
ヨシュアの死の記録を除けば、多分、彼自身が本書の著者でもあろう。
ヨシュア記は戦いの書、征服の書、勝利の書、所有の書である。しかし、一般的な意味での外国の侵略に根拠を与えるために書かれたものではない。
イエス・キリストによる贖い(救い)の計画の中で、神がご自身の約束を実現して行かれるという視点から理解される必要がある。神は、かつてアブラハムに、相続財産としてカナンの地を与えると約束され、今や実現の時が来た。だから神の民は行ってそれを所有せよ、と命じられる。
私たちの信仰生活には、霊的な戦いがある。そのような観点から見るなら、ヨシュア記は霊的真理で満ちており、信仰の戦いに従事する者に大きな励ましと実際的な知恵を与えてくれる書であると言えよう。
出エジプトの指導者モーセは死に、神の民イスラエルをカナンの地へ導き入れる働きはモーセの従者ヨシュアに引き継がれた。主なる神はヨシュアに、土地所有の確認、律法順守の命令、そして、臨在(どこにでも主がともにおられる)の約束を与え、強く雄々しくあるように励まされる。
ヨシュアは二人の斥候を遣わし、カナン第一の城壁の町エリコを偵察させた。この時彼らに協力したのが、ラハブという名の遊女であった。彼女のしたことは、信仰の行為として聖書の中で称賛されているだけでなく、ラハブの名前は、メシヤ(救世主)としてのイエスの系図の中にも加えられている。
イスラエルの人々はヨルダン川を渡った。契約の箱をかつぐ祭司たちの足が水ぎわに浸ったとき、岸いっぱいにあふれる川の水は上流でせきとめられ、民はかわいた地を通ってヨルダン川を渡り終わった。信仰による第一歩が、不可能の中に道を拓く。そして、エリコ攻略にあたり、指導権はヨシュアではなく、主ご自身にあることが確認されている。(5・14)
神の指示されたエリコ攻略の方法は、人間の目には愚かに見える。イスラエルの民は、一日に一度、六日間、町のまわりを回り、七日目には、七度町を回る。祭司たちは角笛を吹き鳴らす。その間、民は黙っていなければならない。そして、最後にときの声をあげる、というものであった。
彼らが角笛の音を聞いて、大声でときの声をあげるや、城壁がくずれ落ちた。こうして民は、エリコの町を攻め取った。神の命令が理解を超えるとき、私たちは判断を中止してそれに従わねばならない。その信仰を通して、神は奇蹟をなされるからである。
エリコに次ぐアイの町の攻略は、最初失敗した。アカンの罪のためである。個人の罪は共同体である全イスラエルの罪とみなされた。勝利の鍵は、神がともにおられるということである。アカンの罪が処理されることによって神の臨在は回復され、イスラエルは再び敵に勝利することができるようになった。
約束の地の分割(13〜22章)
ヨシュアは年を重ねて老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っていた。イスラエルの民は、部族ごとに相続地を割り当てた。
カレブという名に注目したい。民数記に記されている十二人の斥候の一人である。同世代の者の中で、約束の地に入ることを許されたのは、ヨシュアとこのカレブの二人だけであった。彼は、すでに八十五才になっていたが、なお戦うための信仰、気力、体力は昔と変らなかった。
ヨシュアは、カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。彼は、イスラエルの神、主に従い通したという理由で、その名が聖書に特記されている。
ヨシュアの告別(23〜24章)
ヨシュアは、遺して行く民に対して、主なる神に誠実に仕えるよう、また自分たちの仕える神を自ら選ぶように強く勧める。こうして、彼は百十才の生涯を閉じた。
![]()
士師記は、イスラエルの指導者ヨシュアの死後、サウルが王座に着くことによって王制が確立するまでの時期を扱っている。それは、約束の地での最初の四百年ほどの歴史である。この間、十数人のさばきつかさ(士師)が民を治めた。それで、このように呼ばれている。
ヨシュア記が〈勝利の書〉であるのに対し、士師記は〈失敗の書〉である。
カナン征服の時代、イスラエルの民は、神の命令に従ってその土地の先住民族を滅ぼし尽くすことはしなかった。このことが罠となり、次の世代の人々は異教の民と同盟を結び、その結果、偶像礼拝と不道徳に陥って行く。
ここには、士師記の中で繰り返されるパターンが記されている。
1.イスラエル人が主の前に悪を行なう。即ち、彼らは、エジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神、主を捨てて、先住民の神々─バアルやアシェラ─に従い、それらを拝み、主を怒らせた。
2.主は、イスラエル人を回りの敵の手に渡して、彼らを略奪させた。
3.イスラエル人は、敵の圧制のもとで苦しみ、主に向かって助けを叫び求めた。
4.主は一人のさばきつかさを起こして、イスラエル人を略奪者の手から救われた。
5.そのさばきつかさが死ぬと、イスラエル人は逆戻りして、ほかの神々に仕えた。
第1章には、「追い払わなかった」ということばが何度も使われている。
イスラエルの人々は、この点において、神の命令に完全には従い切れなかったが、奇妙なことに、神も、ある目的のためにそれを黙認されたようだ。それは、彼らが神の道を守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためであった。謂わば、テストの方法として、偶像礼拝の民を神ご自身が残されたということか。
また、戦いを知らない新しい世代の者たちに、戦いを教え、知らせるためとも記されている。
結局、イスラエル人は、この試験に失敗したのである。
有名なさばきつかさは七名─オテニエル、エホデ、デボラ、バラク、ギデオン、エフタ、サムソン─である。ただし、デボラは女性で、彼女の補佐役がバラクであった。
或る聖書注解者は、士師たちについて三つの重要な事柄に注意をうながしている。
1.彼らは、神によって召された。
2.彼らは、特別な能力を授けられていた。
3.彼らのほとんどは、パウロが「この世の弱い者・・・身分の低い者・・・無きに等しい者」と記した階層に属している者であった。
この書が伝えているのは、先ず第一に、神から離れた人間の心がいつも邪悪に向かう傾向にあると言うこと。次に、人間の絶えざる失敗にもかかわらず、それを救おうとされる神の恵みもまた大きいと言うことである。
或る神学者は、士師記を次のように要約している。
「七回の背信、七つの異教国への七回の隷属、七回の解放!」
この時代のこまかい描写。
宗教生活における無秩序(17、18章)
道徳生活における無秩序(19章)
国民生活における無秩序(20、21章)
本書の最後の節は、当時の人々の普通の状態を端的に描写している。
「そのころ、イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行なっていた。」(21・25)
私たちは、人間の性質が教育、精神修養などによって向上すると思い易い。けれども、聖書によれば、神から離れた人間は、生まれながらの性質が悪い方に向いており、自己中心的である。生まれてからなされる外からの訓育は、ただ、それをスマートに見せるに過ぎない。
心の中に、真の神を王としてお迎えしない限り、私たちの生活はあらゆる面で無秩序となって行くであろう。
![]()
士師記が、さばきつかさが民を治めた時代の暗い面を扱っているのに対して、ルツ記は同じ時代の明るい面を扱っている。
この書は、主人公として登場する異邦人(モアブ人)の女性ルツの名をとって書名としているが、その価値は最後に記されている人物の名前にある。
「エッサイの子はダビデ」
救い主イエス・キリストはダビデの子孫として世に来られることになっていた。本書は、そのダビデの家系についての記録である。(別資料《イエス・キリストの系図》参照)
スコフィールド博士による概略を引用しておく。
1.決心するルツ(1章)
2.奉仕するルツ(2章)
3.休息するルツ(3章)
4.報われたルツ(4章)
ユダのベツレヘムの人エリメレクは、妻のナオミとふたりの息子を連れてモアブの野へ行き、そこに住んだ。ききんがあったからである。エリメレクはその地で死に、ふたりの息子はモアブの女を妻に迎えた。兄嫁の名がルツである。
約十年の間に、息子たちも死に、こうしてナオミは夫とふたりの子どもに先立たれてしまった。ききんが過ぎて、ナオミはユダの地へ戻るため帰途につく。彼女の勧めで、弟嫁はモアブの実家に帰るが、ルツはナオミとともにユダの地に行く決心をする。
大麦の刈り入れの頃、ナオミは、嫁のモアブの女ルツといっしょに、ベツレヘムに帰って来た。
生活のため、ルツは落ち穂を拾い集めに行くことをナオミに申し出る。モーセの律法によれば、土地の所有者は、畑で穀物の刈り入れをするときに、その隅々まで刈ったり、また収穫の落ち穂を集めたりすることは禁じられていた。在留異国人や貧しい者─みなしご、やもめ─のために、それらを残しておかなければならなかった。(レビ記19:9、10、23:22、申命記24:19〜22)
ナオミには、夫エリメレクの親戚で、その一族に属するひとりの有力者がいた。その人の名はボアズと言った。ルツは出かけて行き、刈る人たちのあとについて、落ち穂を拾い集めたが、そこは、はからずもボアズの畑であった。モアブの女ルツとボアズの出会いは、神の摂理の中に定められていたのである。
ボアズは、ナオミやルツたちにとって買い戻しの権利のある近親者であったとされている。モーセの律法によれば、或る人が貧しくなり、その所有地を売ったなら、近親者が来て、それを買い戻すという権利が認められていた。また、別の律法は、もしある男子が子どもを持たないで死んだときには、彼の兄弟がその妻をめとり、初めの男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにする義務を規定していた。しかし、兄弟のいない場合には、最も近い親族がその義務を負うことが、当時の習慣だったようである。(レビ記25:25、申命記25:5〜10)
ルツがひそかにボアズの寝ている所へ忍んで行って、彼の足許に寝たということは、決して、はしたない行為とは言えない。当時の風習に従って、ただ単に法律上の要求をしたに過ぎない。ルツは、そうすることによって、ボアズに死んだ親族に対する義務を想い出させたわけである。
ボアズは、ルツを妻とすることを願ったが、実は、彼よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がいた。この点が解決されなければならない。
ボアズは証人たちの前で、その最近親者に、エリメレクの所有地を買い戻す権利について語った。同時に、もし彼がその土地を買い戻すならば、モアブの女ルツを妻としなければならない旨を告げる。その近親者は、自分自身の相続地をそこなうことになるのを嫌い、買い戻す権利を放棄してそれをボアズにゆずった。
こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。ルツはひとりの男の子を産んだ。その名はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。
イエス・キリストの系図の中に、異教徒であるルツの名が記録されていることは、神の大きな恵みの現われではなかろうか。
![]()
サムエル記は、イスラエル王国の成立について扱っている。王制の創設にあたって、指導的な役割を果たしたのは、預言者サムエルであった。本書の名は、そこからとられている。しかし、王国の歴史の中では、ダビデがいつも中心的な位置を占めてきた。サムエル記 は、ダビデがイスラエルの正統な王となるための過渡期の書である。
内容は、三人の主要な人物によって区分できよう。
1.サムエルについて(1〜7章)
2.サウルについて(8〜15章)
3.ダビデについて(16〜31章)
範囲は、サムエルの誕生から、サウルの死まで。
ハンナは不妊の女性で、子どもがなかった。
「ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って、激しく泣いた。」(1・10
やがてその願いは叶えられ、男の子が生まれた。その子の名前がサムエルで、このことばには、「主に聞かれる」という意味がある。『祈り』は、この書を特徴づける大切な要素である。ハンナの祈りがなかったら、サムエルは生まれなかっただろう。サムエルも生涯祈りの人であった。
ハンナは、息子サムエルの生涯を主にささげた。当時イスラエルをさばいていたのは祭司エリであったが、彼の息子たちの罪は非常に大きく、神はこの一家を退け、サムエルをさばきつかさとして立てようとなさる。
主は少年サムエルにお語りになり、彼は聞く。
「お話しください。しもべは聞いております。」(3・10)
こうして、サムエルは主の預言者に任じられた。
イスラエルの民は、、ペリシテ人の圧迫を受けていた。戦いのさなか、神の箱は奪われ、祭司エリの一家は没落。サムエルは、イスラエルの全家に、偶像礼拝から真の神に立ち返るように促し、彼らのために主に祈る。こうして、サムエルのとりなしの祈りがイスラエルに勝利をもたらした。
サムエルは、年老いたとき、息子たちをイスラエルのさばきつかさとしたが、この息子たちは父の道に歩まなかった。
イスラエルの長老たちは、サムエルのところに来て言った。
「私たちをさばく王を与えてください。」(8・6)
元来、イスラエルは神政国家であるから、神ご自身が王であり、人間の王を必要としないのだ。けれども、主は民の願いを許容された。
サムエルを通して、一人の若者─サウル─がイスラエルの王として選ばれる。サウルはベニヤミン族の出身で、背のひじょうに高く、美しい青年だった。しかし、彼はけっきょく王として失格、王位から退けられてしまう。その理由は、神のみこころに対する故意の不従順─或るいはむしろ、気乗りのしない従順─であった。
主は、ご自身のために、別な王を見つけておられた。ユダ族のベツレヘム人エッサイの八人兄弟の末息子、ダビデである。彼は、サムエルに呼ばれたとき、父の羊の番をしていた。
サムエルは、主の命令によって彼に油を注いだ。これは、王としての権威と能力が神によって与えられることを象徴している。このことは、実際にダビデの上に神の霊が注がれることによって現実となる。
名目上は、サウルがまだ王位にあった。ダビデはサウルに仕え、幾多の戦いを通して、彼こそがイスラエルの王にふさわしい人物であることを証明していくのである。
少年ダビデと、ペリシテ人の勇士ゴリヤテとの一騎打ちの物語は有名だ。彼は、サウルが遣わす所どこででも勝利を収め、人々の称賛を得たが、それがまたサウルのねたみを招くこととなった。この後、ダビデはサウルの殺意の手を逃れて、放浪生活を強いられる。
一面、ダビデにとって、これは主による訓練の期間でもあった。彼は、あらゆる境遇の中で、主に信頼することを学んだ。本書は、サウルの死をもって終わっている。サウルは、私たちの反面教師、ダビデは私たちの模範と言えるであろう。
![]()
ヘブル語の原文では、サムエル記
Ⅰ、Ⅱは一巻であり、サムエルの生涯の始まりからダビデの生涯の終わりまでの時期を扱っている。旧約聖書がギリシャ語に翻訳された時に、七十人訳の訳者たちによって二巻に分けられた。著者については、Ⅰサムエル記の24章までをサムエルが記し、それ以後およびⅡサムエル記の全体は、ダビデと同時代の預言者ナタンとガドによって追加されたものと考えられている。(Ⅰ歴代誌29・29)
本書は、全文がダビデの人物像に集中されており、ダビデ王政の歴史の記録となっている。全体は三つに区分される。
ダビデが、王としての任命を象徴する油注ぎを三度受けていることに注目したい。
第一は、少年時代にサムエルによって(Ⅰサムエル記16・13)。これは、神による根本的な任命だったが、名目上は、なおサウルがイスラエル王の位に留まっていた。
第二は、サウルの死後、30才になったとき、同族のユダの人々によってユダの家の王として(Ⅱサムエル記2・4)。
第三は、さらに7年後、全イスラエルの人々によってイスラエルの王として(Ⅱサムエル記5・3)。
ダビデは、王位に就こうとして自ら画策したことはない。ただ神の約束を信じつゝ、忍耐して待った。自分の意志で動くことをせず、何事にも主の導きを求めた。彼の成功の秘訣は、「主に伺う」こと、そして「神を待ち望む」ことであった。
ダビデは、神の契約の箱を王の都エルサレムへと運び上る。彼はさらに神殿建設の志を抱くが、その事業は、彼の子─ソロモン─のライフ・ワークとして定められていた。
そして神は、ダビデに永遠の王国を約束されたのである。それは、ダビデの子としてお生まれになるイエス・キリストの王国を指し示すものであった。(7・13、ルカ1・31〜33)
ダビデにとって、生涯の汚点となった罪が記録されている。他人の妻バテ・シェバとの姦淫、そして、彼女の夫ウリヤを戦いの最前線に出して戦死させてしまうという、事実上の殺人。
成功の後は怖い。神の人ダビデにも油断があった。しかし、ダビデの偉大さは、その罪を告白し、心から悔い改めたことにある。神は、ダビデの罪を赦された。
その時の心境を、彼は詩篇の中で歌っている。
「幸いなことよ。
そのそむきを赦され、罪をおおわれた人は。
幸いなことよ。
主が、咎をお認めにならない人、
心に欺きのないその人は。
私は黙っていたときには、一日中、うめいて、私の骨々は疲れ果てました。
それは、御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は、夏のひでりでかわききったからです。私は、自分の罪を、あなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。
私は申しました。
『私のそむきの罪を主に告白しよう。』
すると、あなたは私のとがめを赦されました。」(詩篇32・1〜5)
新約聖書の中でもっとも重要な教理は、「神の前に人の罪が赦され、義と認められるのは、行ないにはよらず、イエス・キリストを信じる信仰による。」ということである。ダビデの事件は、この教理の例証として聖書の中に特記されている。(ローマ4・6)
ある聖書教師いわく、「彼は、大罪人だったが、大聖徒だったのである。」
もう一つ見落とせないのは、ダビデの罪は赦されたが、彼はそれ以来、家庭生活において苦しみを味わわされたということ。蒔いた種は刈り取らなければならない。神は、侮られるべきお方ではないのだ。
ダビデの生涯の事業として、イスラエル王国の統一とともに重要なのは、神殿礼拝の確立である。彼はそのために、イスラエルの讃美歌とも言える詩篇の著作と編集を行なっている。彼は、イスラエルの良き歌びとでもあった。
私たちが詩篇を理解し、自分の生活に適用するためには、彼の生涯についての理解が欠かせない。
ダビデは、晩年になって、ある必要のために一つの祭壇を築いた。そのとき購入した敷地に、後日ソロモンの大神殿が建てられることになる。
![]()
列王記ならびに歴代誌も、サムエル記と同様にヘブル語聖書では一つの書になっていた。これらがギリシャ語に翻訳された時、便宜上夫々が二つに分けられた。
列王記の著者は明確ではないが、おそらくエレミヤによって編集されたものであろう。
本書は、イスラエルが多くの王たちのもとで、どのようになっていったかを記している。彼らによるほとんどの王政は、罪悪と無秩序の歴史であると言ってよい。そして、神は人々をどのように扱われたか、その原則を私たちは学ぶことができよう。
ダビデ王はすでに老齢となっていた。彼の息子のひとりアドニヤが、「私が王になろう。」 と言って、野心をいだいた。けれども、ダビデの後継者として神に選ばれたのはソロモンであった。
『ソロモン』は、父ダビデが命名した名前で、『平和』という意味である。
一方、主なる神は預言者ナタンを遣わして、主のために、その名を『エディデヤ』と名づけさせた。その意味は、『主に愛される者』。(Ⅱサムエル記12・25)
こうして、ソロモンがイスラエルの王位に就き、ダビデは死に、その後王国は確立する。
神はあるとき、夢の中でソロモンに仰せられた。
「あなたに何を与えようか。願え。」
彼が願ったのは、民をさばくための判断力と知恵であった。この結果、神はソロモンに知恵だけでなく、彼の願わなかったもの、富と誉れをもお与えになった。
ソロモンの生涯の最大の事業─ライフ・ワーク─は神殿の建設である。父ダビデがその志を抱いたが、神はそれをお許しにはならなかった。人は夫々に、神によって割り当てられた仕事がある。
神の宮の完成までには七年かかり、その後十三年かけて、ソロモンは自分の宮殿を建てた。
ソロモン王は、富と知恵とにおいて、地上のどの王よりもまさっていた。その名声を伝え聞いた全世界の王たちは、彼に謁見を求めた。シェバの女王はそのひとりである。
繁栄の絶頂にあるときに神を忘れないでいることは困難である。ソロモンの没落をもたらしたのは、この栄光そのものであった。彼は、多くの外国の女性を愛した。その妻たちが彼の心をほかの神々のほうへ向けたのである。彼の心は、父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。
ソロモンはその晩年において偶像礼拝を行ない、イスラエル王国は主なる神によって引き裂かれることになる。
王国の分裂と衰退(12〜22章)
神はソロモンに敵対する者たちを起こされ、彼の子レハブアムの代になってイスラエル王国は分裂するに至った。主なる神は王国を引き裂き、十部族をヤロブアムにお与えになった。以後、そちらを北王国、あるいは狭い意味でイスラエルと呼ぶ。
一方、主はダビデのためにレハブアムに一つの部族を残された。それは、王の都エルサレムで一つのともしびを保つためであった。こちらが南王国、あるいはユダと呼ばれている。
これ以後、北王国の王はヤロブアムからホセアまで十九人、南王国の王はレハブアムからゼデキヤまで二十人、合わせて三十九人の王たちが、交互に列王記の中に登場してくる。(別資料《王国の歴史》参照)
ユダ王国には善い王もいたが、イスラエル(北)王国の王は一人の例外もなく悪い王であった。それは、最初の王ヤロブアムが金の子牛を二つ造り、王国内に偶像礼拝をもたらしたからである。(12・28)
これに加えて、七代目のアハブの時代には、バアル礼拝が持ち込まれた。彼が異邦民族シドン人の王の娘イゼベルを妻にめとったことによる。(16・31)
こうして、その影響は南にも及び、二つの王国は次第に衰退の道をたどって行く。
王国の歴史において見逃すことができないのは、預言者の活動である。エリヤは北王国の暗黒の時期、すなわち偶像礼拝が最も盛んであったアハブ王の時代に、神によって遣わされた預言者であった。聖書の中には、エリヤの行なった多くの奇蹟が記されているが、彼の主な使命はバアル礼拝の撲滅にあったのである。
神は偶像礼拝を忌み嫌われる。それは霊的な姦淫にほかならない。
![]()
本書は、分裂した王国、イスラエル(北)とユダ(南)の堕落の物語の続編と言える。それは、指導者と民の失敗、偶像礼拝と背教の記録である。
この時代にはまた、多くの預言者が活動した。その背景にあるのは、神の民の背信にほかならない。しかし、預言者たちのメッセージも結局は受け入れられなかった。何人かの王の治世下で宗教改革が行なわれたこともあるが、それも部分的なものに過ぎなかった。そして、捕囚において王国は滅亡する。
エリヤとエリシャ(1〜13・21)
預言者とは、神のことばを神に代わって神の民に語る人のことである。
エリヤとエリシャが活躍したのは、偶像礼拝の最も盛んな時期であった。彼らは、イスラエルの邪悪な王妃イゼベルによって導入されたバアル礼拝を根絶するために神から遣わされた預言者で、聖書の中では『神の人』とも呼ばれていた。
エリシャはエリヤの後継者である。彼はエリヤの霊─スピリット─を受け継いだ。そして、天に引き上げられたエリヤに代わって、さらに数十年にわたり地上での働きを続ける。
エリヤとエリシャの働きの大きな特徴は、数多くの奇蹟を行なって、イスラエルの神こそが真の神であることを証明し、当時の王たちに多大な影響を与えたことであると言えよう。
聖書には、エリヤによる八つの奇蹟、エリシャによる十六の奇蹟が記録されている。或る聖書教師は、二人の預言者としての性格を次のように対照させている。
エリヤは熱烈の人、審判と律法と厳格さの預言者。エリシャは情け深い人、恵みと愛と優しさの預言者。彼の奇蹟の多くは、親切とあわれみの行為だった。
二人の関係は、新約聖書におけるバプテスマのヨハネとイエスの関係によく似ているようだ。
なお、彼らの名前は、夫々重要な意味を表わしている。
エリヤ─私の神は主
エリシャ─私の神は救い
北イスラエルの十九人の王は、すべて悪い王として記されている。 最初の王、ネバテの子ヤロブアムによって始められた金の子牛礼拝は絶えることがなかった。神は多くの預言者をこの国に送り、警告をお与えになった。けれども彼らはそのメッセージに聴くことを拒んだのである。
紀元前八世紀、北王国は当時の世界帝国アッシリヤの王によって捕囚とされる。これは神による審判であった。
ユダの衰退と滅亡(18〜25)
南王国は、二十人の王すべてがユダ部族のダビデの家系による一つの王朝であって、ダビデ王朝と呼ばれてきた。 その中には善い王がいて、宗教改革も行なわれたが、それも表面的なもので終わった。
この王国においては、イザヤ、エレミヤなどの偉大な預言者が活躍した。しかし、北王国の影響もあり、民は彼らの警告に耳を傾けようとはしなかった。
北イスラエルがアッシリヤによって捕囚にされてからおよそ百三十年ほど後、南ユダは、アッシリヤに次いで興った世界帝国バビロンの王ネブカデネザルによって捕囚とされた。王の都エルサレムは破壊され、礼拝の中心であった神殿は焼かれ、王族もバビロンへ連れ去られた。
偶像礼拝は、真の神に対する最も大きな罪であって、霊的姦淫に等しい。すべての悪い行ないは、みなこの偶像礼拝に起因する。捕囚は、「主の目の前に悪を行なった」神の民に対する、神ご自身の審判にほかならなかった。
ところで、イスラエルの捕囚とユダの捕囚との間には大きな違いがある。
捕囚後のイスラエルがどうなったかについては、聖書は明記していない。それに対して、ユダの捕囚期間は七十年と定められ、後に彼らはエルサレムに帰還し神殿を再建する。メシヤはユダから出ることになっていた。
ユダヤ人の歴史は、不従順な子らに対する神の取り扱いの記録であると言われる。けれどもまた、神はバビロン捕囚の間もメシヤの系図を保たせ、イエスがユダヤのベツレヘムでお生まれになるための道を準備しておられたのである。
![]()
歴代誌の内容は、歴史的には殆どがサムエル記の一部を含めて列王記と並行しているが、両者にはまた、いくつかの相違も見られる。
1.列王記はバビロン捕囚が始まって間もなく、歴代誌は捕囚から帰って間もなく記された。
2.列王記は預言者エレミヤによって、歴代誌は祭司エズラによって編集された。
3.列王記は南ユダと北イスラエルのことを公平に取り扱っているのに対し、歴代誌はもっぱら南ユダのことのみを取り扱い、 北イスラエルについては付随的に記している。
4.列王記は政治的、王的であり、歴代誌は宗教的、祭司的である。
歴代誌のギリシャ語訳─七十人訳─の題名は『省略された事柄』である。だから、編集者が第一に意図したのは、サムエル記、列王記の記事の中で省略された資料を提供してそれを補充することだったのかも知れない。
しかし、歴代誌はまた別の目的で編集されたとも考えられる。それは、バビロン捕囚から帰ったユダヤ人の間に神殿礼拝を確立するためであった。言い替えれば、神の選民が真の神との契約に忠実であるように、彼らに警告と励ましを与えることが意図されていたようである。
「この書巻は、ほかの書より独立している書で、選民の歴史を新しい様式で、新しい見地から新しく記録しているものである。同じ事がらが記述されていても、それはちがった見地からしるされている。サムエル記と列王記には、歴史上の事実が見られるが、この書には、それらの事実に関する神のみことばと神のみこころがしるされている。前者では、そうした事実を人間の見地から見ており、後者では、神の見地より見ている。」(ロバート・リー著『輪郭的聖書』より)
歴代誌Ⅰは、大きく三つの部分に分けられる。
系図はアダムから始まり、アブラハム、イサク、イスラエル、その十二人の息子たち、ユダ族、そしてダビデの家系をたどっていく。レビ族についても比較的詳しいが、それは、彼らが祭司の家系であって、神殿礼拝にたずさわる務めを与えられていたからであろう。(別資料《イエス・キリストの系図》参照)
サウルはイスラエルの最初の王として選ばれたが、故意の不従順のゆえに神によって斥けられ、王位はダビデに移る。その過渡期の王として終わったために、簡単に記されているにすぎない。けれども、その原因となった事柄は、私たちにも重大な教訓を与えている。
「このように、サウルは主に逆らったみずからの不信の罪のために死んだ。主のことばを守らず、そのうえ、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで、主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。」(13〜14節)
ダビデは全イスラエルの王となり、エルサレムを征服した。彼の勝利の秘訣は、神の臨在であった。
「ダビデはますます大いなる者となり、万軍の主が彼とともにおられた。」(11・9)
次ぎにダビデは、民の指導者たちと合議し、契約の箱をエルサレムの都へ運び上ることになる。最初、運び方に誤りがあって、神の怒りを招いた。ここには、正しいことを間違った方法で行なうことに対する警告が含まれている。(13、15章)
神の箱が天幕の中に安置されたとき、ダビデは神の前にいけにえをささげ、民を祝福し、楽器をもって主をほめたたえさせた。賛美は礼拝に欠かせない。
ダビデは心の中に、神殿建設の願いを抱いたが、それは神によって禁じられた。その仕事は、彼の子ソロモンに与えられた務めであった。そして神は、ダビデにとこしえの王座を約束される。
彼は、神の宮の建設のためにあらゆる組織を整え、必要な材料を準備し、若いソロモンがその事業を遂行することができるように彼を励ました。
「強く、雄々しく、事を成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神が、あなたとともにおられるのだから──。主は、あなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。」(28・20)
ダビデは長寿を全うして死に、ソロモンが代わって王となった。
![]()
本書では、ダビデの家系について続けて記され、先ず彼の子ソロモンの治世、並びに神殿の建設が強調されている。残りの部分は南ユダ王国の歴史をたどり、それはソロモンの子レハブアムの治世から最終的なエルサレムの壊滅─神殿の破壊─、そしてユダの人々のバビロン捕囚に至る。
歴代誌においては、列王記と対照的に、神の民の歴史が政治的見地からでなく、教会(宗教)的な見地から記され、人間的な立場からでなく神の側の観点から見られていることに注目したい。
神は、ご自身の民の歴史の中に重要な役割を持っておられ、人々の政治的生活は、彼らの霊的生活と深い関わりがある。本書に登場する王はすべて、神に対する忠実さでその善悪が評価されている。 多くの王は悪い王であった。しかし、数人の良い王の治世には何度かの宗教改革が行われた。
本書は、三つの部分に分けることができよう。
ダビデの子ソロモンは、王権を強固にした。彼の神、主は彼とともにおられ、彼を並みはずれて偉大な者とされた。ソロモンは、民を治めるための知恵と知識とを神に求め、主はそれ以上のもの、富と財宝と誉れをもお与えになった。
神殿の建設はソロモンのライフ・ワークであった。彼は、壮大な主の宮を神に献げ、民は主に向かって賛美した。
「主はまことにいつくしみ深い。その恵みはとこしえまで。」
そして、主の栄光が神の宮に満ちた。
ソロモンの祈り。
主は彼に答えて仰せられた。それは、罪を犯しやすい私たちが神との関係を正しく保つために、いつも心に留めておくべきことばである。
「わたしの名を呼び求めているわたしの民がみずからへりくだり、祈りをささげ、わたしの顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、わたしが親しく天から聞いて、彼らの罪を赦し、彼らの地をいやそう。」(7・14)
ソロモンの子レハブアムの代になって、王国は北と南に分裂、本書は専らダビデの家系である南ユダの王について記す。ユダの王たちは、レハブアムからゼデキヤまで、全部で二十名。(別資料《王国の歴史》参照)
ソロモンの祈りにもかかわらず、彼の子孫の王たちの多くは、神に対して忠実ではなかった。しかし、中には善い王もいた。アサ、ヨシャパテ、ウジヤ、ヒゼキヤ、ヨシヤ・・・・。特にヒゼキヤ、ヨシヤの治世の宗教改革は、聖書の歴史の中でも特筆に値するものであろう。彼らは、心を尽くして神を求めた。これこそ、神がご自身の民に願っておられることである。
「主はその御目をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力をあらわしてくださるのです。」(16・9)
主はこれらの王たちを祝福された。しかし、神の助けを得て強くなると、彼らの心は高ぶり、主を求めることを忘れてしまった。宗教改革も結局は部分的なものに終ってしまう。
主は多くの預言者をこの国に遣わし、ご自身の民が悪い道から立ち返るよう、何度も悔い改めを促された。イザヤ、エレミヤは、これらの時代に活動した預言者である。
けれども、結局、彼らは心を閉ざして、イスラエルの神、主に立ち返ることはなかった。
「ところが、彼らは神の使者たちを笑い者にし、そのみことばを侮り、その預言者たちをばかにしたので、ついに、主の激しい憤りが、その民に対して積み重ねられ、もはや、いやされることがないまでになった。」(36・16)
主なる神は、異国の王、バビロンのネブカデネザル王を、ご自身の審判の道具として用いられた。バビロン捕囚はその結果である。
七十年に及ぶバビロン捕囚の後、神はペルシャの王クロスを通して回復の宣告をお与えになった。本書の最後の同じことばをもって、次のエズラ記は始まる。神の救いの計画においては、暗黒の中にも、希望の光が輝いているのである。
![]()
旧約歴史の最後の部分を構成するエズラ記、ネヘミヤ記、エステル記の三書は、相互に密接な関係を持ち、年代としては、紀元前536〜432年の約百年間にわたる事柄を扱っている。
ハガイ、ゼカリヤ、マラキの三人の預言者は、ユダヤ復興のこの時期に活躍した。
エズラ記の要旨は回復であって、バビロン捕囚となったユダヤ人のうち、残りの者がエルサレムに帰還して主の宮を再建し、神の民の生活が整えられて行く。
本書の著者はエズラ自身であろう。彼は、大祭司アロンの子孫であり、またモーセの律法に通じている学者でもあった。伝承によれば、エズラが旧約聖書の正典を結集し、これを一冊の書物にまとめる上で指導的役割を果たしたと言われている。
最初の帰還は、クロス王の命令によってなされた。クロスは神の預言の成就としてバビロン帝国を倒したペルシャの王であった。ユダヤ人の帰国を許可する彼の布告は、イザヤによってすでに預言されていたのである。神は、クロスの生まれる200年も前に、イスラエルの民の解放者、神殿の再建者として、異邦人の王である彼の名を呼んでいる。(イザヤ書44・28、45・1〜4)
ユダヤの歴史家ヨセフスは、ダニエルがこれらの預言をクロスに示し、国王はそれによって大変心を動かされ、捕囚の人々に好意をもったので、彼らの故国への帰還を許す布告を出したのであると記している。神は、ご自身の計画を実現させるために、異邦の王の心さえも動かされることに注目したい。
第一次帰還の指導者がゼルバベルであり、このとき、約五万人の人々がバビロンからエルサレムに帰って来た。
そして、総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアの指揮のもとに、主の宮の再建工事が始まった。ところが、ユダヤ人の敵による妨害が起こって、工事は十五年間中断されてしまった。
この時期に活躍した二人の預言者が、ハガイとゼカリヤである。
彼らの励ましによって、神の宮の工事は再開され、着手してから約二十年後に、この第二神殿(第一神殿はソロモン王によって建てられた)は完成した。
なお、この時もペルシャのダリヨス王の援助があったことを見逃すことはできない。当時の世界を支配したペルシャの王の命令とあらば、ユダヤ人の敵もどうすることもできなかった。これらの事柄の背後にも、全能の神の御手があったと言えるであろう。
ゼルバベルのもとにおける帰還が、紀元前五536年、宮の落成が516年、エズラがバビロンを出発したのが457年であった。したがって、6章と7章の間には約六十年の隔たりがある。
祭司であり、学者であるエズラは、主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルでおきてと定めを教えようとして、心を定めていた。当時は、ペルシャの王アルタシャスタの治世であったが、彼はエズラの願いをみなかなえ、そのエルサレムへの帰還を積極的に援助した。それは、主なる神の御手がエズラの上にあったからである。
神は、捕囚の民のエルサレム帰還に当たって、三人のペルシャの王の心を動かされた。クロス、ダリヨス、アルタシャスタ・・・・。これこそ、最大の奇蹟ではないだろうか。
エズラがエルサレムに帰って来たとき、神の宮が再建されて既に数十年が経過していた。
ところが、そこで彼は実に悲しむべき事実を知らされたのである。先に帰還した人々が神の戒めを破り、偶像礼拝の習慣をもつ土地の住民と縁を絶つことなく、かえって姻戚関係を結んでいるという。しかも、つかさたち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのであった。
エズラの祈り。
彼は、民の罪を自分の罪として、神の前に告白した。そして、民の大集団の悔い改め。エズラは、彼らに、この地の民と外国の女から離れるよう命じた。最後に、外国の女をめとった者のリストが記載されている。
ユダヤ人が異邦の妻子を捨て去った行為は厳しすぎるように思われる。しかし、過去において異邦人との雑婚が、彼らを偶像礼拝に導き、さらにはバビロン捕囚に至った事実を忘れることはできない。捕囚から帰還し、主の宮を再建した選民の生活は、神のことばによってきよめられる必要があったのである。
![]()
エルサレムの回復においては、二つの重要な時期があった。
第一は、紀元前536〜516年。総督ゼルバベルと祭司ヨシュアのもとで、この二十年間に、ユダヤの国民生活の中心である神殿が再建された。預言者ハガイとゼカリヤはこの時期に活躍した。
第二は、紀元前457〜432年。総督ネヘミヤと祭司エズラのもとで、二十五年間に城壁が再建され、エルサレムは要塞都市に復興し、更に、神の民の宗教生活における改革が行われている。預言者マラキは、この時期に活躍した。
エズラ記はこの二つの時期について記述しているが、ネヘミヤ記は第二の時期についてのみ記している。
バビロンからの帰還は三回あった。
第一回。 紀元前536年、ゼルバベルのもとにおける帰還。
第二回。 紀元前457年、エズラのもとにおける帰還。
第三回。 紀元前444年、ネヘミヤのもとにおける帰還。
ネヘミヤがバビロンからエルサレムに上ったとき、エズラはすでに十三年間その地にあり、祭司として、また律法学者として人々に神のことばを教えていた。
しかし、ユダヤ人の最初の帰還以来、百年近くが経過していたが、神殿の再建はなされたものの、エルサレムの城壁は依然として破壊されたままであった。城壁の再建工事を妨害する強力な敵がおり、彼らは非常な困難の中に置かれていたからである。
この大事業のためには、勇敢なリーダーが必要であった。ネヘミヤはこのような状況の中で、ペルシャ王からエルサレム再興の権限を与えられて、総督として帰還したわけである。
ペルシャ王による帰還の許可(1・1〜2・8)
ネヘミヤは、献酌官(給仕)として、ペルシャの王アルタシャスタに仕えていた。
異邦の王の心を動かしたのは、ネヘミヤの祈りであったに違いない。彼は祈りの人であり、神から託された大事業遂行に当たって、文字通り絶えず祈った。(1・4、2・4、4・4、9、5・19、6・9、14、13・14、22、29、31)
彼の生涯を通して教えられる主な教訓は、神のために働き、成功するには、祈り、労苦、忍耐が必要だということである。
なお、ユダヤ婦人エステルは、ユダヤ人が最初にエルサレムに帰還してから約六十年後にペルシャの王妃となった。アルタシャスタ王は、王妃エステルの継子にあたる。
エズラとネヘミヤがエルサレムへ行った時期、エステルはおそらくまだ健在で、彼らの事業を側面から支援したことは想像に難くない。
エルサレムの城壁の再建(2・9〜7・73)
城壁の再建工事は、数多くの敵による妨害を受けることになる。彼らは軍隊を動員して、エルサレムに攻め入った。しかし、信仰と祈りをもって、ネヘミヤはユダヤ人たちを統率し、武装させ、夜を徹して工事を進めた。外部の敵だけでなく、内部の敵─ユダヤ人の代表者たちの不正と民の不満─とも戦わねばならなかった。
そして、幾多の障害にもかかわらず、城壁は五十二日間で完成した。こうしてエルサレムは、紀元前586年の滅亡後百四十二年で、再び要塞都市となった。
エズラによる宗教改革(8・1〜10・39)
先に神殿が再建され、ここに城壁の修理が完了してエルサレムの外観が整った。
次には、民の生活が聖別されなければならない。そこで、祭司エズラは律法の書─神のことば─を朗読し、レビ人たちは人々に理解できるように、それを解き明かした。この結果、民は自分たちの罪と、先祖の咎を告白し、主を礼拝し、神の戒めに従うための誓約に加わった。
私たちの生活を整えるために最も大切なのは、神のことば─聖書─である。
ネヘミヤによる諸改革(11・1〜13・31)
ネヘミヤは、一時ペルシャの王宮に帰り、不在であった時期がある。再び帰国した後、更に改革の必要を知らされた彼は、勇気をもって改革を断行し、主の律法の違反を正したのであった。
![]()
本書は年代的にはネヘミヤ記よりも前、エズラ記6章と7章の間に位置している。
内容は、バビロン捕囚に続く時代の、神の選民ヘブル民族絶滅の危機からの救助である。ユダヤ婦人エステルは、その中で大きな役割を演じた。
エステル、王妃として選ばれる(1・1〜2・18)
ペルシャの王アハシュエロスは大宴会を催し、酒で心が陽気になった時、王妃ワシュティに命じた。王冠をかぶり王の前に出て来るようにと・・・・・。彼女の美貌を、民と首長たちに見せるためであった。しかし、王妃は王の命令を拒んだ。王は憤り、ワシュティを王妃の位から退けてしまう。
その後、容姿の美しい未婚の娘たちの中から、王の心にかなう一人のユダヤ人のおとめ─エステル─が代って王妃に選ばれた。彼女は小さいときに両親を亡くし、いとこにあたるモルデカイが彼女を自分の娘として養育したのである。その時、モルデカイは、王の門番であった。
エステル、同胞ユダヤ人を救う(2・19〜7・10)
一つの挿話がある。
モルデカイが王の門のところにすわっていた時に、アハシュエロス王暗殺の計画を知った。モルデカイは、このことを王妃エステルに知らせ、エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。その結果、事実が明らかとなり、関係者は処罰されて、この件は王の前で年代記の書に記録された。
さて、アハシュエロス王は、ハマンという名の人物を重んじ、彼を王に次ぐ最高の位につけた。王の家来たちはみな、ハマンに対してひざをかがめてひれ伏した。しかし、モルデカイはそうすることを拒否した。ユダヤ人である彼は、真の神以外のなにものをも礼拝することはしなかったからである。
ハマンはこのことを知って憤りに満たされ、モルデカイひとりに手を下すことだけで満足せず、王国中のすべてのユダヤ人を根絶やしにしようとする。そして、ユダヤ人虐殺の日が、プル、すなわちくじによって決められ、アハシュエロス王の名でその法令が発布された。
ユダヤ人のうちに起った大きな悲しみと、断食と、泣き声と、嘆き!
モルデカイは、自分の民族の救助のために王にあわれみを求めるよう、王妃エステルに依頼した。
「あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、この時のためであるかもしれない。」(4・14)
エステルは、命を賭けて王のところへ行き、幸い彼女は王の好意を得ることができた。
一方、以前にモルデカイがアハシュエロス王のいのちを救ったにもかかわらず、栄誉を受けていなかったことが偶然にも王に知られ、彼はハマンの上に位する栄誉を与えられることとなった。同時に、ハマンのユダヤ人絶滅の奸計も王の目に明らかにされて、彼は処刑されるに至る。
ユダヤ人の復讐(8・1〜10・3)
ところで、ペルシャの法律によれば、ひとたび王の名で発布された命令は、だれも─当の王でさえも─取り消すことはできなかった。ハマンがいなくなったとは言え、ユダヤ人虐殺の日を定めた法令は効力を持っていた!
そこで、それに対抗するために、新しい法令が王の名によって発布されることになったのである。その法令とは・・・・・、ユダヤ人が殺害されることになっていた同じ日に、彼らを襲う者を逆に滅ぼし、その家財をかすめ奪うことを許すという内容のものであった。
その日、ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変して、ユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。それ以来、この日はユダヤ人の喜び、楽しみ、祝いの日となり、くじ(プル)にちなんで、プリムの日と呼ばれている。これがプリムの祭りの起源である。
エステル記のメッセージは、『神の摂理の真実性』ということ。本書の中には、神の名が一度も記されていない。しかし、著名な聖書注解者のマシュー・ヘンリーは、
「ここには神の名はないが、神の指がある」と書いている。
或る人は、本書を『摂理のロマンス』と言った。神は、人間の生活のすべての面に係わりを持ち、そのご計画が成就して行くために、ごく普通の出来事をもお用いになる。
「神の摂理とは、神が前方を眺めて神の民の直面する危機を知り、その備えをされることを言う。そのような場合、神は神の民を救出するために特別な奇蹟を用いず、御自身の意志を成就するために、罪深い人間の行為と計画をも含め、普通の事件を用いられる。その故に摂理は最も大いなる奇蹟である。」(W・ペイプ)
エステルは、自分の民を絶滅の危機から救った。しかし、その背後には、メシヤの系図が絶えることのないように、主権をもって働かれる神がおられたのである。
![]()
旧約聖書には『詩歌書』又は『知恵文学』と呼ばれる一群の書巻がある。すなわち、ヨブ記、詩篇、箴言、伝道の書、雅歌。本書はその最初のものである。
ヨブ記は、苦難の問題を取り扱う。全体を通して説かれている主題は、「なぜ義人が苦しむのか」。
プロローグ(1・1〜2・10)
義人ヨブには七人の息子と三人の娘があり、彼はまた大富豪であった。
さて、天上で会議が開かれている。神ご自身、御使いたち、その中にどういう訳かサタンもいた。
神はヨブの潔白なことを保証し、サタンに対して挑戦される。サタンは神の前にヨブを訴える。サタンの主な働きは、神の前に絶えず私たちを告訴することだ。神は、サタンに制限付き許可をお与えになった。
「では、彼のすべての持ち物をおまえの手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。」(1・12)
ある日、ヨブのもとへ悪い知らせが次々と届いた。彼は一日のうちに、全財産─家畜としもべたち─、さらに七人の息子と三人の娘を失ってしまう。
しかし、ヨブは悲嘆の谷間に落されながらも、主なる神を礼拝し、主の御名をほめたたえている。
「私は裸で母の胎から出て来た。また、裸で私はかしこに帰ろう。
主は与え、主は取られる。主の御名はほむべきかな。」(1・21)
彼はついに、神に愚痴をこぼすことはなかった。
天上で再び会議が開かれた。サタンは、またも神の前にヨブを訴えている。この時も、主はサタンに制限を設けて、許可をお与えになった。
「では、彼をおまえの手に任せる。ただ彼のいのちには触れるな。」(2・6)
サタンは、ヨブの足の裏から頭の頂まで、悪性の腫物で彼を打った。ヨブの妻は彼に言った。
「神をのろって死になさい。」
サタンの意図は、神の子どもたちに神をのろわせることである。しかし、ヨブはこのようになっても、すべてのことが神の御手から出ていることを認め、罪を犯すようなことを口にしなかった。
ヨブと彼の友人たち(2・11〜37・24)
三人の友人たちがヨブを慰めるためにやって来た。彼らは、神は悪を罰するお方であり、ヨブの苦難は彼の罪の結果であると交互に主張する。それに対してヨブは、彼が罪を犯しているという非難を拒否し、自分は正しいと言い張った。
これは、両者共に間違い。
終わりに、ヨブと三人の友人の論争を聞いていた若者エリフが発言した。人が神のなさることを理解できなくても、神に不正はない。だから、全能者の正しい計らいに信頼し、神を恐れよ・・・・と。
ヨブと神(38・1〜42・6)
最後に、神ご自身がヨブに語られる。神は、ヨブがなぜ苦しまなければならないのか、その理由を彼に説明しようとはなさらない。むしろ、創造と摂理の神秘を示して、逆にヨブに問われる。
「わたしが地の基を定めたとき、あなたはどこにいたのか。」
「あなたは海の源まで行ったことがあるのか。」
「あなたは・・・・・知っているか。」
「あなたには・・・できるのか。」
彼は答えることができない。遂に、ヨブは神に降伏する。
「あなたは、どんな計画も成し遂げられることを、私は知りました。まことに、私は、自分で悟りえないことを告げました。私はあなたのうわさを耳で聞いていました。しかし、今、この目であなたを見ました。それで私は自分をさげすみ、ちりと灰の中で悔い改めます。」(42・2〜6)
エピローグ(42・7〜17)
ヨブは、自分を苦しめた三人の友人たちのために神に祈る。神は、ヨブの前の半生よりあとの半生をもっと祝福された。
苦難は、時には訓練のために与えられる。
義人ヨブの隠された罪とは、神よりも自分を正しいとする自己正義だったと言えるだろう。神は、試練を通して、そのことを明らかにされ、ヨブがそれを悟ったときに、彼に対する神の取り扱いは終わったのである。
神が私たちに願っておられるのは、私たちがどのようなときにも、自分の判断にではなく、神ご自身に信頼を置くと言うことではなかろうか。
![]()
原語の題名は『テヒリーム』、訳せば『賛美の書』である。ここに含まれる百五十の詩の中心思想は礼拝であり、これらは礼拝音楽のために使われ、種々の楽器に合わせて聖歌隊によって歌われたようだ。
マイヤー・パールマンの聖書概論によれば、
「歴史書においては、神が人間について語っておられ、預言書においては、神が人間に語っておられ、詩篇においては、人間が神に向かって語っている。」
詩篇は神の民イスラエルの国民讃美歌であり祈祷書であるとも言えるであろう。
ダビデの詩篇
ダビデが主要な作者また編集者と考えられるので、本書はダビデの詩篇とも呼ばれている。だから、これはイスラエル王国の黄金時代の成果である。詩篇の編集と神殿礼拝の確立は、王国の統一にもまさるダビデの功績と言えよう。
詩篇の中には、神を信じる者の赤裸々な感情が表わされている。そして、ダビデ自身の味わった様々な生活が、詩篇を解く重要な鍵となっていることは否めない。彼は逆境の中で、苦悩、悲嘆、迷い、疑い、恐れ、失望、憎悪を経験した。
一方、安楽な環境に置かれた時に、ふとした気の弛みから大きな罪を犯した。ダビデはそれらを決して隠してはいない。
そして、詩篇の全体を貫いて見られる調べは、神への信頼と賛美である。これこそ、ダビデの信仰告白であった。此の信仰によって、彼は神の救い、いつくしみ、また赦しを実際に体験したのである。
詩篇の分類
詩篇は五巻にまとめられる。すなわち、1〜41篇、42〜72篇、73〜89篇、90〜106篇、107〜150篇。各巻は頌栄をもって終わり、最後の第150篇は全体が頌栄となっている。
古くからあるユダヤ人の説明では、「モーセは五巻の律法をイスラエル人に与え、ダビデはそれに対して五巻の詩篇を与えた」とされている。
別の分類法もある。内容または主題によって分ければ、教訓、賛美、感謝、悔い改め、信頼、悩み、希望、歴史、預言─メシヤ詩篇─・・・・・・。
メシヤ詩篇について一言。イエス・キリストを指し示す預言的な詩が、キリストの来られる千年も前に書かれている。
復活された主イエスご自身が、弟子たちに語られた。
「わたしについてモーセの律法と預言者と詩篇とに書いてあることは、必ず全部成就する・・・。」(ルカ24・44)
直接にはダビデ自身についてと思われる記述の背後に、『ダビデの子』としておいでになるメシヤを暗示している箇所が少なくない。2篇、8篇、16篇、22篇、40篇、45篇、69篇、72篇、110篇、118篇等は、最も明白なメシヤ詩篇と言われている。
詩篇の使い方
もともと、詩篇は歌われるために書かれた。多くの詩篇には表題がつけられている。
たとえば、
「指揮者のために。弦楽器に合わせて。ダビデの賛歌」
「指揮者のために。『暁の雌鹿』の調べに合わせて。ダビデの賛歌」。
だから、どのような時にも私たちは神に向かって歌うべきだ。詩篇は賛美の霊に満ちている。私たちが詩篇のことばを使って神をほめたたえるなら、教会はどれほど徳を高められることだろうか。
詩篇は、また祈りの書である。私たちが神に祈るときに、心の思いをどのように表現したらよいか分からないことがあるのではないだろうか。詩篇のことばを使って祈ったらよい。詩篇の記者は、私たちと同様の経験を三千年も前に経験し、それらを神の霊感によって言い表わし、記録してくれた。
H・C・ミアーズ著『旧約聖書の概説』に書かれている。
「深い欠乏を覚えるとき、いつもあなたは、あなたの深い感情を表現する詩篇を見出すことができる。あるいはあなたが大きな喜びを持っているなら、それを表現することばが詩篇の中にあるのである。」
英国の有名な説教家C・H・スポルジョンは、詩篇大注解書の著作が完結したときに、次のような輝かしい証しのことばを記した。
「ダビデとともに黙想し、ともに悲しみ、ともに希望をいだき、またともに喜びつゝ過ごした日は実に幸いであった。詩篇は、翼とことばとを用いることを私たちに教え、また、私たちを天にかけのぼらせ、歌をうたわせるものである。」
![]()
本書は、旧約聖書の詩書、又は知恵文学と呼ばれる五つの書巻の第三番目のものである。
『箴言』の意味は『知恵の言葉』で、ソロモンの箴言とも呼ばれている。
ソロモンの時代にイスラエル王国は黄金時代を迎えた。彼が、父ダビデに替わって王座に着いたときに、彼は民をさばくための知恵を神に求めた。
「神は、ソロモンに非常に豊かな知恵と英知と、海辺の砂浜のように広い心とを与えられた。」(Ⅰ列王記4・29)
彼は三千の箴言を語り、彼の歌は千五首もあった。すべての国の人々、すべての王たちがソロモンの知恵を聞くためにやって来たと言われる。本書にはその箴言の一部が含まれているのであろう。
彼のライフワークは神殿の建設であったが、箴言の著作にはそれに優るとも劣らぬ価値があると言えるのではなかろうか。
この書は、モーセの五書や詩篇と同じく、題目によって五部に分けられる。
1.ソロモンの箴言(1〜9章)
2.ソロモンの箴言(10〜24章)
3.ユダの王ヒゼキヤの人々が書き写したソロモンの箴言(25〜29章)
4.アグルのことば(30章)
5.マサの王レムエルのことば(31章)
詩篇の主な作者はダビデであった。同様な意味で、箴言の大部分は、ソロモンによって書かれた。
詩篇は信仰の書。
箴言は実践倫理の書。
神の民は、未来の贖い(救い)を待つ者ではあっても、現在の義務、しなければならないことを忘れてしまってはいけない。この書は、古来、「若い人を成功に導くのに最良の案内書」と呼ばれてきた。
ヘンリエッタ・C・ミアーズ著
『旧約聖書の概説』に、両者は次のように対比されている。詩篇には、ひざまずいているキリスト者が見出される。 箴言には、両足で立っているキリスト者が見出される。
詩篇は、キリスト者の礼拝のためのもの、箴言は、キリスト者の歩みのためのものである。
詩篇は、密室の祈りのためのもの、箴言は、職場、家庭、運動場のためのものである。
本書で推奨されている徳目は、
知恵を追い求めること、
親孝行、
施し、
家庭を大切にすること、
仕事の関係で正直であること等々。
一方、非難されている不道徳は、
飲食の不節制、
放蕩、
偽り、
怠惰、
争い好きなこと、
悪い仲間との交際等々。
箴言は、神を恐れることの大切さを特に強調している。
「主を恐れることは知識の初めである。」(1・7)
「主を恐れることは知恵の初め、聖なる方を知ることは悟りである。」(9・10)
本書を学ぶ最も良い方法は、題目による研究である。
例えば『知恵』について。
そして、この書は人間を二種類に分けていることが判る。すなわち、知恵のある者と愚かな者。もし、『愚かな者』ということばを探すなら、全部で八十回ほど出てくる。それらを書き出すことによって、貴重な教訓を得ることができるだろう。
ところで、聖書全体はキリストについて記されていると言われる。
「それから、イエスは、モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事がらを彼らに説き明かされた。」(ルカの福音書24・27)
だから、私たちは箴言の中にもキリストを発見することができる筈だ。このような箇所がある。
「主は、その働きを始める前から、そのみわざの初めから、わたし(知恵)を得ておられた。・・・
神が天を堅く立て、深淵の面に円を描かれたとき、わたし(知恵)はそこにいた。
神が・・・・地の基を定められたとき、わたし(知恵)は神のかたわらで、これを組み立てる者であった。」(8・22〜30)
これを、新約聖書のヨハネの福音書1章1〜3節、コロサイ人への手紙1章15〜16節、ヘブル人への手紙1章2節等と対照させて見れば、『知恵』を『キリスト』と置き換えて読むこともできよう。
箴言は、人生に有用な知恵で満ちた宝の書である。私たちも、この書の中に宝捜しをしよう。きっと、金や銀にまさる宝(みことば)を発見することだろう。
![]()
箴言、伝道者の書、雅歌は、いずれもダビデの子ソロモンによって書かれたと言われている。箴言は彼の治世の初めの頃、ソロモンが神とともに歩んでいた時のもの、伝道者の書はその晩年、彼の心が主なる神から離れていた時期のものであろう。
箴言には神からの知恵のことばが記されているが、本書においては、神から離れた人間の知性が真理と幸福を追い求めている有様が見られる。
本書のヘブル語本文の題は『コーヘレト』で、これは元来一つの職を表わし、『集会を招集する者』、『説教者』、『伝道者』等の意味を持つものであった。ギリシャ語訳聖書─七十人訳聖書─では『エクレシアステース』で、英訳聖書はそれに拠っている。本書は、魂の自伝、あるいは体験の書であり、恐らくソロモンが自らの背教による悲しい経験を通して学んだ教訓を、神の民に対して公に語るために書かれたのではなかろうか。
本書の全体を流れる調べは、或る種の悲哀だろう。
「空の空。・・・・・。空の空。すべては空。」(1・2)
『空』と訳されていることばが全部で三十五回、また、人間の努力のむなしさ表わすために、『風を追うようなもの』、或るいはそれに類する表現が十回使われている。そして、この世の価値観を表わす『日の下で』が二十九回。
それに対して、『主』(ヤーウェ)という契約の神の名が一度も出てこない。
本書は、奇妙なことに、無神論者には常に喜ばれていたようだ。神を除いた、その哲学的理論を立証するために、この書を好んで使ったらしい。確かに伝道者の書には、多くの健全な教えと共に、聖書の他の教えと矛盾する教義がかなり含まれている。
例えば、
「空の空。空の空。すべては空。
日の下で、どんなに労苦しても、それが人に何の益になろう。」(1・2〜3)
「殺すのに時があり、いやすのに時がある。」(3・3)
「愛するのに時があり、憎むのに時がある。」(3・8)
「人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねば、あれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣にまさっていない。すべてはむなしいからだ。みな同じ所に行く。すべてのものはちりから出て、すべてのものはちりに帰る。」(3・19〜20)
「私は快楽を賛美する。日の下では、食べて、飲んで、楽しむよりほかに、人にとって良いことはない。」(8・15)
聖書は、神の完全な霊感を受けた、誤りのない基準書なのではないか?なぜ、本書が旧約聖書正典の中に入れられているのか?
このことについては、以下のように説明されてきた。すなわち、この書の中の議論は、神の議論ではなく、人間の議論に関する神の記録なのだと。
「私は知った。」
「私は心の中で言った。」
と何度も記されている。
しかし、
「主はこう言われる。」という句はない。
同じような意味で、聖書はほかにも、悪人たちの多くの言葉を含んでいることを私たちは知っているだろう。サタンのことばさえ記録されているではないか。この場合、その言葉は霊感されたものではないが、その記録が霊感されているのである。
ソロモン王の心が神から離れたとき、彼は人間的視点に立って幸福を追い求めた。ソロモンは何によって満足を得ようとしたのか?
それは、
科学(1・4〜11)
哲学(1・12〜18)
快楽─歓楽、飲酒、事業、財産、音楽─(2・1〜11)
唯物論(2・12〜26)
宿命論(3・1〜15)
理神論(3・16〜4・16)
自然宗教(5・1〜8)
富(5・9〜6・12)
道徳(7・1〜12・12)
けれども、これらによって彼の心が完全に満たされることはなかった。
A・T・ピアソン博士はこう語っている。
「伝道者の書を解く鍵は、人間はこの世界にとって大きすぎるということである。」
人は、元来、神のかたちに創造された。だから、神のみが人間の心に本当の満足を与えることがおできになり、神から離れては人生は退屈と失望に終わるだけであろう。
人間の本分は、神を畏れること。
それが、本書の最後の2節に記されている結論である。そして、そのような生活に入るのは早いほどよいのである。
「あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。わざわいの日が来ないうちに、また『何の喜びもない。』と言う年月が近づく前に。」(12・1)
![]()
表題は『ソロモンの雅歌』。ソロモンは千五首の歌を作った。ヘブル語聖書の題は『歌の中の歌』となっている。だから、雅歌は多分、彼が作ったものの中で最上の歌なのであろう。
旧約聖書の中で、本書ほど誤解され、その解釈と分解の困難な書巻は、他にないのではないか。しかし、ユダヤ人は雅歌を最も価値あるものと信じていた。彼らは箴言を神殿の外庭に、伝道者の書を聖所に、そして雅歌を至聖所にたとえたと言われる。
またジョナサン・エドワード、ハドソン・テーラー、バークレー・バックストンその他、キリスト教の歴史の中で最も霊的な心の持ち主だった人々が、好んでこの書を愛読したことは事実である。
雅歌は、東洋の詩の形式を使った結婚における愛の歌であり、登場人物はソロモンとシュラムの女とエルサレムの娘たちであって、一般には、三重の意味を含むとされている。
1.シュラムの女に対するソロモンの愛
「表面的には、本書は夫婦生活の喜びの賛歌で、その本質は夫婦愛の熱い喜びをやさしくかつ真実に表わした点に見いだされる。本書はそれ以上の何ものでもないとしても、またそれに神の名がどこにも示されていないとしても、なお神の言葉のうちに位置を占める価値がある。そもそも結婚は神が定められたものであり、人生の幸福と福祉の大半は、結婚生活における正しい相互の態度にかかわるものである。」 (ヘンリー・ハーレー)
人類最初の結婚が、人が罪を犯して堕落する以前に行われていたのは意義深いことである。結婚は、創造の神が初めから意図しておられたことであった。
2.選民イスラエルに対する神の愛
比喩的に見るなら、卑しい娘に対するイスラエルの王ソロモンの自発的な愛は、契約の民に対する神の愛を示しているとも解釈されよう。旧約聖書の中で、イスラエルの民は主なる神の妻と呼ばれている。(イザヤ54・5、6、エレミヤ2・2、3・1、エゼキエル16章、23章、ホセア2章)
過去の歴史において、彼らは何度も神に背を向け、異国の民の神々を拝んだ。このことは、夫である神の目には霊的姦淫と写った。それにもかかわらず、神は淫行の妻、ご自身の契約の民イスラエルに対して愛の御手を差し伸べて来られたのである。
「『主は、あなたを、夫に捨てられた、心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようか。』
とあなたの神は仰せられる。
『わたしはほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、
大きなあわれみをもって、あなたを集める。
怒りがあふれて、ほんのしばらく、わたしの顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもって、
あなたをあわれむ。』
と、あなたを贖う主は仰せられる。」(イザヤ54・6〜8)
3.教会に対するキリストの愛
新約聖書では、教会はキリストの『花嫁』と呼ばれている。(Ⅱコリント11・2、エペソ5・25〜32、黙示録19・7、21・2、22・17)
だから、雅歌に描写されている男女の愛は、教会に対するキリストの愛を象徴的に表わしているとも言える。
「ソロモンのこの可憐な少女に対する熱愛は、真実で疑う余地のないものであったろう。しかも彼はメシヤを生み出すべき家系の王であった。それで彼の結婚がメシヤと花嫁との永遠の婚姻を予表するものと考えることに何の不合理もなかろう。雅歌の喜びは小羊の婚姻の宴席のハレルヤの絶頂のうちに見いだされよう。黙示録19・6〜9」(ヘンリー・ハーレー)
今日の教会で、キリストに対する人格的な愛ほど必要とされているものはない。雅歌の中に、特に印象に残る同様のことばが三回記されている。
「エルサレムの娘たち。
私は、かもしかや野の雌鹿をさして、あなたに誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目ざめたいと思うときまでは」(2・7、3・5、8・4)
愛は外から強制されて持てるものではなく、内から芽生えてくるものである。イエス・キリストが
『私』のためにしてくださった贖いのわざを知ることによって、私たちの心に、このお方に対する本当の愛が目ざめてくるのではなかろうか。そして、キリストに対する個人的な愛が土台となるときに、私たちの奉仕は─それがどのようなものであっても─、神に喜ばれるものとなるに違いない。![]()
ヘンリー・ハーレー著『聖書ハンドブック』には、次のように要約されている。
「創世記からエステル記にいたる旧約聖書の歴史書は、ヘブル民族の興亡の物語である。
ヨブ記から雅歌にいたる諸書は、大体において、ヘブル民族の黄金時代に書かれたものである。
イザヤ書からマラキ書にいたる預言書は、ヘブル民族の衰退期に属している。」
預言者は、イスラエルの歴史の暗黒時代に、神によって立てられた人たちであった。旧約聖書の預言書は全部で十七、著者は十六人。そのうちエレミヤは、『エレミヤ書』と『哀歌』を書いている。
預言者の活動の主な背景となったのは、神の選民の背教、偶像礼拝、王国の分裂、衰退、滅亡、捕囚、復興である。これらの預言者たちは、王、指導者、民に対して、臆することなくその罪と失敗を指摘した。彼らは、祖国の復興を熱望する愛国者であり、常に神の立場から国民の良心に向かって語り続けたのである。ある意味では、預言者はその時代の最も人気のない人たちだったと言えるかも知れない。
預言書を正しく理解するためには、旧約の預言者たちの「イスラエル的」性格を心に留めておくことが必要だろう。預言者はすべてヘブル人であり、また、その務めにおいては、常に神の契約の民、すなわちイスラエル民族のことが念頭に置かれていた。
彼らの罪、失敗、捕囚、離散、回復、そして栄光に輝く未来・・・・。
その他の民族─異邦人─については、ただ次のような観点から述べられている。
1.背信のイスラエルを懲らしめる道具として、神に用いられる。
2.イスラエルを攻撃した、その高慢のゆえに、神の裁きを受ける。
3.将来イスラエルに対して現わされる恵みに、共に与るようになる。
預言書を年代について分類すれば、十四がヘブル民族の滅亡に関係し、三つがその復興に関係を持っている。預言者の活動の全期間は紀元前9〜5世紀、約450年に及んだ。
1.北王国イスラエルの滅亡─アッシリヤ捕囚─。
紀元前734〜721年。
この時期の前後に書かれた預言書は、ヨエル、ヨナ、アモス、 ホセア、イザヤ、ミカの各書。
2.南王国ユダの滅亡─神殿、エルサレムの破壊、バビロン捕囚─。
紀元前606〜586年。
この時期に属する預言書は、エレミヤ(哀歌を含む)、エゼキエル、ダニエル、オバデヤ、ナホム、ハバクク、ゼパニヤ書。
3.ユダヤ民族の復興─バビロン捕囚からの帰還、神殿の再建、エルサレムの修復、宗教改革─。
紀元前536〜444年。
この時期に関係する預言書は、ハガイ、ゼカリヤ、マラキ書。
キャンベル・モルガンは、預言者のメッセージには三つの要素があると述べている。
1.預言者自身の時代へのメッセージ─直接神から。
2.預言された未来の出来事についてのメッセージ。
(1)神の選民の失敗と、彼らとその廻りの諸国民に対する神のさばき。
(2)メシヤの到来と、彼に対する拒絶、彼の終局の栄光。
(3)『メシヤの王国』が究極には地上に打ち立てられること。
3.読者の時代に対する生きたメッセージ─善悪の永遠的原理。
預言のメッセージの中心がメシヤ─キリスト─に関するものであることは言うまでもない。(ルカ24・25〜27、44)
ところで、聖書には二つの全く異なったメシヤ像が描かれている。一つは、苦しみを受けるメシヤ。もう一つは、支配するメシヤ。苦しみと栄光、弱さと力。メシヤのこの二重性の奥義には、預言者自身さえも、とまどいを感じたらしい。
この奥義を解く鍵は、「メシヤの二度の来臨」にある。このことは、新約聖書の啓示によって明らかとなる。
一度目の来臨は、苦しみを通して民を贖うため。二度目の来臨は、栄光のうちにご自身の王国を支配するため。この時、イスラエル民族に対する神の約束が全て成就するのであろう。こうして、預言者たちは、メシヤの来臨を二つの形で描写したわけである。
そして、実はこの二度の来臨の間に『教会時代』が入ってくることになるが、『教会』は旧約聖書の預言書には見られない。それは、預言者たちには未だ啓示されておらず、神が新約の時代まで隠しておかれた奥義だったからである。(エペソ3・1〜6)
![]()
イザヤは、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代の預言者であり、活動の期間は、紀元前8世紀から7世紀にかけて、約六十年位と言われる。
当時の、北イスラエル、南ユダ王国の状態については、Ⅱ列王記15〜20章、Ⅱ歴代誌26〜32章を参照。
背景には、神の選民の堕落─偶像礼拝─と、アッシリヤの王による侵略があった。これは、神の審判であり、アッシリヤはそのための道具と見なされている。北イスラエルのアッシリヤ捕囚は、この間に行なわれた。
イザヤ書は、聖書全体の構造とよく似ている。
聖書は66巻
本書は66章
聖書の二大区分は、第一、旧約聖書39巻、第二、新約聖書27巻
本書の二大区分は、第一、1〜39章、第二、40〜66章(27章)。
旧約聖書は、堕落(創世記)に始まり、メシヤの来臨待望(預言者)で終わる。
本書の第一区分の要旨は『審判』。罪の告発に始まり、新しい時代への待望で終わる。
本書の第二区分の要旨は『慰め』。『荒野に呼ばわる者の声』で始まり、解放者としてのメシヤについて述べ、新しい天と新しい地に至る。
新約聖書は、同じく『荒野に呼ばわる者の声』─バプテスマのヨハネ─に始まり(福音書)、イエス・キリストがメシヤであることを宣言し、新天新地で閉じられている(黙示録)。
イザヤ書の第一区分を更に二つに分け、全体を三つの部分に分解しておこう。
1.審判の部分(1〜35章)
主として、イスラエルの罪に対する譴(けん)責。或る聖書教師が言うように、主は、ご自分の民の繁栄よりも、その純潔に多くの関心を持って おられるようだ。
諸国民に対する審判の預言。神は、イスラエルの罪に対する怒りの鞭として、近隣諸国をお用いになるが、その高ぶりのゆえに、それらの諸国民への報復も必ずなされる。
イスラエルの、栄光ある回復への期待。
なお、ここにはイザヤの預言者としての召命についての記録が含まれている(6章)。
2.歴史的部分(36〜39章)
アッシリヤの王セナケリブの侵略とエルサレムの救い。
ユダの王ヒゼキヤの病気と癒し。バビロン捕囚の預言。
3.慰めの部分(40〜66章)
ペルシャの王クロスによる、捕囚からの解放。
メシヤの苦難を通してのあがない。
神の民─残りの者─の回復と未来の栄光。
旧約聖書から新約聖書への引用は、本書が一番多い。
また、イエス・キリストの全生涯についての預言が数多く記されている。
すなわち、
誕生(7・14、9・6)
家系(11・1)
神性(9・6、7)
油注ぎ(11・2)
性格(11・3、4)
職務(9・1、2、42・1〜7、61・1、2)
死(52・1〜53・12)
復活(25・8)
未来の王国における支配(2・、11・、32・、35・、65・)
このようなわけで、内容が極めて福音的であることから、『第五福音書』とも呼ばれてきた。因みに、『イザヤ』には、「主は救い」という意味がある。
特に、本書の53章には、贖い主イエスの御姿が実にはっきりと啓示されている。
「まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みをになった。
だが、私たちは思った。
彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
しかし、彼は、
私たちのそむきの罪のために刺し通され、
私たちの咎のために砕かれた。
彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、
彼への打ち傷によって、私たちはいやされた。
私たちはみな、羊のようにさまよい、
おのおの、自分かってな道に向かって行った。
しかし、主は、私たちすべての咎を彼に負わせた。」(4〜6節)
また本書には、メシヤの二度の来臨が描写されている。
一度目は、私たちの罪を負うために苦しみを受けるお方として。
二度目は、偉大な力と栄光を帯びて再び来られるお方として。
十字架におけるキリストと、
王座におけるキリスト。
預言者の目は、ひとりのお方の、二つの異なったメシヤ像を正しく捕らえていたのである。
![]()
エレミヤは、イザヤより約百年ほどあとの人である。
アッシリヤによる北イスラエルの捕囚が、イザヤの活動の背景にあったように、バビロンによる南ユダの捕囚が、エレミヤの活動の背景となっている。
彼は、ユダヤ民族のもっとも暗い悲劇的な時代、四十年あまりを、預言者として生きた。
1.エレミヤの召命(1章)
祭司エレミヤは、若くして預言者としての務めに召された。
主のことば、
「わたしは、あなたを胎内に形造る前から、あなたを知り、
あなたが腹から出る前から、あなたを聖別し、
あなたを国々への預言者と定めていた。」
エレミヤは、これを聞いてしりごみした。
「ああ、神、主よ。
ご覧のとおり、私はまだ若くて、
どう語っていいかわかりません。」
神は、ご自身の主権によって人をお選びになる。
エレミヤは感受性が強く、温順な若者であった。神の審判というきびしいメッセージを伝えるのに、なぜエレミヤでなければならなかったのか。
「ああ、それは、さばきに関するきわめてきびしい使命を、力と悲しみのしらべとをもって伝えるためには、心のやさしい人が必要だったからである。ことばの調子というものは、大切なものである。エレミヤは傷心の預言者だった。」(ロバート・リー)
彼は、「泣き預言者」として知られている。
2.ユダに対する審判の預言(2〜45章)
ユダの民は真の神に背を向け、偶像礼拝を行なっていた。これは霊的な姦淫にほかならない。エレミヤはその罪を責め、民に悔い改めをうながす。
「イスラエルよ。もし帰るのなら、─主の御告げ。─
わたしのところに帰って来い。」
これは、背信の民に対する、神の愛と悲しみの叫びではないか。けれども、彼らは向きを変えようとはしなかった。そこで、エレミヤは神の審判を語らないわけにはいかない。それは、バビロン捕囚であった。彼は、王や民の指導者たちに向かって言う。
「あなたがたはバビロンの王のくびきに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよ。」
エレミヤは王や民の指導者たちからおおくの迫害を受け、親族の人たちからも忌みきらわれた。預言者は、自分が語りたいことをではなく、神が語れと言われたことを語らねばならない。ここに、神のことばを預かった者の光栄とともに、苦しみと戦いがある。
「私は、『主のことばを宣べ伝えまい。もう主の名で語るまい。』と思いましたが、
主のみことばは私の心のうちで、骨の中に閉じ込められて
燃えさかる火のようになり、
私はうちにしまっておくのに
疲れて耐えられません。」(20:9)
そのころのユダには、人心を買うために平安を語る自称預言者もいたが、彼らは神から遣わされた人ではなかった。
ところで、ユダに対する神の審判は、民を正しく懲らしめるのが目的であって、彼らを滅ぼすためではない。審判の向こうには、希望の光が見えていた。ある聖書教師が言ったように、本書には黄金の聖句が満ちている。
その一つ、
「わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。─主の御告げ。─それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。」(29・11)
そして、31、33章は、全体が黄金の章と呼ばれている。
3.諸国民に関する預言(46〜51章)
神は、ご自身の民を懲らしめるために、異邦諸国の王をお用いになった。そして、神は諸国民をも審かれる。それは、彼ら自身の高ぶりのゆえにほかならない。
4.歴史的補遺、ユダのバビロン捕囚(52章)
エレミヤはバビロンからエルサレムを救おうとして失敗した。しかし、神の目から見るならば、彼は成功したのである。エレミヤの偉大さは、神が語れと言われたことを忠実に語ったことにある。
「神はメッセージに答えた人の数によらず、伝える際の忠実さによって成功の度をお計りになる。」 (W・ペイプ)
神のご計画の中には、民の捕囚のあとに将来があった。神は常に成功者であられる。ハレルヤ!
![]()
旧約聖書のギリシャ語訳聖書─七十人訳聖書─では、本書にこのような序文がつけられている。
「イスラエルが捕囚となり、エルサレムが荒廃の地と化した後、エレミヤは座して泣き悲しみ、エルサレムに対するこの哀歌を歌い、次のように語った。」
エレミヤが、自分の預言が成就したことを喜ぶかわりに、嘆き泣いていることに注目したい。エルサレムに『エレミヤの洞窟』として知られている場所がある。言い伝えによれば、預言者はここに座り、慟哭(どうこく)しつつ、彼が力をつくして救おうとした町のために悲しみの哀歌を書きつづったのだとされている。
そして、この洞窟は、主イエスが十字架にかかられた『ゴルゴタ』とよばれている丘の中腹にある。
実は、主イエスも、メシヤを受け入れようとしない不信の都エルサレムのために、悲しみの涙を流されたのであった。
哀歌は五つの詩から成っている。そのうちの四つは、日本のいろは歌のような形式になっている。各節が、それぞれヘブル語のアルファベット順の文字ではじまっているのである。これは、詩篇の一部にも見られるもので、記憶を助けるためであった。
おそらく、人々がこれを憶えて愛誦しやすいようにとの意図でつくられたのであろう。この哀歌は、イスラエルの苦難と離散の悲哀を表わすのに、今日まで使われてきた。
金曜日ごとに、ユダヤ人たちは、神殿のあったエルサレム旧市街の一区域に集合する。そこには『嘆きの壁』とよばれる昔の石垣が残っている。そこで彼らは、神の宮の破壊を声をあげて悲しみ、石垣に接吻しながら、涙を流して哀歌の各節を、また詩篇等を唱える。
また、アビブの月(現在の7、8月)の9日─この民の上にふりかかった五つの大きな惨禍を嘆くために聖別された断食の日─には、世界中にあるユダヤ人の会堂において、この哀歌が朗読されていると言う。
本書の目的は、ユダヤ人たちに、その災いの中に神の懲らしめの御手を認めさせ、悔い改めて神に立ち帰らせることにあった。
ロバート・リー氏による概略を以下に示す。
1.第一の詩。エルサレムは、嘆き悲しむやもめのように表現されている(1章)
2.第二の詩。エルサレムは、荒廃の悲しみの中、顔をヴェールでおおった婦人のように表現されている(2章)
3.第三の詩。エルサレムは、さばき主である主の前に、悲嘆して泣き悲しんでいる預言者のように表現されている(3章)。
4.第四の詩。エルサレムは、光を失い、色あせ、価値の少なくなった黄金のように表現されている(4章)。
5.第五の詩。エルサレムは、神に訴える嘆願者のように表現されている(5章)。
この悲しみの歌の中にも、黄金の聖句がある。
「私たちが滅びうせなかったのは、主の恵みによる。
主のあわれみは尽きないからだ。
それは朝ごとに新しい。
『あなたの真実は力強い。
主こそ、私の受ける分です。』と
私のたましいは言う。
それゆえ、私は主を待ち望む。
主はいつくしみ深い。
主を待ち望む者、主を求めるたましいに。
主の救いを黙って待つのは良い。
人が、若い時に、くびきを負うのは良い。
それを負わされたなら、
ひとり黙ってすわっているがよい。口をちりにつけよ。
もしや希望があるかもしれない。
自分を打つ者に頬を与え、
十分そしりを受けよ。
主は、いつまでも見放してはおられない。
たとい悩みを受けても、
主は、その豊かな恵みによって、
あわれんでくださる。
主は人の子らを、ただ苦しめ悩まそうとは、思っておられない。
地上のすべての捕らわれ人を足の下に踏みにじり、
人の権利を、いと高き方の前で曲げ、
人がそのさばきをゆがめることを、主は見ておられないだろうか。
主が命じたのでなければ、
だれがこのようなことを語り、
このようなことを起こしえようか。わざわいも幸いも、
いと高き方の御口から出るのではないか。
生きている人間は、なぜつぶやくのか。
自分自身の罪のためにか。」(3・22〜39)
神殿の破壊、エルサレムの荒廃、バビロン捕囚は、民の罪ゆえの審判の結果だった。神はつねに正しいお方であり、災いも幸いも、いと高き神の命令によるものである。しかし、主が民をさばかれるのは、ただ苦しめ悩ますためではない。患難の中にあっても、主の恵みは朝ごとに新しい。神の民よ、真実の悔い改めをもって主に立ち返れ!
![]()
エレミヤ、エゼキエル、ダニエルは、大体おなじ時代の預言者であり、活動の背景となっているのは、エルサレムの滅亡、神殿の破壊、ユダのバビロン捕囚である。
神の民の最暗黒の時代、エレミヤは主としてエルサレムにとどまって預言活動をした。
ダニエルは、他の数人のユダヤの少年とともに、紀元前606年に、バビロンに連れて来られた。彼は、もっぱら王の宮廷で、イスラエルの神のしもべとして活躍している。
エゼキエルは、ダニエルより九年遅く、紀元前597年、多くの同胞といっしょにバビロンへの捕囚となった。それは、紀元前586年にエルサレムが滅亡する十一年前のことである。彼は捕囚の民の中に住み、バビロンにおいて、エレミヤと基本的に同じメッセージを彼らに語った。
エゼキエルの召命(1〜3章)
エゼキエルがバビロンの地にいたとき、天が開け、彼は神々しい幻を見た。神がエゼキエルに語られた方法は、ダニエルや使徒ヨハネ(黙示録)の場合とよく似ている。
「次のような主のことばが私にあった」。
このような表現は、本書に五十回近く記されている。
「神の最大の伝達は、その心が砕かれた神のしもべらによってだけ成し遂げられる。神の手の中にある器は、自分も他の人たちとともに苦しみにあずかる用意ができていなくてはならない。」(H・ミアーズ)
エルサレム滅亡の預言(4〜24章)
エゼキエルは象徴的行為によって多くを語った。
預言の中心は、エルサレムの滅亡である。捕囚の民は、エジプト人の助けによってバビロンのくびきが取り除かれるという偽りの希望に耽っていた。偶像礼拝の罪から離れなければ、審判は避けられない。
エゼキエルは、民が聞いても、聞かなくても、「神である主はこう仰せられる」と彼らに語らなければならなかった。それは、見張り人としての預言者の使命だ。(33章)
本書の鍵の言葉は『神の栄光』である。神の栄光とは、神の臨在のしるしであり、それは罪のあるところには留まることができない。エゼキエルは、幻の中で、その栄光が神殿とエルサレムから去って行くのを見た。(9・3、10・4、10・18、19、11・22、23)
「主の栄光は徐々に、渋々と、荘厳に、神殿と『聖都』を去り、それから捕囚がやって来る。」
「不従順のために輝きが去ってしまっている干からびたキリスト者生活というものは、実に多くあるのである。」(H・ミアーズ)
異邦諸国に対する審判(25〜32章)
神は、イスラエルとユダに対する懲らしめの道具として、異邦の諸国民を用いられたが、同時に、その高ぶりのゆえに彼らをも罰せられる。この預言がなされたのは、これらの諸国がなお強力なときであった。後に、預言は細かい点に至るまで実現した。 神は全世界の主権者であられる。
イスラエルの回復(33〜48章)
預言されていたとおり、神殿は破壊され、エルサレムの町は滅亡し、ユダの民はバビロンに捕囚となった。この後、エゼキエルの預言には、神の民に対する慰めの要素が多く見られるようになる。
捕囚となったユダヤ人の、故国パレスチナへの復帰、霊的回復、神殿の再建、そして聖地エルサレムにおける神の臨在の約束・・・。
エゼキエルは、幻の中でふたたび神の栄光を見ている。それが、また戻って来た!地はその栄光で輝き、神殿は主の栄光で満ちていたのである。(43・2、4、5)
これは、おそらく、千年王国における神殿の情景ではなかろうか。
マイヤー・パールマンは本書の主題を次のように要約している。
「来るべき審きを見通して、イスラエルから神の栄光が取り去られること、そして、未来の回復を見越して、神の栄光がふたたび帰ってくることを示す。」
「彼ら(あなたがた)は、わたしが主であることを知ろう。」
本書の48章中27の章にこの句が見られ、全部で六十回以上記されている。ユダヤ人は、審判を通してそのことを知った。
バビロン捕囚は、偶像礼拝から彼らをいやした。それ以来、ユダヤ人は偶像礼拝の罪だけは犯したことがない。けれども、彼らは神の御子イエスを十字架につけた。この後、終末に向かって残りの預言が成就していくことにより、彼らはイエスを真のメシヤとして知るようになるであろう。
![]()
本書の著者ダニエルは、彼の少年時代、ネブカデネザルによる最初の捕囚のときに、ユダヤからバビロンへ連れて来られた。
ダニエルの生涯は、バビロンのネブカデネザル王、ベルシャツァル王の時代を過ぎ、バビロンの滅亡の後、ペルシャ帝国の時代に入り、メディア人ダリヨスの治世を経て、ペルシャ人クロス王の第3年にまで及んでいる。
彼は約七十年余、ほぼユダヤ人のバビロン捕囚の期間、世界を支配した大帝国の宮廷において、神の証人として活躍した。
ダニエル書は、新約聖書のヨハネの黙示録と同じように『黙示の書』と呼ばれている。『黙示』、あるいは『啓示』とは、「ヴェール(おおい)を取り除く」という意味である。
悪の力がこの世を支配している時に、なぜ神は黙示をお与えになるのか。その目的は、目に見えるものの背後に隠されている本当の実態を明らかにするため、そして、この地上において、究極的には正義が勝利を収めるということを示すためであった。
黙示的な記述には、様々な異象とか象徴が使われている。神は、ご自身の真理を神の民に伝えるために、このような文学形式をお用いになった。
本書は、王と王国について、王座と主権について記している。多くの歴史的な記録を含むが、一方では、いくつかの預言をも包含している。異邦の王国が次々と起こって、ユダヤ人を支配し圧迫する、いわゆる『異邦人の時』と呼ばれる期間について(ルカ21・24)、さらに、この世の終わりについての啓示が記されている。
また、旧約聖書の中で本書だけ、キリストの初臨─1度目に世に来られること─の時期を定める預言を記していることに注目したい。(9・24〜27)
ダニエルの時代から始まって、神の選民ユダヤ人を支配する世界帝国として預言されているのは、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマであるが、これは、歴史的な事実となった。
しかし、本書の預言はそこで終わっていない。
人間が支配する、どのような強国が起こったとしても、キリスト(メシヤ)が再び来られるときに、その主権は終わりを告げることになるという。したがって、ダニエル書は何よりも、神が全世界を支配される真の主権者であることを宣言するために書かれたものであろう。
ダニエル書は、新約聖書に多く引用されている。特に、主イエスご自身により、終末の時代について・・・。(マタイ24・15、マルコ13・14)
このようなわけで、本書は、黙示録を解釈するための鍵ともなっているわけである。
本書を以下のように分解しておく。
A.歴史的部分
1.バビロンの宮廷における、ダニエルの初期の生活(1章)
バビロンで受けた教育
彼の三人の友人
2.ネブカデネザルの夢(2章)
ダニエルの解き明かし
バビロンとその後に興る国々の未来に関するもの
3.三人のヘブル人の若者たち、燃える火の炉から救い出される(3章)
ダニエル三人の友人たちが、ネブカデネザル王の建てた金の像を拝むことを拒否
王の怒りと燃える火の炉、救出
4.ネブカデネザルの夢(4章)
ダニエルの解き明かし
王の高ぶりと神の刑罰
神の主権
王のへりくだり
5.ベルシャツァルとダリヨスの治世におけるダニエルの経験(5〜6章)
宮殿の壁に書かれた不思議な文字とダニエルの解き明かし
バビロン王国の滅亡
ダリヨスの禁令とダニエルのとった態度
獅子の穴
B.預言的部分
6.ダニエルの見た夢(7章)
四頭の獣
獅子─バビロン帝国
熊─メド・ペルシャ帝国
ひょう─ギリシャ帝国
第四の獣─ローマ帝国
永遠の王国
7.ダニエルの見た幻(8章)
雄羊─メド・ペルシャ帝国
雄やぎ─ギリシャ帝国
ペルシャ人がギリシャ人に滅ぼされること
神の宮の冒涜
8.ダニエルの祈りと70週に関する預言(9章)
9.ダニエルの見た最後の幻(10〜12章)
ペルシャとギリシャの戦い
エジプトとシリヤの戦い
終末における出来事
神は、ご自身が歴史の主権者であることを後の世の人々に知らせるために、この黙示をダニエルにお与えになった。彼が、そのすべてを理解したわけではないが(12・8)・・・。
![]()
ホセアは、北イスラエルの十三人目の王ヤロブアム二世の治世に預言者として召された。そして、紀元前721年に首都サマリヤが陥落する頃まで、約四十年の間、北王国で活動した。ホセアと同時代の預言者にアモスがいる。
おなじ時期、南王国のユダには、イザヤ、ミカなどの預言者がいた。ヤロブアム二世の時代、北イスラエルは隆盛をきわめ、国内も平和であり、領土も、ダビデ、ソロモンの時代に匹敵するほどになっていた。しかし、経済的、物質的繁栄は逆に、イスラエルに宗教的、道徳的、社会的腐敗をもたらした。
ヤロブアム二世の死後、北イスラエルの王位に着いた六人の王のうち、四人が暗殺され、暗殺者が王になるということがくりかえされている。そして、最後の王ホセア(預言者ホセアと名前は同じであるが別人)の時代に、北王国はアッシリヤに捕囚となった。これは主なる神の審判の結果であり、その原因は国全体の偶像礼拝にほかならなかった。(Ⅱ列王14・23〜17・23)
イスラエルの各々の王について、何度も出てくることばに注目したい。
「彼は主の前に悪を行ない、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。」(Ⅱ列王14・24、15・9、18、24、28)
ネバテの子ヤロブアムは、分裂した北王国の初代の王である。彼は、金の子牛を二つ造り、すでに行なわれていた異邦人の神々に対する偶像礼拝に加えて、王国内に子牛礼拝を導入したのであった。(Ⅰ列王12・28〜33)
ホセア書は、偶像礼拝を霊的姦淫の罪として要約している。これは、イスラエルをエジプトの奴隷の状態から救い出し、ご自身の所有の民として契約を結ばれた主なる神に対する、忌まわしい不貞にほかならない。この姦淫の民に対し、裏切られた夫である主の切々としたメッセージを伝えるために選ばれた預言者がホセアであった。
実は、彼の家庭生活そのものが、生々しい神のメッセージとなっている。ホセアは、淫行の妻をめとるように主から命じられた。
「行って、姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、はなはだしい淫行にふけっているからだ。」(1・2)
ホセアは、姦淫の妻を受け入れた。そして、彼自身のつらい経験を通して、神の愛をイスラエルの民に伝えようとしたのである。
マイヤー・パールマンは、本書の主題を次のようにまとめている。
「不忠実な妻イスラエルは、彼女の夫を捨て、あわれみ深い夫である主は、彼女をふたたび受け入れる。」
本書に示されている大切な真理は、
1.神は、ご自身の民が不忠実であるときに、苦しみを味わわれる。
2.神は、罪を大目に見ることはおできにならない。
3.神は、ご自身の民に対する愛の心を変えることを決してなさらない。だから、神を見捨てた人々が、ご自身のもとに立ち返ることを切に願っておられる。
ホセア書を、以下のように分解する。なお、本書においては、イスラエル、エフライム、サマリヤは同じ意味に使われている。本来、エフライムは北イスラエルを代表する部族名、サマリヤは北王国の首都であった。
1.分離─主の不忠実な妻、イスラエル(1〜3章)
ホセアの家庭生活を通してのメッセージ。
その内容は、彼の子どもたちの名前に表わされている。
第一子(男子)、イズレエル、「神は散らされる」の意。神の刑罰の意味が込められている。
第二子(女子)、ロ・ルハマ、「愛されない者」の意
第三子(男子)、ロ・アミ、 「わたしの民でない者」の意
2.断罪─罪深い民、イスラエル(4〜13章)
イスラエルの罪とさばき(滅亡)の宣告。
悔い改めて神に立ち返るように との訴え。
3.回復─回復された民、イスラエル(14章)
悔い改めの招き、回復と繁栄の約束。
「イスラエルよ。
あなたの神、主に立ち返れ。
あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。
わたしは彼らの背信をいやし、
喜んでこれを愛する。
わたしの怒りは彼らを離れ去ったからだ。
わたしはイスラエルには露のようになる。
彼はゆりのように花咲き、
ポプラのように根を張る。」(14・1、4〜5)
![]()
ヨエルが活動した時期については様々な説があるが、一般には南ユダ八人目の王ヨアシュの時代と考えられている。
ヨエルの預言のきっかけとなったのは、破壊的害虫─いなごの群れによる、烈しい侵害であった。いなごは、土地を荒し、収穫物を破壊し、広範囲のききんと極度の貧困をもたらした。その災害の恐ろしさについては、次のような描写がある。
「これらの食い荒す群れが通過した土地は、たちまち不毛と涸渇の様相を帯びる。ローマ人がこれらを『国土を焼く者』と呼ぶが、これは『いなご』の文字通りの意味である。
彼らが移動するときは、そこの土地がおおい尽くされ、全くかくされてしまうほどだ。非常に多くの数なので、その大軍が通り過ぎるには、しばしば、3日も4日もかかる・・・。遠方からこの進軍するいなごの群れをみると、ちりか砂の雪のように見え、幾億という害虫が前方へとぶ時、地面から数フィートの高さに達する・・・・・・・。
彼らは王もなく、指導者もないが、しかも、たじろぎもせず、間隙ない隊伍をなして、不可抗的な衝動によって同じ方向へと突進して行く。またいかなる障害があっても、右にも左にもまがらない。
彼らの進路に、壁や家があるとき、彼らはまっすぐに上へよじのぼり、屋根をこえて向う側へおり、開かれた戸口や窓から、めくらめっぽに突き進んで行く。水ぎわに来たときには、それが水溜りであろうと、河であろうと、湖であろうと、大海であろうと、決して廻り道をしようとはせず、おかまいなしにその中にとびこんでは溺れてしまうのである。そして水面に浮かぶ彼らの死体が、その仲間が通り過ぎるひとつの橋を形づくる・・・・・・。このようにして天罰は、しばしば終わりに至るのであるが、しかし何百万という昆虫の腐敗は、疫病と死の原因となる。」(バン・レナップ)
なんと、聖書の記述とよく似ていることだろうか。
預言者は、この災害を神の刑罰と見て、民に対して断食を呼びかけ、悔い改めて主なる神に立ち返るよう促している。そして、主は選民の真実の悔い改めを受け入れ、いなごの害を取り除かれるだけでなく、それが食い尽くしたものを償うことをも約束しておられる。
いなごによる侵害は歴史的な事実であった。しかし、ヨエルは、それを人間の軍隊による侵略の先触れと見ていたようだ。ユダ王国に対するアッシリヤの侵攻、バビロンによる破壊は、後に現実となった。さらに進んで、預言者は終末の時代、『主の日』の審判について語っているように思われる。
ヨエル書には三つの特徴がある。
1.いなごの被害に関する雄大な記述
2.すべての人に神の霊が注がれるという最初の約束
3.預言の範囲が非常に広く、ヨエルの時代から世の終わりにまで及んでいること
本書を、以下のように分解しておく。
1.いなごの災害(1・1〜12)
いなごの侵害が外国軍の攻撃にたとえられ、様々ないなごが襲来して、国土を荒廃させてしまった。
2.警告と悔い改めの呼びかけ(1・13〜2・17)
預言者は、この災害を神の刑罰と考え、さらに隣接の異邦人による侵略のひな型と見て、同胞に警告を与え、断食して悔い改 め、神に立ち返るよう呼びかける。
3.神の約束(2・18〜29)
主は、ご自分の地をねたむほど愛し、ご自分の民を深くあわれまれる。
民が真心から悔い改めるなら、主はその国から災害を取り除き、地に豊かな産物を実らせ、そればかりか、過去にいなごが食い尽くした年々を償ってくださると言う。
それは、すべての人に神の霊─聖霊─が注がれることによって実現する。聖霊が注がれるとの約束は、直接にはイスラエルの霊的回復をさしていよう。そして、ペンテコステの日に、その一部が成就した。(使徒2・16)
4.、来たるべき主の日における、神の究極の審きと支配(2・30〜3・21)
本書の鍵の句は『主の日』であり、全体で五回語られていて、それは審判を示している。
イスラエルが回復され、神に逆らいイスラエルを苦しめた地上の諸国民がさばかれた後、永遠の王国が打ち立てられる。
聖地パレスチナは、再び力の中心となり、帰還されたキリストが真の主権者として、全世界を支配されることになろう。
「主はシオン(エルサレム)に住む。」(3・21)
![]()
アモスが預言活動をしたのは、ウジヤが南ユダの王、ヤロブアム二世が北イスラエルの王だった時代である。アモスは羊飼いであったが、神は、日常の仕事の場から彼を召された。
自ら語っている。
「私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、いちじく桑の木を栽培していた。ところが、主が群れを追っていた私をとり、主は私に仰せられた。『行って、わたしの民イスラエルに預言せよ。』と。」(7・14、15)
アモスとホセアは同時代にイスラエル(北王国)へ遣わされ、イザヤとミカはユダ(南王国)に遣わされた。王国は、この頃、繁栄の絶頂に達していた。しかし、経済的、政治的、物質的繁栄は逆に、王国内に宗教的、道徳的、社会的腐敗をもたらしたのである。
ホセアは、神の愛に対するイスラエルの不誠実という面から、その罪を責めた。アモスは、神の義に対する違反という面から、イスラエルを厳しく非難している。
その理由は、
神のことばの無視、
社会的不正、
快楽の追求、
自己満足、
はなはだしい偶像礼拝・・・・。
近隣諸国の罪も同じように深かったが、イスラエルの責任は、より大きいものとみなされた。なぜなら、イスラエルは、地上のすべての民族の祝福となるために、神によって特別に選ばれた民であり、そのために偉大な特権を与えられていたからである。
マイヤー・パールマンによる本書の主題は・・・・・、
「特権を与えられた民たちの罪。この特権は、彼らに大きな責任をもたらした。そして、この責任を果たさなかったことは、彼らに、その受けた光にしたがって、審判をもたらした。」
本書を三つに分解する。
1.諸国民に対する審判(1〜2章)
ユダもイスラエルも、この叱責のメッセージに含まれている。キャンベル・モルガン博士は、すべての国民の罪を、次のように要約している。
①シリヤ(ダマスコ)の罪─残酷
②ペリシテ(ガザ)の罪─奴隷売買
③フェニキヤ(ツロ)の罪─契約に反して、奴隷売買仲介をしたこと
④エドムの罪─決定的、報復的な赦さざる心
⑤アンモンの罪─慾心に根ざした残酷
⑥モアブの罪─残虐な報復的憎悪
⑦ユダの罪─主の律法の侮蔑
⑧イスラエルの罪─堕落と虐待
2.イスラエルに対する審判(3・1〜9・10)
三つの説教(3・1〜6・14)
それぞれが、「このことばを聞け」で始まっている。
「わたしは、地上のすべての部族の中から、あなただけを選び出した。それゆえ、わたしはあなたがたのすべての咎をあなたがたに報いる。」(3・2)
「それでも、あなたがたは、わたしのもとに帰って来なかった。」(4・6、8、9、10、11)
「イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。」(4・12)
「わたしを求めて生きよ。」(5・4、6、14)
「公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように、流れさせよ。」(5・24)
五つの幻(7・1〜9・10)
①食い尽くすいなご
②焼き尽くす火
③重りなわ
④一かごの夏のくだもの
⑤祭壇のかたわらに立っておられる主
これらは、いずれも北イスラエルの滅亡を象徴しており、神は、イスラエルに対するさばきが刻々と近づいていることを示された。アモスは、これらのメッセージを率直に語ったため、イスラエルの祭司から迫害を受けている。(7・10〜17)
「見よ。その日が来る。
その日、わたしは、この地にききんを送る。
パンのききんではない。水に渇くのでもない。実に、主のことばを聞くことのききんである。」(8・11)
イスラエルは、神のことばをないがしろにした。だから神は、その同じことばのききんをもたらすと言われる。これこそ最大のさばきではなかろうか。
3.イスラエルの回復(9・11〜15)
しかし、神はご自身の民を見捨ててはおられない。審判は、民を悔い改めに導くためのものであった。
「わたしは、わたしの民イスラエルの捕われ人を帰らせる。わたしは彼らを彼らの地に植える。彼らは、わたしが彼らに与えたその土地から、もう、引き抜かれることはない。」(9・14〜15)
いつの日か、神の選民は豊かな繁栄を与えられ、こうしてイスラエルの栄光は回復されるのである。
![]()
本書はオバデヤに啓示されたので、このように呼ばれているが、著者については、何も知られていない。その名には『主のしもべ』、あるいは『主を礼拝する者』という意味がある。
書かれた時代を定めることは困難であるが、内容から推してエルサレム滅亡後とするのが最も妥当のようだ。
この書は、旧約聖書の中で最も短い書巻であるが、非常にユニークな主題を含む。それは、イスラエルの絶え間ない敵であったエドムの罪、刑罰、国家の消滅である。
エドムとイスラエルの間には深い因縁があった。エドムはエサウの子孫、イスラエルはヤコブの子孫、エサウとヤコブは双子の兄と弟である。彼らはアブラハムの子イサクの息子たちであるが、両者の対立は母リベカの胎内で既に始まっていた。そして、主は母親のリベカにこう仰せられた。
「二つの国があなたの胎内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。
一つの国民は他の国民より強く、
兄が弟に仕える。」(創世記25・22〜23)
出産のときに最初に出て来た子がエサウ、そのあとで弟が出て来たが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それで、その子はヤコブと名づけられた。『かかとをつかむ者』、『押しのける者』という意味である。
その名の如く、ヤコブは兄のエサウから長子の権利をだまし取り、父親からの祝福を奪ってしまった。(創世記27・36)
神は、かつてアブラハムに仰せになった。
「あなたは、
あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、
わたしが示す地へ行きなさい。
そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、
あなたを祝福し、
あなたの名を大いなるものとしよう。
あなたの名は祝福となる。
あなたを祝福する者をわたしは祝福し、
あなたをのろう者をわたしはのろう。
地上のすべての民族は、
あなたによって祝福される。」(創世記12・1〜3)
アブラハムへの祝福はイサクに受け継がれた。
「地のすべての国々は、あなたの子孫によって祝福される。」(創世記26・4)
そして、イサクへの祝福を受け継いだのはヤコブであった。神が、双子の兄のエサウではなく、弟のヤコブをお選びになったのは、彼らがまだ母親の胎内にいたときである。それは、性格や行ないによるのではなく、神の一方的な主権によるものであった。
アブラハムの神、イサクの神、主は、ヤコブにも仰せられた。
「あなたの子孫は地のちりのように多くなり、あなたは、西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。」(創世記28・14)
本書に記されているエドムの大罪とは、祝福の民イスラエルに対するものである。
かつて神は、イスラエルに対しては、エドムを好意的に扱うよう命じられたことがあった。(申命記2・5、23・7)
けれども、エサウの子孫であるエドム人は高慢で狂暴な民となり、たえずヤコブの子孫に敵対する姿勢を変えようとはしなかった。(民数記20・14〜21)
バビロンの王ネブカデネザルが、エルサレムを占領した時にも、エドムはイスラエルの没落を喜び、残酷にもその略奪と殺人とに加わっている。(詩篇137・7)
このようにして、エドムの凶暴な行為が極まり、神による刑罰と破滅がここに宣言さているわけである。
ユダヤ人─イスラエル─の回復後、ペルシャの王クロスがエドムを征服し、何千という人々を虐殺した。また、彼らはマカベヤの指揮したユダヤ人によって、徹底的な攻撃を受けた。
新約聖書の時代になって、エドム人とユダヤ人の対立は、イエス・キリストの時に頂点に達した。(マタイ2・16、14・6〜9、ルカ13・31〜32、23・9)
イエスはユダヤ人─ヤコブの子孫─として生まれ、ヘロデはエドム人で、エサウの子孫であった。
紀元70年、ローマの軍隊によるエルサレム包囲以後、エドム人は世界の歴史から姿を消し、国家として完全に消滅した。死海の南に位置した領土、セール山は、現在廃虚となっており、本書の預言が成就したことへの無言の証しとなっている。
本書は、三つの部分に分けられる。
1.エドムの運命についての宣告(1〜9)
2.エドムの最大の罪、ユダ─ヤコブの子孫─に対する凶暴な態度(10〜14)
3.エドムに対する刑罰─国家の滅亡(15〜21)
主の日、イスラエルは回復し、王権は主のものとなる。
![]()
ヨナは、ガリラヤのナザレに近い町ガテ・ヘフェルの出身で、ヤロブアム二世の時代に北イスラエルで活動した預言者だったと考えられている。(Ⅱ列王記14・25)
彼はヤロブアム王の治世下、北のイスラエル王国の黄金時代に、その繁栄を助けたのであろう。エリシャの活動が終った時、ヨナの働きが始まった。同時代の預言者に、ホセアやアモスがいる。
本書は、預言書の中でも特異な位置を占めている。それは、神の選民イスラエルに対して直接語られたものではなく、アッシリヤ帝国の首都ニネベに対するメッセージとなっているからだ。アッシリヤはイスラエルの強敵で、後に北王国を滅亡させた異邦の大国であった。
しかし、ヨナ書には、ユダヤ民族に対しても、ひとつの大きな教訓が含まれている。すなわち、神はユダヤ人だけの神ではなく、異邦人にとっても同じ神である。だから、神の啓示の光を異邦の人々にもたらすことは、神の選民の偉大な義務なのだ。
本書は、異邦人に対する預言者の説教が記録されているために、旧約聖書の宣教の書と呼ばれてきた。
マイヤー・パールマンによれば、ヨナ書の主題は次のように要約されている。
「悔い改めに導くために預言者をつかわされたことに見られる、異邦人に対する神の愛」。
また、ヨナ書は、超自然的な記述に満ちている。
主なる神は、大風を海に吹きつけられた。(1・4)
大きな魚を備えられた。(1・17)
ニネベ全市を悔い改めさせられた。(3・8)
一本のとうごまを備えられた。(4・6)
一匹の虫を備えられた。(4・7)
焼けつくような東風を備えられ た。(4・8)
人知では理解できないこれらの箇所を、削除したり、合理的に説明しようとしても、何の解決にもならない。神の奇蹟は私たちに、説明ではなく信仰を求める。大魚がヨナを飲み込んだこと、そして、ニネベのような異教の大都市が、一人の無名の宣教師によって数日のうちに悔い改めたことは、特に重要な記事であるが、この二つの史実性は主イエスご自身によって証明されているのである。(マタイ12・38〜41)
本書を各章ごとに分解しておく。
1.ヨナの不従順とその結果(1・1〜17)
ヨナは、神からニネベへの宣教命令を受けたが、主の御顔を避けて、船で別の方向へ行こうとする。彼が神に、「いや!」と言ったのは、間違った愛国心からだったらしい。(4・2)
アッシリヤはイスラエルの大敵であった。アッシリヤが、その悪のゆえに神の裁きを受けるなら、それはイスラエルにとって喜ばしいことに違いない。ヨナは、アッシリヤの滅亡を願った。
もし、彼がニネベに行って説教した結果、この異邦の人々が悔い改めたとしたら、神は彼らをお赦しになるであろう。それでは、自国イスラエルのためにならない・・・・・。
ところが、神のみこころは異なっていた。主は、ヨナの不従順を戒めるために暴風を送り、彼は同船の人たちの手によって海に投げ込まれてしまう。けれども、次いで主は大きな魚を備えて、ヨナをのみこませなさった。こうしてヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。
2.ヨナの悔い改めと救助(2・1〜10)
ヨナは魚の腹の中から、彼の神、主に祈る。それは、悔い改めと、神の救いに対する感謝の叫びであった。主は、魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させられた。
3.ニネベへの宣教と史上最大のリバイバル(3・1〜10)
再びニネベへの宣教命令を受けたヨナは、今度は従順にそれに従った。
ヨナの説教によって、ニネベ全市が悔い改め、神は彼らに下すと言っておられたわざわいを思い直し、そうされなかった。
4.神の大いなる憐れみ(4・1〜11)
ヨナは、神がニネベを憐れまれたことに対して腹を立てている。
神は一本のとうごまを通して、ご自身の慈しみの深さを彼に教えられた。
なお、主イエスご自身の説明によれば、ヨナが三日三晩魚の腹の中にいて、そこから生還したことは、キリストの死と葬りと復活の型であり、ヨナの説教に対するニネベの人々の応答は、真の悔い改めの模範とされている。
![]()
ミカは南王国の出身、ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に預言者として活動した。
彼は、イザヤと同時代の人であり、二人の預言には、非常によく似た個所があるので、お互いに接触があったのかも知れない。(イザヤ2・2〜4、ミカ4・1〜3参照)
ミカのメッセージは北イスラエルと南ユダの両国に向けられているが、主としてそれぞれの首都であるサマリヤとエルサレムに対して語られた。その中には、三つの主な思想が含まれている。すなわち、神の選民の罪、滅亡、および回復。
本書も、イザヤ書と同様に、大きく二つ─警告的部分と慰安的部分─に区分することができよう。
ただし、罪・滅亡・回復のメッセージが繰り返されているので、全体を順序よく分けることは困難である。
マイヤー・パールマンは、ミカ書の主題について以下のように説明している。
「第一区分において、預言者は、捕囚に運命づけられた罪深い国民を描写し、
第二区分において、千年期の祝福を楽しんでいる贖われた人々を描写している。
第一区分において、彼は、偽りの指導者によって迷わされ、破滅に導かれたイスラエルを示し、
第二区分においては、真の指導者メシヤによって回復された人々を示している。
その主題は、次のように要約することができる。すなわち、偽りの指導者によって滅ぼされ、メシヤなる真の指導者によって救われたイスラエル。」
ミカ書は、三回、重要な機会に引用されている。
1.ユダの王エホヤキムの治世、その地の長老たちは、ミカのことばを引用することによって、預言者エレミヤの命を助けた。(エレミヤ26・18、ミカ3・12)
2.主イエス誕生の頃、祭司長、学者たちによって。(マタイ2・5、6、ミカ5・2)
3.十二弟子を遣わされるとき、主イエスによって。(マタイ10・35、36、ミカ7・6)
本書の分解。
1.サマリヤとエルサレムの告訴(1・1〜16)
北イスラエルの偶像礼拝の罪は、 もはや癒しがたく、その影響は南ユダにも深く及んでいた。
「わたしはサマリヤを野原の廃 虚とし、・・・」(1・6)
この預言は、ミカの生きている間に成就した。北王国はアッシリヤによって滅ぼされ、捕囚とされたからである。
2.指導者たちによる圧政の罪(2・1〜3・12)
指導者たち─政治的支配者、預言者、祭司─に対する非難、民の罪と苦しみ。
エルサレム滅亡の予告。
未来の回復の預言も挿入されている。(2・12〜13)
3.神による回復(4・1〜5・15)
エルサレムの未来の栄光について描写されている。
5章2節は、メシヤ誕生の場所を示す唯一の預言。
「ベツレヘム・エフラテよ。
あなたはユダの氏族の中で最も 小さいものだが、あなたのうちから、わたしのために、イスラエルの支配者になる者が出る。
その出ることは、昔から、
永遠の昔からの定めである。」
4.神の裁きと慈しみ(6・1〜7・20)
ここには、真の宗教の本質的要素が記されている。
「主はあなたに告げられた。
主は何をあなたに求めておられるのか。
それは、ただ公義を行ない、誠実を愛し、
へりくだって、あなたの神とともに歩むことではないか。」(6・8)
「もしわれわれの宗教が、一つの大きな信条、大会堂、念の入った儀式にすぎないとしたら、われわれは何も持っていないのである。」(ヘンリエッタ・ミアーズ)
主はうわべではなく、私たちの心を見られるのだ。
「神へのいけにえは、砕かれたたましい。
砕かれた、悔いた心。
神よ。あなたは、それをさげす まれません。」(詩篇51・17)
そのことを悟らせるために、神はご自身の民を裁かれる。
本書の最高の美しさは、7章18〜19節に見られると、或る説教者は言っている。
「あなたのような神が、ほかにあるでしょうか。
あなたは、咎を赦し、ご自分のものである残りの者のために、
そむきの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、いつくしみを喜ばれるからです。
もう一度、私たちをあわれみ、
私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。」
![]()
本書はアッシリヤの首都ニネベの、目前に迫った滅亡を宣告している。ニネベは紀元前612年に、バビロンとその同盟軍の侵略によって陥落した。
ナホムはまた、エジプトの町ノ・アモン(テーベ)の略奪を既成事実として語っているようだ(3・8)。
これはアッシリヤの王アッシュルバニパルによって、紀元前666年頃になされた。だから、本書の預言は年代的にはこの間に語られたものであろう。だとすればナホムは、エレミヤ、ハバクク、ゼパニヤと同時代の預言者ということになる。
ナホム書はヨナ書の後編とも言える預言書である。この二人は、ニネベに関係のある預言者として召されていた。ナホムはヨナよりも約百五十年ほど後の人。ヨナ書は憐れみのメッセージ、ナホム書は滅亡のメッセージ。
ヨナの預言によって、ニネベの人々は悔い改めに導かれ、差し迫っていた運命(滅亡)から救われた。しかし、彼らはその悔い改めを後悔し、偶像礼拝と残虐、圧制にふけるようになっていた。そこでナホムが、ニネベに対する神の審判を宣言したのである。
このようなわけで、本書の主題は、かつてヨナが警告を与えた町ニネベの破滅であるが、メッセージの内容は、神の選民ユダに対する慰めを含んでいる。同胞の北イスラエルは、すでにアッシリヤに捕囚とされていて、その脅威は南ユダにも及んでいた。したがって、この圧制者の没落は、しいたげられたユダの解放につながるものだったからである。因みにナホムの名は『慰め』を意味しているから、彼のメッセージは、その名にふさわしかった。
本書の分解。
1.神の性格─全世界の『審判者』(1章)
ここには、審判者としての神の二重の性格が啓示されている。
(1) 怒りの神
ねたむ
(2) 愛の神
神は、アッシリヤに対して怒りを遅くされた。ヨナは神の属性の一面である『愛』について語った。 しかし、神はまた、不義に対する怒りを保ち、罰せずにおくことはしない方である。ナホムは神の性格の別の面、『怒り』について語っている。
「神の怒りについて、ある人は次のように言っている。
『ナホム書の永久的な価値は、旧約聖書の他のどの書も描かない、神の怒りの絵を人々の前に示していることである』・・・・・。神の怒りを、人間が怒った時のように、烈しく激情的、盲目的、愚かで馬鹿げたもののように考えてはならない。・・・・・・。人間においては、怒りが彼の主人となり、彼は怒りにふりまわされるが、神は常にその怒りを統禦し、それを用いられるのである。」(マイヤー・パールマン著『聖書概論』)
2.神の審判(2、3章)
「散らす者が、あなたを攻めに上って来る。
町々の門は開かれ、宮殿は消え去る。
ニネベは水の流れ出る池のようだ。みな逃げ出して、
『止まれ、立ち止まれ。』と言っても、だれも振り返りもしない。
銀を奪え。金も奪え。
その財宝は限りない。
破壊、滅亡、荒廃。
心はしなえ、ひざは震え、
すべての腰はわななき、
だれの顔も青ざめる。」(2・1〜10、抄録)
「メディヤ人とバビロニヤ人は、紀元前607年にニネベを完全に破壊した。それはニネベの力の絶頂の時のことだった。ナホムの預言の通りに、ティグリス川は急激に増水し、城壁の大部分を流し去り、メディヤ人とバビロニヤ人の攻撃の助けとなり、ニネベは陥落したのである。」(ヘンリエッタ・ミアーズ著『旧約聖書の概説』)
そこは、今も廃虚となっている。
「ああ。流血の町。
虚偽に満ち、略奪を事とし、
強奪をやめない。」(3・1)
ニネベの繁栄は、不義によってもたらされた。蒔いた種は刈り取らなければならない。確かに神は、イスラエルの背教を懲らしめるために、怒りの杖としてアッシリヤを用いてこられた。けれども、この異教の王は自分が全世界の主権者である神の道具にすぎないことを悟らず、みずから高ぶり略奪を欲しいままにした。(イザヤ10・5〜16、36〜37章)
それゆえに、神はニネベに対して正しいさばきを下されたのである。
![]()
ハバククは、エルサレムが滅亡する直前の、ユダの最後の時代に活躍している。
それまで世界を支配した大帝国アッシリヤは、ナホムの預言のとおりに滅亡、新興のバビロンがネブカデネザル王の下に世界帝国として勢いを増していた。
同時代の預言者としてユダにエレミヤ、バビロンにはダニエルがいた。
ハバククは預言者として神に召されていたが、またレビ人によって構成される神殿礼拝の聖歌隊にも加わっていたらしい。(3・19)
当時、王国内には罪がはびこり、神はそれを黙認しておられるかのように思えた。そこで預言者は、神に向かって疑問をぶつけている。
「主よ。私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで、聞いてくださらないのですか。私が『暴虐。』とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。」(1・2)
神はハバククに対して語られた。
「見よ。わたしはカルデヤ人を起す。強暴で激しい国民だ。これは、自分のものでない住まいを占領しようと、地を広く行き巡る。」(1・6)
神は異邦の民カルデヤ人(バビロン人)によって、ユダの不義を罰すると言われる。このことは、更にハバククを当惑させた。
「悪者が自分より正しい者をのみこむとき、なぜ黙っておられるのですか。」(1・13)
なぜ、神はユダを矯正するために、より邪悪なカルデヤ人を使おうとされるのか。なぜ、ご自身の民であるユダを異教の敵の手に渡されるのか。また、なぜユダをその罪のために罰しながら、バビロンのような罪深い国の存在を許されるのか。彼らこそ、さらに大きな刑罰に値するのではないか。
しかし、幸いにもハバククは、自分の疑問の答えを神に求めた。
「彼は、自分の時代の問題を解決するのに、委員会を招集したり、協会を作ったりはしなかった。彼はまっすぐに主のもとに行き、自分の問題を述べた。」(ヘンリエッタ・ミアーズ著『旧約聖書の概説』)
ハバククは、神が彼に何と答えられるかを待った。
「私は、見張り所に立ち、
とりでにしかと立って見張り、
主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。」(2・1)
主は幻によってハバククにお語りになった。それは、本書の中心である次のことばに要約される。
「正しい人(義人)はその信仰によって生きる。」(2・4)
邪悪なバビロンは、やがて神の裁きのもとに滅ぼされよう。現実に悪が栄え、正しい人が苦しんでいるとしても、義人は目に見える状況にではなく、神のことばに信頼を置かなければならない。神の約束は必ず成就するからである。
「もしおそくなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。」(2・3)
こうして、ナホムがアッシリヤ帝国の滅亡を預言し、オバデヤがエドムの滅亡を預言したように、ハバククはカルデヤ帝国(バビロン)の滅亡を、その最盛期に預言した。これらは、いずれも後の歴史において成就している。
ハバククは主のことばに信頼することを学んだ。本書は疑惑と非難で始まっているが、確信と信頼で終わっている。
マイヤー・パールマンはハバクク書の主題を次のように要約している。「信仰の戦いと最後的勝利」
本書の分解。
1.信仰の戦い(1、2章)
ハバククの最初の葛藤
神の第一の解答
預言者の第二の葛藤
神の第二の解答
「義人はその信仰によって生きる。」(2・4)
このことばは、新約聖書に三回引用されている。(ローマ1・17、ガラテヤ3・11、ヘブル10・38)
信仰によって義とされるという教理をパウロはハバククより学び、宗教革命の父マルチン・ルターは、それをパウロから学んだ。
2.信仰の勝利(3章)
私たちは、その時々に、神のご計画のほんの小さな一部分しか知ることができない。
神の道は、私たちの道よりも高く、神の御思いは、私たちの思いよりも高い。(イザヤ55・9)
神の方法は常に最善である。
神は私たちに、どのようなときにもご自身に絶対的に信頼することを求めておられる。
ハバククは、暗黒の中で、神に向かって喜びの叫びをあげている。
「しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は、私の力。
私の足を雌鹿のようにし、
私に高い所を歩ませる。」(3・18〜19)
![]()
ゼパニヤは、ユダの十六代目の王ヨシヤの時代に預言活動をした。彼は十三代目の王ヒゼキヤの曽孫の子にあたり、王族の出身で、ヨシヤ王とも血のつながりがあった。ヨシヤは、ヒゼキヤの子マナセの悪政の後を受けて王位に着き、大改革を行なった。(Ⅱ歴代34、35章)
この改革に、ゼパニヤは重要な役割を果たしたに違いない。ユダが紀元前586年に滅ぼされる前の数十年間の時期であった。
同時代の預言者に、エレミヤがいる。
本書には『主の日』ということばが度々出てくる。それは『怒りの日』であり、ゼパニヤが審判のメッセージを語っていることは明らかだ。
ヨシヤは確かに善い王には違いなかったが、彼の宗教的・政治的改革は部分的なもので終わってしまった。ユダの民の背教は修復不可能な状態になっていたのである。やがて神の都エルサレムはバビロン軍の侵入を受け、ユダの民は捕囚となって行く。だから、『主の日』とは第一にはそのことを指していると見てよかろう。
そして、それはまた、終末の時代に起こる大変動を象徴的に描写しているのかも知れない。
ゼパニヤは、ユダに悔い改めを呼び掛けた。
「主を尋ね求めよ。
義を尋ね求めよ。柔和を求めよ。
そうすれば、
主の怒りの日にかくまわれるかもしれない。」(2・3)
そして、神の刑罰による荒廃はユダの周辺諸国にまで及ぶことを預言者は宣言している。主は全世界の主権者であられ、すべての国の罪を公正に裁かれるからである。ここに記されている国々は、ペリシテ、モアブ、アンモン、クシュ(エチオピア)、アッシリヤ。二十年を経ないうちに、これらの諸国はすべて、バビロンに制圧された。
バビロンは、ユダならびにこれらの異邦諸国に対する神の審判の道具であった。かつては、神はアッシリヤを、イスラエルに対する怒りの杖としてお用いになった。(イザヤ10・5)
しかし、これらの世界帝国も、自らの高ぶりと罪のゆえに、神の裁きを受けていく。バビロンは、後にメド・ペルシャによって滅ぼされた。
幸いなことにゼパニヤ書は審判で終わっていない。他の多くの預言書と同様に、本書にも回復のメッセージが含まれている。
「シオンの娘よ。喜び歌え。
イスラエルよ。喜び叫べ。
エルサレムの娘よ。心の底から、喜び勝ち誇れ。
主はあなたへの宣告を取り除き、
あなたの敵を追い払われた。
イスラエルの王、主は、
あなたのただ中におられる。
あなたはもう、わざわいを恐れない
その日、エルサレムはこう言われる。
シオンよ。恐れるな。気力を失うな。あなたの神、主は、あなたのただ中におられる。
救いの勇士だ。
主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、
その愛によって安らぎを与える。
主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。」(3・14〜17)
本書には、ユダに対する刑罰が宣告されているだけでなく、捕囚からの帰還も預言されている。(2・7、3・20)
これは、バビロンからの帰還はもちろん、終わりの時代におけるユダヤ人の祖国復帰、さらには霊的回復をも示しているのであろう。
マイヤー・パールマンによる本書の主題
「イスラエルと諸国民にくだされた審判の夜と、それにつづく、イスラエルの回復と諸国民の回心の朝。」
本書の分解。
1.神の審判の警告(1・1〜2・3)
罪に対する刑罰の警告と、悔い改めへの招き。
2.神の審判の範囲(2・4〜3・7)
審判はユダのみならず、その周辺諸国にまで及ぶ。
3.メシヤ王国のもとでの回復の約束(3・8〜20)
「そのとき、わたしは、
国々の民のくちびるを変えてきよくする。
彼らはみな主の御名によって祈り、一つになって主に仕える。」(3・9)
イスラエルの残りの者の救い、捕囚からの帰還、栄誉の回復。
「清きくちびる・・・・これはすなわち神に関する正しい思想の体系の事である。言葉は真理の表現であり、伝達機関なのだ。これは神の完全無欠の啓示が人類に与えられる事─明らかにキリストの福音を意味している─の恩恵に浴する来たるべき日の預言であり、この結果として、諸国の民の中の回心者は、あがないの歌を喜び歌いつつ主に来たり、全地は神の民の賛美をもってこだまするであろう。」(ヘンリー・ハーレイ)
![]()
ハガイ、ゼカリヤ、マラキは捕囚後に預言活動をした。ハガイとゼカリヤは同時代の人、マラキはそれより百年ほど後の預言者であろうと思われる。
本書の歴史的背景については、エズラ記1〜6章を参照のこと。
紀元前536年、ペルシャの王クロスの勅令により、バビロンに捕囚となっていたユダの民の第一陣が、ゼルバベルを指導者としてエルサレムに帰還した。
捕囚から帰ってきたユダヤ人にとって、神の民としての回復の第一歩は神殿の再建であった。そして総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアの指揮のもとに神の宮の再建工事が始まった。ところが、近隣の敵の妨害によって建設工事は中止させられてしまう。
工事の停止は十六年に及んだ。その間に人々は神の宮に対して無関心で利己的となり、神殿を建てる代りに、自分の家を美しくすることに専念するようになった。いわゆるマイ・ホーム主義である。ひでりと不作は、この怠慢の結果もたらされた神の刑罰だったと言える。
これらのわざわいの原因に関する人々の問いかけが、ハガイにメッセージの機会を与えた。このメッセージの中で彼は、神殿の必要に関して人々がまったく無頓着であるために、彼らに不幸がもたらされたのであると宣言した。
ハガイは民に、もういちど神殿の建設に立ち上がるよう呼びかけ、励ました。こうして、宮は四年間で再建されたのである。
マイヤー・パールマンは本書の主題を次のように要約している。
「神殿完成についての怠慢の結果─神の怒りと刑罰。神殿完成の結果─神の祝福と未来の栄光の約束。」
〔分解〕
本書はハガイの五つのメッセージにしたがって分解される。
1.第一の叱責のメッセージ(1・1〜11)
彼は、神を忘れて自分の家のために走り回っている民の怠慢を責めた。
「この宮が廃虚となっているのに、あなたがただけが板張りの家に住むべき時であろうか。」
そして、国家的災害は神に対する国民的な不従順に因ることを指摘、工事にとりかかるようにうながす。
「あなたがたの現状をよく考えよ。山に登り、木を運んで来て、宮を建てよ。そうすれば、わたしはそれを喜び、わたしの栄光を現そう。」
2.第一の励ましのメッセージ(1・12〜15)
ハガイの励ましと、工事の再開
3.第二の励ましのメッセージ(2・1〜9)
昔の神殿の荘厳さを知っている 老人たちの目には、新しい宮は貧弱に映った。そこで彼は、この宮をとおして神の栄光が現されるのだと民を激励する。
「わたしの霊があなたがたの間で働いている。恐れるな。すべての国々の宝物がもたらされ、わたしはこの宮を栄光で満たす。 この宮のこれから後の栄光は、先のものよりまさろう。」
4.第二の叱責のメッセージ(2・10〜19)
神の宮の工事がなおざりにされている間、民のささげものは無益であった。彼らの祈りが答えられず、収穫が乏しかったのは、 彼らが神殿の完成をあまりにも長いこと延ばしていたからにほかならない。服従(神殿建築)のない犠牲は神に受けいれられ ることはなかったのである。しかし、神の民が事を始めた今は、事情が異なってきた。
「きょうから後、わたしは祝福しよう。」
5.第三の励ましのメッセージ(2・20〜23)
その頃、ユダヤの国は他の国の支配のもとにあった。けれども、やがて主なる神は異邦の王国を滅ぼし、イスラエルの家の繁栄と安全を永遠に確証される。ダビデの家系の代表として、またメシヤの先祖として、ゼルバベルはその約束を受けた。未来において、世界の国々は震われ、ユダヤ民族はメシヤ─キリスト─によって確立されよう。ゼルバベルは、そのメシヤの型を表わしている。
本書の特徴は、すべて預言された日が明記されていること。
ペルシャのダリヨス王の治世
(1) 第2年6月 1日
(2) 第2年6月24日
(3) 第2年7月21日
(4) 第2年9月24日
(5) 第2年9月24日
ハガイの預言の期間は、 三ヵ月と二十四日であった。それに対して、ゼカリヤは約三年間預言活動をしている。
本書の中にくりかえし使われている語句は、
「主のことば」、5回
「主は言われる」、「主の御告げ」、19回
「万軍の主」、14回
「よく考えよ」、4回
疑問文(1・4、2・3、12、13)
![]()
ゼカリヤはハガイと同じ時代に預言者として活動した。
総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアの指導のもとに始められた神殿の再建工事は、ユダヤ人の敵の妨害にあって中断させられていた。ゼカリヤの使命は、苦悩のために意気沮喪し、神殿の再建をおくれさせている民に、現在の成功と未来の栄光を約束し、彼らを激励することにあった。
彼は、三年間の預言活動を通し、民の目を暗い現状から、輝かしい未来へ向けさせようとした。彼は回復と栄光を告げる預言者であって、メッセージの内容は神殿の再建に始まるが、千年王国にまで至っている。本書は、主として未来についての書であり、旧約聖書の黙示録とも呼ばれている。
マイヤー・パールマンは、本書の主題を次のように要約している。
「未来におけるメシヤ時代の栄光を望み見て、現在の悲嘆の中にも、神に忠実に奉仕するようにとの民に対する激励」。
〔内容〕
1.悔い改めと従順への招き(1・1〜6)
「わたしに帰れ。─万軍の主の御告げ。─そうすれば、わたしもあなたがたに帰る。」
イスラエルの先祖たちは、先の預言者たちの声に耳を傾けようとしなかった。現在の苦境はその結果にほかならなかい。神の 民は、主なる神に聞き従うべきである。そのとき、神の祝福は現実のものとなろう。
2.八つの幻と戴冠式(1・7〜6・15)
神は一連の幻と、大祭司ヨシュアの象徴的戴冠式を通して、残りの民に励ましのメッセージをお与えになった。
①ミルトスの木の中の騎士の幻(1・7〜17)
②四つの角と四人の職人の幻(1・18〜21)
③測り綱を持った人の幻(2章)
④大祭司ヨシュアの幻(3章)
⑤金の燭台とオリーブの木の幻(4章)
⑥飛んでいる巻物の幻(5・1〜4)
⑦エパ桝の幻(5・5〜11)
⑧四台の戦車の幻(6・1〜8)
大祭司ヨシュアの象徴的戴冠式(6・9〜15)
イエス・キリストは、ご自分の千年王国を立てるため地上に帰られる時、祭司として、王として栄光の座にお着きになる。 ヨシュアはそのキリストのひな型である。神はイスラエルに対して、長期的な計画を持っておられ、これらは神殿再建工事に携わる人々を励ますための象徴的メッセージであった。
神の事業は人間の知恵や力によるのではなく、神の御霊の働きによって成し遂げられるものである。
4章6節は、よく引用される 重要なことば。「権力によらず、能力によらず、わたしの霊によって。」
3.従順か、形式主義か(7〜8章)
ここには、断食についての実際的メッセージが語られている。断食のための断食は無益であり、従順こそが、神との正しい関係への鍵である。
4.イスラエルの終りの時代、キリストの来臨と支配に関する預言(9〜14章)
未来に係わる預言的メッセージである。
『王』が来られる(9・9)。
『王』が拒絶される。
価が払われ、(11・12、13)
牧者は殺され、(13・6、7)
民はちらされる。
『王』が再び来られる。─反キリストとの戦い─
『王』の勝利と即位(14章)。
『王』は救い主として、卑しい姿で来られ、ご自分の民によって拒否され、イスラエルは審きのために、諸国民の間に散らされる。
諸国民が戦いのためにエルサレムに集結するときに、イスラエルは再臨の『王』を自分たちが突き刺した者として認める(12・10)。『王』は全世界の主となられ、諸国の民は、万軍の主である『王』を礼拝するために、エルサレムに上ってくる。
ゼカリヤは、イザヤを別にすれば、他のどの預言者よりも、救い主について多くを語っている。(3・8、9・9、11・12、13、12・10、13・7、14・4)
聖書には、メシヤから放たれる二つの光─十字架の光と王冠の光─が輝いている。来るべき時代のメシヤがひとりの『お方』として、しかし、二つの姿で来られる。第一は謙卑と苦しみの姿で、そして第二は威厳と大いなる栄光の姿で・・・・。
ユダヤ人は、十字架のキリストを無視してきた。 キリスト者は、あまりにもしばしば、王なるキリストを無視してきたのではなかろうか。
![]()
マラキの年代は、紀元前5世紀の後半で、ハガイ、ゼカリヤより約百年後の人。彼らが総督ゼルバベルを助けたように、マラキは総督ネヘミヤを助けたことであろう。
ユダヤ人がバビロンより本国に帰還して既に百年あるいはそれ以上の年月が経過していた。捕囚によって神の民の偶像礼拝は矯正されていたが、神との関係はあるべき状態になかった。神に対する信仰は形式化し、道徳的にもたるんでいた。
具体的には、祭司の堕落、宮の犠牲の軽視、什一献金がなおざりにされていたこと、異教の民との雑婚、離婚、神の正しいさばきと真実に対する疑い等々・・・・。
本書には、これらの罪に対する叱責のメッセージとともに、メシヤの来臨の約束が記されている。
メシヤは、悪を行なう者をさばき、主を畏れる者に豊かな報いをお与えになるであろう。
マラキ書は、メシヤの先駆者としてのエリヤの到来の預言をもって終っている。
マイヤー・パールマンによれば、本書の主題は以下のように要約される。
「旧約聖書の最後の預言、反抗的で不誠実な人々についての黙示、忠実な残りの者、またその民をさばき、潔めるところの来たるべきメシヤについての啓示。」
本書の特徴は、神と民の対話という形式をとっていることで、これは主の非難に対する、民の反抗的態度をよく表わしている。
1.イスラエルに対する神の愛(1・1〜5)
ここでのイスラエルとは、捕囚後に帰還したイスラエルとユダの残りの者全部を意味している。人々は、彼らに対する主の愛を疑っていた。神は、イスラエルに対するご自身の愛の証拠として、彼らの先祖ヤコブを選び、その兄エサウと彼の子孫エドムを斥けたことを指摘される。
2.悔い改めへの招き(1・6〜3・18)
(1) 祭司たちの罪(1・6〜2・9)
彼らは、総督にさえ差し出さない傷のある、病気の犠牲動物を神にささげた。自分に何の犠牲も必要としない供え物は、神の前に価値がない。
また彼らは、神とともに歩むこと、人々を不義から立ち返らせる熱心、民を正しく教え導く能力など、祭司に必要な資格に欠けていた。
(2) 家族に対する罪(2・10〜16)
民のうちの或る者たちは、異教の女性をめとるために、イスラエル人の妻と離婚していた。(ネヘミヤ13・23〜28)
(3) 神のさばきの宣告(2・17〜3・5)
不義を行なう民に対して、さばきの宣告がなされる。しかし、このさばきには、民をきよめる意図も含まれていた。
(4) 神に立ち返る道(3・6〜12)
民は什一献金を怠ることによって、神のものを盗んでいた。
「十分の一をことごとく、宝物倉に携えて来て、わたしの家の食物とせよ。」(10)
「十分の一献金は、すべてが神のものであることの外に見える承認(神の所有権を認めること)のしるしである。われわれは、自分の全部、すなわち、肉体、魂、霊を神のもとに持参すべきである。その時、神は、われわれを受け入れ、天の窓を開いて、ご自身の祝福を注ぎ出してくださるであろう。」(ヘンリエッタ・ミアーズ)
(5) 主を畏れる者への約束(3・13〜18)
ある人々は、悪人が栄えるのを見て、神に仕えることはむなしいと考える。しかし、神は公正なさばきをなさるお方、「あなたがたは再び、正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる」と言われる。
3.来たるべき主の日とメシヤの 来臨(4・1〜6)
(1) 主の日のさばきと救い(4・1〜3)
『主の日』、それは悪を行なう者にとっては滅びの日であるが、主を畏れる神の民にとっては救いの日となろう。
究極的には、キリストの再臨の時を示しているのではないか。
(2) 旧約聖書の最後の奨励(4・4)
「モーセの律法を記憶せよ。」
マラキは旧約最後の預言者であり、以後メシヤ、すなわちイエス・キリストが来られるまでの四百年間、啓示は途絶えることになる。その間、律法がイスラエルの民の信仰生活の規範となるべきであった。預言者がいないとき、人々は容易に律法を忘れてしまう。だから律法を記憶することは、最も大切なことであった。
(3) 旧約聖書の最後の預言(4・5〜6)
神は、メシヤの来臨に備えて、先駆者エリヤを遣わされる。この預言は、バプテスマのヨハネにおいて成就された。また、なお将来のこととして、キリストの再臨においても、先駆者があるかもしれない。
![]()
旧約聖書と新約聖書の間には、約四百年の隔たりがあり、この期間は中間時代とも呼ばれている。
改めて、聖書のおおまかな内容を記しておく。
〔聖書の主題〕
イエス・キリストによる人類の贖(あがな)い
〔聖書の分類〕
A.旧約聖書─救いの準備
B.新約聖書
1.福音書─救いの顕現
マタイの福音書
マルコの福音書
ルカの福音書
ヨハネの福音書
2.歴史書─救いの伝達
使徒の働き
3.教理書─救いの説明
パウロ書簡
一般書簡
4.預言書─救いの完成
黙示録
なぜ、四つの福音書があるのか。その理由の一つは、使徒時代には四つの主な階級の人々がいたということである。
すなわち、
福音書の記者たちは、直接には、夫々のクラスの人たちを対象にして書いた。
けれども、また同時に、福音書のメッセージは人類全体にあてられているとも考えられるであろう。なぜなら、どの時代においても、人間性というものは変わりないからである。
四つの福音書が書かれたもうひとつの理由は、ひとつの福音書では、キリストのご人格の多面性を示すのに不十分であったからだ。
四人の記者たちは、イエス・キリストをそれぞれ異なった観点から描いている。
このようなわけで、四福音書には、矛盾したように見える個所が見られるのである。これらの部分を集めて、イエスの生涯を充分に説明しようとすることは、それほど重要だとは思えない。
もっとも大切なのは、四つの福音書をとおして、それが現わそうとしている『お方』を知ることだろう。四福音書はひとつの完全な伝記というよりは、むしろ、ひとりの『人格』を提示しているからである。ある理由によって、神は、人間が神の御子の完璧な伝記を書くことを望まれなかった。
イエスが公に神の国の務めを開始されるまでの事柄は、ほとんど記されていない。わずかに、ルカの福音書の数節で触れられているだけである。聖書に記されていないことを敢えて詮索しようとするのは賢明ではない。神の沈黙に対しては、それを尊重するのが最も賢明なことだと思われる。
しかし、四福音書は、ストーリーとしては不完全でも─それは神の意図されたことであるが─、啓示としては完全である。私たちは、イエスがなさったことのすべてを知ることはないかも知れない。が、イエスという『お方』を知ることはできる。四つの偉大な記述の中には─それぞれが、或る点について他の三つを補う関係にあって─『イエス・キリストご自身』が現わされているからである。
四福音書が共通して記している主要な点を挙げると、
(1) ひとりのユニークな人格
(2) バプテスマのヨハネの務め
(3) 5000人の給食
(4) ゼカリヤ書9章9節による、王としてのキリスト
(5) イスカリオテ・ユダの裏切り、ペテロの否認
(6) キリストの裁判と十字架刑
(7) キリストの復活
(8) キリストの復活後40日間の務めの間に起きた事柄
(9) キリストの再臨
四福音書のうち、最初の三つは共観福音書と呼ばれてきた。それらは、同一事件の共観(共通的観察)を示し、また、共通の計画を持っているからである。これに対して、ヨハネの福音書は、他の三つの書とは、まったく違った意図から書かれている。
マイヤー・パールマンによれば、その相違点は次のように要約される。
「共観福音書は、霊的でない人たちのための伝道メッセージを含み、ヨハネの福音書は、クリスチャンたちに対する霊的メッセージを含んでいる。三福音書においては、われわれは、イエスの真正で完全な人間性に印象づけられるが、第四福音書の中では、イエスの真実で畏敬すべき神性に印象づけられる。」
![]()
著者はマタイ、他の福音書ではレビという名でも呼ばれている。彼は、ローマ政府のために税金を集める役人─取税人─であった。当時の取税人は、支配者であるローマ帝国に協力する立場にあり、また不正な取り立てをして私腹を肥やす人たちが多かったので、ユダヤ人からは憎まれ、軽蔑されていた。
マタイは後に、イエスの十二弟子の一人として選ばれ、使徒としての働きをしている。
本書は、直接にはユダヤ人を対象として書かれた。そして、ナザレのイエスが旧約聖書において預言されていたメシヤであることを強調している。
冒頭の書き出しは、メシヤがアブラハムの子孫として、ダビデの家系から生まれるという神の約束を、ユダヤ人たちに示すためであったに違いない。
また本書には、他の福音書と比較して、旧約聖書からの引照が特に多い。およそ六十ある。(例 1・22、2・15、17、23、3・3、4・14、12・17、13・14、21・4、26・54、56、27・9)
ユダヤ人に対して教える場合には、旧約聖書から、その教理を証明することが必要であった。
本書において、キリスト─メシヤ─は王として描写されている。その系図はダビデ王の家系であることを示し(別資料《イエス・キリストの系図》参照)、生まれた場所がベツレヘムであることが強調されている。ここは、またダビデの故郷だ。そして七回、イエスは『ダビデの子』として記されている。(1・1、9・27、12・23、15・22、20・30、21・9、22・42)
さらに、『王』に関係のあるいくつかの表現に注目したい。
『栄光の座』(19・28、25・31)
『聖なる都』(4・5)
『偉大な王の都』(5・35)
この福音書は『天国』という言葉を非常に多く用いているので、『天国の福音』とも呼ばれている。神の支配する王国を意味する『バシレイア』ということばが使われている回数は五十を下らない。
また、他の福音書が『神の国』という書き方をしているのに対し、本書は『天の御国』という表現を三十回以上も用いている。
マタイは、また主イエスの説教を多く記録し、特に山上の垂訓、キリストの再臨と終末の教えは、すべて収録されている。
さらに、この福音書には、『教会』ということばが用いられており(16・18、18・17)、これも他の福音書に見られない特色であろう。
〔内容〕
1.王の紹介(1〜4章)
系図、誕生、公生涯の初期
2.王国の支配原理(5〜7章)
山上の説教
3.王の権威の顕現と拒絶(8〜12章)
4.王国の奥義(13章)
王の二度の来臨の間の期間
5.拒絶された王の務め(14〜23章)
6.王が再び来られることについての予告(24〜25章)
オリブ山でのイエスの説教
7.王の死と復活(26〜28章)
メシヤの系図の中に、特に四人の女性の名が記されていることは興味深い。すなわち、タマル、ラハブ、ルツ、ウリヤの妻(バテシェバ)。いずれも異邦人で、しかも身分の低い女性たちである。神の恵みの広さ、深さが示されているのではなかろうか。
また、死から復活されたイエスは、十一人の弟子たちに言われた。
「わたしは天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。」(28・18〜19)
この個所は、『天国の福音』がユダヤ人だけでなく、あらゆる国の人々に伝えられるべきことを述べ、イエスが全世界のメシヤ─救い主─であることを明示しているといえよう。
なお、マイヤー・パールマンは、本書の内容を心に明記するために、各章につき簡単な言葉による概略を挙げている。
1章 系図と誕生
2 逃避
3 洗礼
4 誘惑
5〜7 山上の垂訓
8〜9 奇跡
10 使徒の派遣
11〜12 説話
13 たとえ
14〜15 群衆の養い
16 ペテロの告白
17 変貌
18〜20 説教
21 勝利の入城
22 敵の陰謀
23 わざわい
24〜25 再臨
26 裏切り
27 十字架刑
28 復活
![]()
著者はマルコ。マルコはローマ名で、本名はヨハネだったようである。彼は、エルサレムの一婦人マリヤの息子であって、その家は初代クリスチャンたちに開放されていたらしい。(使徒12・12)
マルコの名は、福音書には見られないが、『使徒の働き』の中に出てくる。彼は、使徒パウロの第一次伝道旅行に、いとこのバルナバと共に随行した。ところが、彼は途中で一行から離れて、エルサレムへ帰って来てしまった。(使徒13・13)
その理由については、何も記されていない。おそらく、未知の地域への旅の厳しさに耐えられなかったのではなかろうか。
後にパウロが第二次伝道旅行をバルナバに提案したとき、バルナバはマルコもいっしょに連れて行くつもりであった。しかしパウロは、旅の途中で一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったような者はいっしょに連れて行かない方がよいと考えた。
こうして激しい反目となり、その結果、二人は互いに別行動をとることになる。パウロはシラスを選び、第二次旅行に出発、バルナバはマルコを連れて別の方面に向かうことになった。(使徒15・36〜41)
マルコは、のちになって、彼に対するバルナバの信頼に報いたようである。パウロの書いた手紙から、そのことがうかがえる。彼は、パウロとも行動を共にするようにもなっていた。(コロサイ4・10、ピレモン24)
そして、パウロは殉教直前に、こう書くほどにマルコについての考えを変えている。
マルコを伴って、いっしょに来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。(Ⅱテモテ4・11)
使徒ペテロは、マルコのことを、『私の子」と呼んだ。(Ⅰペテロ5・13)
初代教会の教父と呼ばれる人たちの証言によれば、マルコはペテロに同行して、彼の通訳者としてローマに行き、そして、この福音書をペテロの説教から編集したと言う。初期のころより、マルコの福音書は、ペテロのキリスト観を反映していると考えられてきた。失敗から立ち直ったという面からも、この二人には共通するものがあったと言えよう。
本書は、異邦人、特にローマ人を念頭において書かれたと思われる。マルコは、ローマ人のために福音書を書くのに特にふさわしい人物だったのかも知れない。マルコというローマ名は、彼がローマ人の中で育ったという事実を暗示している。
マルコの福音書は、最も簡潔で短い。
マタイ 28章
マルコ 16章
ルカ 24章
ヨハネ 21章
しかし、マルコの文体は、マタイ、ルカの並行記事と比較して、より活き活きとしており、また詳細にわたっている部分も少なくない。たとえば、「悪霊につかれたゲラサ人」の物語などがそうである。(5・1〜20)
マルコの福音書では、キリストは『しもべ』として描写されている。これは、何事につけても実際的なローマ人に対して、ふさわしい提示の仕方ではなかっただろうか。
また、『ことば』よりは『行ない』の書で、長い説教を含まず、たとえも少ない。
本書の主な特徴は、「直ちに」とか「すぐに」ということばが、くり返し出てくることで、約四十回に及ぶ。これは、しもべの継続されていく活動を示していると言えるだろう。
本書は以下の記事を省略している。
イエスの系図
処女降誕
イエスの幼・少年時代
山上の説教
旧約聖書からの引用(2章以降)
このことは、しもべとしてのイエスを描写するというマルコの中心的な目的とも調和していよう。
〔内容〕、
1.しもべが公の務めに導き入れられること(1・1〜13)
2.しもべによって為された働き(1・14〜13章)
3.しもべの、死に至るまでの従順(14〜15章)
4.勝利のしもべの復活と昇天(16章)
本書においては、奇蹟が主要な位置を占めている。そして、この『しもべ』は、継続する働きを弟子たちにゆだねて、天に帰って行かれた。
「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。・・・・・・。信じる人々には次のようなしるしが伴います。すなわち、わたしの名によって悪霊を追い出し、新しいことばを語り、・・・・また、病人に手を置けば病人はいやされます。」(16・15〜18)
![]()
ルカは、この第三福音書と『使徒の働き』を書いている。彼は、初代教会において、『愛する医者』として知られていた。(コロサイ4・14)
使徒パウロの随行者であり、同労者でもある。(Ⅱテモテ4・11、ピレモン24)
本書は、直接にはギリシャ人のために書かれたと考えられるが、その根拠として、ある学者は次のような点を挙げている。
1.著者において
ルカはギリシャ人であったようだ。彼は医者であり、また、その文体からみて、高い教育を受けた人物だったに違いない。
2.書き方において
ルカの福音書は、イエスの言葉とわざについて、最もよく順序だてて書かれた歴史であるとみなされている。注意して読むと、思慮深い人間によって、思索的、哲学的な人たちに対して書かれた聖句を見い出す。
3.文体において
ルカによる福音書は、その詩的雄弁な文体から特に魅力的である。第1章にある賛美に注意。
この福音書をとおして、イエスの説話をみるが、これは、教えよりもむしろ行ないを強調したマルコによる福音書とは、まったく対照的である。
4.その省略において
明らかにユダヤ的なものは省略されている。旧約聖書の預言については、ほとんど、あるいは全然、語られていない。
本書が強調するのは、キリストの完全な人性である。このお方は『人の子』、完全な人間性を備えた神聖な人格として描写されている。
ルカの福音書にみられる特徴を挙げてみよう。
本書だけが、キリストの少年時代について記す。また、主イエスの祈りの生活についての記述が、他の共観福音書よりもずっと多い。(3・21、5・16、6・12、9・18、29、11・1、22・32、44、23・34、46)
聖霊による奉仕についての言及。(4・1、14、18)
主は、そのみわざを、自動的に『神の子』としてではなく、『人の子』として、祈りを通し聖霊の力によって成し遂げられた。
そのたとえ話は、失われた人類に対するキリストの深い関心を示している。
或る奇蹟の記事には、医師ルカの深い観察が明らかに見られる。特に病人や苦しんでいる者、見捨てられた者に対する主イエスの憐れみに力点が置かれている。
婦人たちの、キリストに対する奉仕の記述。(8・2、3)
『人の子』としての描写に沿って、世界的な救いの展望の強調。
七十人の弟子たちの派遣。(10・1〜24)
失われた羊、失われた銀貨、失われた息子─放蕩息子─のたとえの記録。(15・3〜32)
取税人ザアカイの話。(19・1〜10)
〔内容〕
1.序文(1・1〜4)
2.キリストの誕生、バプテスマ、系図、荒野の誘惑(1・5〜4・13)
イエス・キリストの系図は、マタイの福音書とルカの福音書に記されている。マタイは、法律上の父方の系図、これに対して、ルカは母方の系図を記していると考えられる。そして、マタイとは逆に先祖へとたどって行く。ダビデから先は共通で、アブラハムを経て、全人類の祖先アダムに至る。マタイは、『王』としての系図、ルカは『人の子』としての系図を示していると言えよう。
3.人の子の公生涯、エルサレムへの勝利の入城まで(4・14〜19・27)
イエスの務めは、祈りを通し、聖霊の力によってなされた。これが奉仕の秘訣である。以下の表現に注目したい。
「聖霊に満ちたイエス」
「御霊に導かれて」
「聖霊の力を帯びて」
「わたしの上に主の御霊が」
「(聖霊の)油を注がれた」
同じ著者による『使徒の働き』には、このように要約されている。
神はこの方─ナザレのイエス ─に聖霊と力を注がれました。このイエスは、神がともにおられたので、巡り歩いて良いわざをなし、また悪魔に制せられているすべての者をいやされました。」(使徒10・38)
4.キリストの排斥と死(19・28〜23・56)
5.キリストの復活、弟子たちへの宣教命令、そして昇天(24・1〜53)
宣教命令には、約束が伴っていた。
「さあ、わたしは、、わたしの父の約束してくださったものをあなたがたに送ります。あなたがたは、いと高き所から力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。」(24・49)
この約束は、私たちのものでもある。
![]()
本書の記者は、一般に使徒ヨハネであると信じられている。彼はガリラヤの漁師であった。あるときまで、バプテスマのヨハネの弟子であったと思われる。(1・35、40)
後に、バプテスマのヨハネの証言によって、彼はイエスの直弟子のひとりとなった。その後、しばらくは家業の漁師に戻ったようであるが、まもなく仕事を捨てて、生涯イエスに従う道を選んだ。それ以来、彼は常にイエスとともにおり、福音書に記されている出来事の目撃者の一人となっている。
ヨハネのニックネームは『雷の子』(マルコ3・17)。このことは、彼が激しい気質を持っていたことを暗示している(マルコ9・38、ルカ9・54)。しかし、彼は後に、愛の使徒と呼ばれるまでに変えられたのである。
イエスは、ご自分の身近に置いて訓練するために、十二人の弟子たちをお選びになり、その中でも特にシモン・ペテロ、ゼベダイの子と呼ばれるヨハネと彼の兄弟ヤコブの三人を内弟子として区別しておられる。主イエスの山上の変貌の時、また主が会堂管理者ヤイロの娘をよみがえらせなさった時、そしてゲッセマネにおいて苦悶の祈りをされた時、その場に共にいることを許されたのは、この三人の弟子たちだけだった。
さらにヨハネは、イエスに最も近い弟子と認められていた。過越の食事の間、主の胸によりかかっていたのはヨハネであった。(13・23)
すべての使徒たちの中で、彼ひとりだけがイエスの十字架の側に立ち、主の臨終のメッセージを受け取った。(19・25〜27)
彼は五度も、「イエスの愛しておられた弟子」と呼ばれている。(13・23、19・26、20・2、21・7、20)
彼とシモン・ペテロとは、全く気質を異にしていたが、よく行動を共にしており、初代教会において指導的役割を果たした。(20・2、使徒3・1、11、4・13、8・14)
確かな伝承によれば、彼は長くエルサレムに滞在し、晩年をエペソで過ごした。エペソの教会では長老的存在だったようである。
ヨハネの福音書は、キリストの人格についての最も霊的かつ深遠な教えを含んでいる。主イエスとの特に親密な交わりと長年の経験とが、本書を記すための十分な資格を、ヨハネに与えていると言えるであろう。彼は、使徒たちの中の最年少者と考えられているが、最も長寿を保ち、福音書のほかに、三つの手紙、そして黙示録を記している。
本書は、他の福音書よりもずっと後に書かれた。教会が確立された後に、各地のクリスチャンたちから、福音書のさらに深い真理の説明についての要請があった。これに応えるために、ヨハネは彼の福音書を書いたとされている。
書かれた目的は、
「イエスが神の子キリストであることを、あなたがたが信じるため、また、あなたがたが信じて、イエスの御名によっていのちを得るためである。」(20・31)
だから、本書では、イエス・キリストが神の子として提示されていることは明らかである。
本書の性格に関連して、比較的多く使われている言葉は、『信じる』、『いのち』、『真理』、『愛』、『証言』、『世』・・・。また、キリストの「わたしは・・・である」という偉大な宣言も、ヨハネだけが記している。(6・35、8・12、10・7、11、11・25、14・6)
さらに、「まことに、まことに、あなたがたに告げます」という導入で始まるキリストのことば。(1・51、5・19、24、25他)
また、ヨハネは、聖霊の働きについても詳しく記述している。(7・39、14〜16章、20・22)
〔内容〕
1.プロローグ(1・1〜14)
永遠のことば、神の御子として受肉。「ことばは人となって・・・」
2.神の御子に対するバプテスマのヨハネの証言(1・15〜34)
3.神の御子の公生涯における力の顕現(1・35〜12・50)
4.人目につかないところでなされた神の御子の務め(13〜17章)
5.神の御子の犠牲(18〜19章)
6.復活における神の御子の顕現(20章)
7.エピローグ(21章)
よみがえられた神の御子、生涯と奉仕の主権者
なお、本書には、聖書の中の聖書と呼ばれることばが収められている。
「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。」(3・16)
![]()
本書の著者はルカであると考えられる(1・1)。
彼は、本書と第三福音書を書いた。彼は医者であり、パウロの同労者であった。そのことは、いわゆる「私たち」章節から明らかである。(16・10〜17、20・5〜21・18、27・1〜28・16)
ルカは、また初代教会の最初の歴史家でもあった。
本書は、口語訳聖書では『使徒行伝』となっているが、『聖霊行伝』とも呼ばれてきた。この一つの書巻だけで、聖霊について五十回以上の言及がある。特に、聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされること、聖霊に導かれることについて・・・・。
しかし、主役はイエス・キリストご自身である。福音書においては、主が地上において「行ない始め」られたことについて書かれているが、本書においては、主が聖霊によって、弟子たちを通して行ない続けられたことが記されている。
福音書は主イエスの昇天で終わっていた。使徒の働きは、主イエスが天に上げられることから始まり、パウロがローマで囚人として生活を始めるところで終わっている。その間、約三十年余。
使徒の働きは、ある意味で最も重要な書巻である。なぜなら、
教会の始まり、および初代教会の歴史に関する、神の霊感を受けた唯一の資料を提供している。
パウロの手紙が書かれた背景のいくつかを明らかにしている。
新約聖書正典の中で、福音書から書簡への橋渡しをする役割をになっている。
以下のことがらについての第一の教科書である。
福音宣教の原則
信仰
聖霊の人格と働き
キリスト教の説教の方法と主題
異邦人への使徒パウロの生涯
本書の主題は、1章8節に示されている。
「しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。」
この主題にしたがって、本書を次のように分解する。
1.エルサレムにおける宣教(1〜7章)
聖霊のバプテスマの約束
聖霊降臨とペテロの説教
初代教会の発足
迫害
ステパノの殉教
2.ユダヤとサマリヤの全土における宣教(8〜12章)
ピリポの宣教
サウロ(パウロ)の回心
ペテロの宣教
コルネリオの回心
アンテオケ教会の設立
3.地の果てまでの宣教(13〜28章)
(1) パウロの第一回伝道旅行(13〜15・35)
聖霊による派遣
小アジヤへの宣教(南部ガラテヤ地方)
エルサレム会議
(2) パウロの第二回伝道旅行(15・36〜18・22)
マケドニヤへの宣教(福音が初めてヨーロッパへ。ピリピ、テサロニケの教会誕生)
ギリシャへの宣教
コリントの教会の設立(Ⅰ、Ⅱテサロニケ教会への手紙執筆)
(3) パウロの第三回伝道旅行(18・23〜21・26)
エペソの教会の設立
パウロは、エペソでコリント人へ第一の手紙、マケドニヤでコリント人へ第二の手紙、コリントでガラテヤ人への手紙とローマ人への手紙を書いた。
(4) パウロのローマへの旅(21・27〜28・31)
パウロ、エルサレムで捕らえられる
カイザリヤへ
ローマへ
ここ(ローマ)で書かれた手紙は、一般に獄中書簡と呼ばれている。
エペソ人への手紙
ピリピ人への手紙
コロサイ人への手紙
ピレモンへの手紙
聖霊は福音宣教の御霊であり、いつも、福音が新しい地域に広められる方向に働かれる。迫害でさえ、そのための手段として用いてこられた。そして、パウロの一行が、アジヤ地方への宣教を、キリストの御霊によって禁じられたのは、福音が別の地域、すなわちヨーロッパに伝えられるためであった。
聖書の中で結びのないのは使徒の働きだけである。主イエスは今も働いておられる。聖霊行伝は、まだ終わっていない。
![]()
新約聖書にある二十一の書簡(手紙)のうち、十三は使徒パウロによって書かれた。それらは、パウロ書簡と呼ばれている。
彼はイスラエル人であったが、ローマの市民権を持ち、ギリシャ的教養も身につけており、母国語であるヘブル語はもちろん、当時の世界の共通語であったギリシャ語をも自由に話すことができた。
さらに、偉大な教師ガマリエルに師事して旧約聖書の律法を学び、彼自身も宗教的には厳格なパリサイ人であった。
パウロは、また天幕造りを職業とし、必要に応じて、それにより生計を立てることもできたのである。
彼は教会の迫害者であった。初代教会の最初の殉教者となったステパノが、石で打ち殺された時にも、その場に居合わせた。その後、クリスチャンを捕縛する使命を帯びてダマスコへ行く途中に復活のイエス・キリストに出会い、劇的な回心に至る。やがて、異邦人にキリストの福音を伝える使徒となるが、それは、彼の人間的な資質ではなく、神からの直接の召しによるものであった。ただし、神がパウロのすぐれた資質を、その務めのために用いられたという事実を見逃すことはできない。
ローマ人への手紙は、使徒パウロの第三次伝道旅行の折、コリント滞在中に書かれた。
ローマの教会の大部分は異邦人であり、そこに少数のユダヤ人のグループが含まれていたと思われる。パウロは、それまでローマに行ったことはなかった。しかし、そこに住むクリスチャンたちを訪問し、自分に啓示された神の福音を彼らに伝えることを熱望していた。コリントにいた時、彼はフィベという名のクリスチャン婦人に会った。彼女は教会の執事で、ローマに行こうとしていた。そこでパウロは彼女に、後にローマ人への手紙として知られるようになった一通の書簡を託したと考えられている。
本書の主題は『神の福音』、鍵のことばは『神の義』である。要点は、信仰によって義とされること、その方法及び結果。
ユダヤ人も異邦人も、神の前には等しく罪人であり、救いを必要としている。イエス・キリストの人格において、完全な義が啓示された。このキリストの死と復活を通し、信仰によってこの義を得る道が人類に提供されているということである。
さらに神の福音は、人がこの義にふさわしく生きることができるための原理を示す。それは、キリストを信じる者に聖霊を通して与えられる神聖な力にほかならない。
また、本書においては、ユダヤ人に対する特別な考察がなされている。神は旧約聖書の時代に、この民族を通してご自身を啓示されたのであった。しかしパウロの生きた時代、彼の同胞であるイスラエル民族は、イエスを旧約聖書で預言されたメシヤとして受け入れることを拒み続けていた。しかし、神の賜物と召命はとは変わることがない。(11・29)
本書の終わりの部分でパウロは、それまで述べてきた教理的記述に基づき、クリスチャン生活の実践的な面について教えている。
本書は、大きく三つに区分されよう。
教理的部分(1〜8章)
挿入部分(9〜11章)
実践的部分(12〜16章)
このことを把握した上で、以下のように分解しておく。
1.緒論と主題(1・1〜17)
主題聖句
私は福音を恥とは思いません。 福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力です。なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。(16〜17節)
2.全ての人は有罪(1・18〜3・20)
「義人はいない。ひとりもいない。」(3・10)
3.キリストにあって提供される義─義認─(3・21〜5・21)
「すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵により、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです。」(3・23〜24)
4.人に分け与えられる義─聖化─(6・1〜8・39)
「キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あなた(私)を解放した・・・・。」(8・2)
5.神の計画におけるイスラエル(9・1〜11・36)
この箇所は挿入部分
「神の賜物と召命は変わることがありません。」(11・29)
6.様々な人間関係の中での義なる生き方(12・1〜15・13)
「あなたがたのからだを、神に受け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげなさい。」(12・1)
7.結論と挨拶(15・14〜16・27)
![]()
使徒パウロは、第二回伝道旅行の途中、コリントに一年半ほど滞在し、ここに教会を設立した。(使徒18・1〜11)
その後、第三回伝道旅行で小アジアのエペソに留まっていた彼の所に、コリント教会の状態について好ましくない知らせが届いた。信仰生活における幾つかの質問も寄せられた。
そこでパウロは、それに対処するために、この手紙を書いたと思われる。ここには、教会が直面していた、実に様々な事柄が取り上げられている。分裂、不品行、信者間の訴訟、結婚、偶像にささげた食物、御霊の賜物、復活を否定する者に対する反論、貧しい聖徒のための献金の問題等。
パウロの時代、コリントは地中海に面する商業の中心地として繁栄し、ギリシャ全土で最も重要な都市であった。ローマの植民地だったので、沿岸の各地からローマ人、ギリシャ人、ユダヤ人などが移り住み、文化、芸術、学問のレベルは非常に高かったが、一方では、ぜいたくと浪費と不道徳が、この町にはびこっていた。
教会も、少なからず、その影響を受けていたらしい。この書は叱責の手紙である。直接には、人々の実生活の中に見られる悪習慣を矯正するため、コリントの聖徒たちに宛てて書かれたが、この中には基本的な教理と、信仰生活についての一般的な教えとが含まれている。
ローマ人への手紙の主題が『神の義』であったのに対して、本書簡の主題は『クリスチャンの生活における義』と言えるであろう。義は神から与えられるのであるが、それはキリスト者の行ないによって示されねばならない。
本書を、以下のように分解する。
1.序文(1・1〜9)
はじめの10節までに、『主イエス・キリスト』という称号が六回も使用され、『主』の尊称も全体にわたって多く用いられている。教会の中に多くの無秩序、混乱が侵入してきたのは、コリントの聖徒たちがイエス・キリストを生涯の『主』として認識できなかったからにほかならない。
2.教会内の分裂(1・10〜4・21)
人々は、自分の好みに合った指導者を支持して、互いに争っていた。曰く、パウロ派、アポロ派、ケパ派、キリスト派・・・・・。その原因は、知的高ぶりにあり、教会内の分裂は、信仰の幼稚さを現わすものであった。
3.教会内の道徳的混乱(5・1〜6・20)
不品行。異邦人の中にもないほどのもので、近親相姦さえ行なわれていた。
法廷における聖徒たちの争い。信者同士が訴え合うこと自体が敗北なのであった。
からだの神聖。
「あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか。あなたがたは、代価を払って買い取られたのです。ですから自分のからだをもって、神の栄光を現わしなさい。」(6・19〜20)
行ないの動機は、神の栄光のためである。
4.結婚の問題(7・1〜40)
独身、離婚、奉仕、再婚について、パウロは慎重な表現で、しかも実際的に書いている。
5.偶像にささげられた食物の問題(8・1〜11・1)
個々の問題は、『自由』の原則によって導かれる。
「私はだれに対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。」(9・19)
「すべてのことは、してもよいのです。しかし、すべてのことが有益とはかぎりません。すべてのことは、してもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとはかぎりません。」(10・23)
「あなたがたは、何をするにも、ただ神の栄光を現わすためにしなさい。」(10・31)
私たちは、弱い人をつまずかせないため、そして神の栄光を現わすために、与えられた自由の立場を活用する責任がある。
6.公の礼拝における問題(11・2〜34)
婦人のかぶり物について
主の晩餐について
7.御霊の賜物について(12・1〜14・40)
すべての肢体(メンバー)が、からだ(教会)にとって欠かせない。賜物は全体の益のためにある。愛が動機となっていなければ、どのような賜物も無意味である。
8.復活─クリスチャン信仰の基礎(15・1〜58)
福音の四本柱、
イエス・キリストの死
イエス・キリストの葬り
イエス・キリストの復活
イエス・キリストの顕現
死に対する勝利と励まし
9.結論(16・1〜24)
献金について
パウロの訪問の計画
勧めと挨拶
![]()
本書はパウロ書簡の中で最も個人的なものであり、随所に彼の自己表現が見られる。
肉体的、精神的な弱さ(1・8〜10、12・7〜9、11・23〜33)
外見、話し方(10・1、10、11・6)
十四年間秘められていた秘密(12章)
コリントの教会はパウロの宣教によって生まれたものだが、こゝに彼の動機と権威に疑いを持つ偽教師たちがいた。だから、本書は「パウロの使徒職に関する自己弁明」となっている。彼は余儀なく自分を三十回以上も誇っている。
「本書は厳密な意味において、教理的なものでもなく実践的なものでもなく、全編を通じて強度に個人的なもので、説明あり、弁護あり、抗議あり、提訴あり、譴責、難詰、警告あり、ここには激情を抑制しているかと思えば、最も鋭い皮肉が交えられている。」(フィンドレー)
こうした個人的な弁護という形をとりながら、本書にはパウロの伝道の働き、動機、犠牲、責任、効果性などが記されている。
パウロは、エペソにおいて第一の手紙を書いてのち、エペソを去って(使徒19・23〜41)、トロアスに行き、そこでテトスがコリントから返事を持ってくるのを待った。(2・13)
期待がかなえられず失望して、彼はマケドニヤに行き、そこでテトスに会う。(7・5、6)
そして、彼の勧告に応じて悔い改めた人々(2・1〜11、7・7〜16)がいた反面、まだ、彼の権威を認めたがらない人たちもいることを、パウロは知った。
そこには、新しい危険もあった。ユダヤ教の教師たちが、コリント教会のクリスチャンたちに偽りの教えをもたらし、パウロの務めの動機について非難し、彼の使徒としての権威に対して挑戦をしていたのである。(3・1〜3、4・2、8・20〜23、10・2、8〜10、15、11・1〜5、12、13、12・11〜12、16)
本書の書かれた目的
(1)
コリントを訪問しないことの理由を説明するため(1・15〜24、2・1〜3)
(2) 悔い改めた人々を慰め、励ますため(2・6〜9、7・4、15)
(3) まだ悔い改めない少数の人たちに警告を与えるため(12・21、13・2)
(4) 偽教師に惑わされないように警告するため(11・3、4、13)
(5) 彼が使徒であることについて弁明するため(11、12章)
(6)
エルサレムにいる貧しい聖徒たちのために彼らが約束した寄付金を納めることを奨励するため(8・10、11)
本書の分解は困難であるが、一応の区分をすれば、
1.緒論(1・1〜11)
慰めの神
苦難と慰め
「もし私たちが苦しみに会うなら、それはあなたがたの慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら。それもあなたがたの慰めのためで、その慰めは、私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなたがたに与えるのです。」(1・6)
2.神の使者としてのパウロ(1・12〜7・16)
彼の推薦状
ユダヤ主義者との比較
「神は私たちに、新しい契約に仕える者となる資格を下さいました。文字に仕える者ではなく、御霊に仕える者です。文字は殺し、御霊は生かすからです。」(3・6)
3.ユダヤの貧しい聖徒たちのための募金(8・1〜9・15)
4.パウロの使徒職の弁明(10・1〜13・10)
彼に与えられた驚くべき啓示
肉体のとげ
人の弱さとキリストの力
「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現われるからである。」(12・9)
5.結論(13・11〜13)
祝祷
「主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなたがたすべてとともにありますように。」(13・13)
本書には、聖書研究のテーマとしてふさわしい重要な『ことば』が含まれている。
『喩え』(2・15、3・3、18、4・7、5・20)
『慰め』
源(1・3)
目的(1・4、6、7)
報い(1・5)
信者のつとめ(2・7)
人を通しての慰め(7・4、6、7、13)
命令(13・11)
『精神、心、からだの苦しみを表 わすことば』
『喜び』
『勝利』
『霊の戦い』
この世の神(4・4)
戦いの武器(10・4)
サタン(11・14、15)
![]()
ガラテヤは小アジヤの一部で、パウロが第一回目の伝道旅行をした地方だとも考えられている。(使徒13、14章参照)
パウロが諸教会に宛てゝ書いた手紙の冒頭には、一つの例外を除き、神に対する賛美や感謝のことばが記されている。その例外が本書で、彼の語調は特に厳しい。
「私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが宣べ伝えた福音に反することをあなたがたに宣べ伝えるなら、その者はのろわれるべきです。」(1・8)
人が神の前に義と認められるのは律法の行いによらず、イエス・キリストを信じる信仰による。これは福音の中心的真理である。ところが、彼がガラテヤの諸教会を最後に訪れた後に、ユダヤ主義者が来て、救われるためには割礼を受けなければならないと言って人々を混乱させた。そればかりかパウロの使徒職についても非難攻撃した。こうして、ガラテヤのクリスチャンたちは、再び律法の束縛の下に閉じ込められてしまったのである。
これらの問題に対処するために、パウロは本書簡を執筆した。
本書の主題は、『キリスト者の自由』である。或る聖書教師曰く、
「ガラテヤ人への手紙は、われわれの自由としてのイエス・キリストを描いている。」
〔内容〕
1.パウロの使徒職の弁護─自由の使徒─(1、2章)
「生まれたときから私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を宣べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することをよしとされたとき、私はすぐに、人には相談せず先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも上らず、アラビヤに出て行き、また ダマスコに戻りました。」(1・15〜17)
パウロの務めは、啓示によって直接神から与えられたものであった。
「私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が、この世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。」(2・20)
これが使徒パウロの働きの原点となっている。
2.信仰義認の教理─自由の教理─(3、4章)
「義人は信仰によって生きる。」(3・11)
神の前に義と認められる、
聖霊を受ける、
神の奇蹟を体験する、
これらはすべて律法の行いによるのでなく、十字架につけられたイエス・キリストを信じる信仰によるものである。人間の罪深い性質は律法のいましめを完全に守ることができない。律法は、その事実を教え、救いの方法として人を信仰にまで追いやるために与えられたにすぎない。
「こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。」(3・24)
私たちは、神の御子を信じる信仰によって律法の束縛から贖い出され、神の国の相続人とされた。もはや奴隷ではなく神の子であり、自由人なのである。
3.実践的教え─自由の生活─(5、6章)
「キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。」(5・1)
「兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。」(5・13)
『自由』とは勝手気儘を意味しない。喜んで神に従う能力である。それは、御子を信じる者のうちに内住される神の御霊によって与えられている。
「私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。」(5・16)
この結果、信者の生活の中に御 霊の実が結ばれて行く。
「御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。」(5・22〜23)
「内的な御霊の実を結ぶことは、外面的な肉の服従よりはるかに大切であり、また、もし聖霊が内にあって支配しているなら、外的な人間の行為も当然それに応じて抑制されるはずである。このように、キリスト者の生命は、人間のいやいやながらの意志と神の横暴な意志との間の争いではない。それは、キリストによって内的生命が不断に支配されるようになることなのであるから、『キリストが、わたし のうちに生きておられる』というのは、自由の主観的局面なのである。神の意志は、抑圧的強制によってではなく、私たちの自由な同意によって、私たちを支配するものとなる。」(M・C・テニイ『ガラテヤ人への手紙』より)
![]()
この手紙は使徒パウロがローマで監禁されていたときに書き送った四つの獄中書簡の一つである。他はピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙。この内、エペソ、コロサイ、ピレモンは同時期に書かれ、同じ使者(テキコ)によって宛先に運ばれた。
エペソ教会はパウロが三度目の伝道旅行の途中、この地に三年ほど滞在している間に創設された。
本書簡はエペソの教会のみに宛てられたものではなく、もとはアジヤ地方の諸教会へ回状として送られたと考えられ、これらの教会には若干のユダヤ人もいたが、会員の大部分は異邦人クリスチャンだったようである。
パウロが、この手紙を書いたとき、エペソ教会の実情も彼の念頭にあっただろう。(クリスチャンらしくない歩み、ユダヤ人信者と異邦人信者の間の不一致等)
けれども、内容は地方教会の枠をはるかに超えて実に深遠、且つ格調が高い。パウロは獄中において深く沈思黙考する機会が多く、全宇宙に対する神の経綸を一層綿密に記述する必要のますます切なるものを感じたと言われている。(ヘンリー・シーセン)
エペソ人への手紙において、パウロは『教会』という言葉を、宇宙に唯一つ存在する『普遍教会』の意味で使っている。それはキリストのからだであり、神の永遠の計画の中で、イエス・キリストの贖いを通して、神ご自身によって建てられたものである。
その計画とは、
「天にあるものも地にあるものも、いっさいのものが、キリストにあって一つに集められることなのです。」(1・10)
クリスチャンは、この永遠の計画が遂行されるために召されており、聖なる召しは聖なる歩みを私たちに要求する。
教会のかしらなるキリストは、全能の神の力によって死から復活し、天に上り、神の右に着座された。霊的な意味において、神は信者をもキリストとともによみがえらせ、ともに天の所にすわらせてくださった。クリスチャンの生き方は、この世の行動様式とは対照的な立場、天の領域を基準とし、聖霊の力を通して生み出されて行く。これが、召しにふさわしい歩みにほかならない。
マイヤー・パールマンによる主題の要約。
「教会はキリストにあって選ばれ、贖われ、一つとされている。それゆえに教会は、神の武具により、主の力によって、一致と新しい生命に歩むべきである。」
〔内容〕
A.教理的部分(1〜3章)
1.挨拶(1・1〜2)
2.信者の召し(1・3〜23)
神の救いの計画
父なる神による予定・選び
御子イエスによる贖い
聖霊による保証
保証(アラボーン)は、将来、信者のものとなるべき完全な贖い(救い)の手付け金を意味する。
パウロの祈り─知るように
知恵と啓示の霊によって
召しによって与えられる望み
聖徒の相続財産
神の全能の力の偉大さ
キリストの主権
キリストのからだなる教会の栄光
3.教会─キリストのからだ(2・1〜3・21)
罪の中に死んでいた者
神の恵みによる救い
良い行ないをするために造られた神の作品
ユダヤ人と異邦人の和解
神の家族
福音の奥義
その奥義とは、福音により、キリスト・イエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、ともに一つのからだに連なり、ともに約束にあずかる者となるということです。
パウロの祈り─聖霊の満たし
御霊による内なる人の強化
キリストの内住
キリストの愛を知る
神ご自身の満ち満ちたさまにまで満たされるように
B.実践的部分(4〜6章)
4.信者の歩み(4・1〜6・9)
「召されたあなたがたは、その召しにふさわしく歩みなさい。」
教会の一致 「御霊の一致を熱心に保ちなさ い。」
新しい歩み
5.クリスチャンの霊的戦い(6・10〜20)
敵
「悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身に着けなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。」(6・11、12)
神の武具
霊の戦いのための祈り
「どんなときにも御霊によって祈りなさい。」(6・18)
6.結び(6・21〜24)
![]()
本書は、エペソ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙と合わせて、使徒パウロがローマで投獄されていたときに書いた四つの獄中書簡の一つである。
ピリピは今のギリシャ地方の北部、マケドニヤにあった。
パウロの第二次伝道旅行の初期、御霊の導きによってイエス・キリストの福音が初めてヨーロッパに伝えられた。そのとき最初に設立されたのがピリピの教会である。この手紙を読む準備として使徒の働き16章を読むとよい。
使徒パウロは、ピリピ教会のクリスチャンたちに対して特別に親しい感情を抱いていたらしい。この書簡を読むと、お互いの間にあった温かい情愛が伝わってくるのが感じられる。
或るとき、獄中のパウロを訪ねて、ピリピ教会の使者エパフロデトがローマにやって来た。パウロは彼を通して教会からの贈り物を受取り、また愛するクリスチャンたちの近況を聞くことができた。彼の来訪は、パウロにとって、この上ない励ましとなった。手紙の中で、こう書いているほどだ。
「私の兄弟、同労者、戦友、またあなたがたの使者として私の窮乏のときに仕えてくれた人エパフロデト・・・。」(2・25)
このエパフロデトがローマ滞在中、死ぬほどの病気にかかり、この知らせはピリピにまでも伝わったようである。彼が回復したとき、パウロは大急ぎでエパフロデトを送り帰すことに心を決めた。この事情を利用して、ピリピの教会に対する感謝と勧告の手紙を彼に託した。
本書のキー・ワードは『喜び』である。
「ある偉大な学者が、ピリピ書の大要は、『私は喜んでいる。あなたがたも喜びなさい。』であると言った。この手紙は喜びで満ちている。各章ごとに、銀の鈴が鳴るように『喜び』、『喜びなさい』、『喜ぶこと』などの言葉を響かせている。投獄と、また彼が死刑台の影に身を寄せているという事実にもかかわらず、使徒パウロは喜ぶことができたのである。その主題をつぎのように要約しよう。すなわち、あらゆる境遇のもとにおいて現わされるクリスチャン生活と奉仕の喜びである。」(マイヤー・パールマン)
1.序文(1・1〜11)
挨拶
パウロの祈り
2.ローマでのパウロの近況(1・12〜26)
獄中でのパウロの喜び。彼は、自分の投獄が福音の前進に役立ったことを喜んでいる。
3.勧めと模範(1・27〜2・30)
福音にふさわしい生活の勧め
霊的一致の勧め
コリントの教会に見られたような分裂はなかったが、信者間の或る些細な相違によって、教会内に一致がそこなわれる危険性のあることをパウロは感じとったらしい。一致の基礎は謙遜と自己否定の精神にある。
「何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。」(2・3、4)
キリストの模範(2・5〜11)
謙遜と自己否定の最大の模範はキリストご自身のうちに見られるものだ。ここは、教理的にも重要な個所である。すなわち、
自己の救いの達成への勧め。
極限までご自分を低くされたキリストの姿(イメージ)にまで変えられて行くこと。これが信者の救いの目標でなければならない。
テモテの模範
エパフロデトの模範
4.異端に対する警告(3章)
律法主義者に対する警告
パウロ自身、パリサイ人と呼ばれる厳格な律法主義者であったが、キリストを知ることによって外面的なユダヤ主義を克服した。パウロにとっての唯一の目標は、律法による自分の義を確立することではなく、キリストの死に合わせられ、死者の中からの復活に達することであった。
反律法主義者に対する警告
「信者は、天的歩みを保つべきである。なぜなら、我らは天的希望、すなわち、主イエスの来臨における栄化の望みをもっているからである。」
5.終わりの勧告(4章)
堅く立つこと
主にある一致
不一致の主な原因は、ふたりの有力な婦人─ユウオデヤとスントケ─の確執にあったようだ。
喜ぶこと。「いつも主にあって喜びなさい。」
主ご自身が環境であるなら、私たちは、どのようなときにも喜ぶ理由を持っていることになる。
寛容
思い煩わないこと
すべての良いことに心を留めよ
教えの実践
贈り物に対する感謝(10〜20)
挨拶と祝祷
![]()
本書は、パウロがローマで第一回目の獄中生活を送っていた時期に書かれた、いわゆる獄中書簡の一つで、他にエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、ピレモンへの手紙がある。
パウロがコロサイの町を訪問したことを示す個所は、新約聖書の中に見られない。
彼が第三回伝道旅行の期間、エペソに三年ほど滞在したことがあリ、「アジヤに住む者はみな、ユダヤ人もギリシャ人も主のことばを聞いた。」とある(使徒19・10)。本書にエパフラスという人物の名が記されているが、多くの聖書注解者によれば、彼はそのとき信仰に入り、エペソの東方160キロの所にあるコロサイに、パウロの代わりに遣わされ、コロサイ教会の基礎を築いた。
ピレモンは、この教会の重要な会員であった。
パウロがエペソを去って後、コロサイの教会に異端的な教えが入って来た。この問題に対処するために、エパフラスはローマにパウロを訪問したが、彼自身捕らえられたため、パウロはこの手紙を書き、テキコに託してコロサイの教会に送った。なお、エペソ人への手紙、ピレモンへの手紙も、同じ時期、同じ使者によって宛先に届けられている。
コロサイの異端は、キリスト教信仰にユダヤの律法主義と異教哲学の混じった教理を加えようとするものであった。この異教哲学は、後にグノーシス派として知られるようになり、キリスト信仰にとって最大の危険を及ぼすものとなった。
グノーシス派の人たちは、聖書に啓示された知識よりも更に深い知識、すなわち、ごくわずかの選ばれた者だけに与えられた知識を持っているとして、自らを誇示した。『グノーシス』とは『知識』を意味するギリシャ語から来ている。
このグノーシス派の教えの背景には、霊は善であり、物質は悪であると言う二元論がある。そこから次のような珍説が導き出されてきた。
「絶対的善である神が悪である物質を造るはずはない。また神は本質的に聖であり、肉は本質的に悪であるから、両者の間には無限の深淵があり、互いに接触し、親しみ、交わることは不可能である。
それでは、聖なる神が悪の状態の中に住む人類に近づき、これと交わるための方法とは何か?
まず、本質的に聖い神から、ほんの少しばかり、聖さにおいて劣る存在者が出、そこから聖さで更に劣る第三の存在者が出、第三から第四というように、次第に聖さと神性の薄くなっていく存在者を経て、ついに、ほとんど人間に近かったため人間に触れることのできた一人の人(イエス)が現われるに至った。」
グノーシス派の説によれば、聖さにおいて神より劣る第二番目以下の存在者はデミウルゴスと呼ばれ、創造のわざは、これら低次の神によるものとされた。また、人間は肉体を持っているので神と直接に交わることができず、御使いの仲介が必要だとも考えられていた。この異端は、イエスの主権、神性、神と人との仲介者としての職務などに対して打撃を加えるものであった。
この間違った教えに対抗して、パウロが本書において特に強調しているのはキリストの卓越性である。キリストこそ真の神、万物(天使を含めて)の創造者、宇宙の支配者、すべての被造物を神と和解させる唯一の仲介者、そして教会のかしらである。
エペソ人への手紙と本書簡は、同じ著者によって、同じ時期に書かれた。多くの個所がよく似ているので、双子書簡と呼ばれてきたが、両者の主題は全く異なっている。前者はキリストのからだなる教会の一致とその雄大さを扱い、後者は教会のかしらなるキリストの神性と、その充足性を扱っている。
〔内容〕
1.緒論(1・1〜12)
挨拶
感謝
祈り
諸教会に対するパウロの最も美しい四つの祈りの一つ。
エペソ1・16〜19
エペソ3・14〜19
ピリピ1・9〜11
コロサイ1・9〜12
2.説明(1・13〜2・3)
キリストの卓越性
すべてのもののかしら
和解の務め
神の奥義
知恵と知識の源
3.反論(2・4〜23)
異端との戦い
だましごとの哲学
律法主義
天使礼拝
禁欲主義
4.勧告(3・1〜4・6)
キリストにある新しい生き方
天にある立場
『古い人』の死
『新しい人』を着ること
家族に対する訓戒
その他
5.結び(4・7〜18)
挨拶
![]()
テサロニケの教会は、使徒パウロが第二回伝道旅行において、ピリピを去った後に設立された。紀元51年頃と考えられている。
歴史的な背景については、使徒の働き17章参照。当時のテサロニケは、ピリピとともにマケドニヤ地方の主要都市であった。この教会を形成していたのは、ユダヤ人と言うよりは、大部分が異邦人だったらしい。
パウロは、テサロニケに、それほど長くは留まらなかった(多分一ヶ月未満)。同胞のユダヤ人による迫害が激しかったからである。 この後、パウロはアテネを通ってコリントへ行くが、アテネに着いた時、彼はテサロニケの若い教会を気づかって、テモテを遣わした。テモテが戻って来た頃、パウロは既にコリントに移っていて、そこでテサロニケのクリスチャンたちの様子を知った。
彼が本書簡を書いたのは、コリント滞在中だったと考えられている。パウロ書簡の中では最も初期のものであろう。
本書簡の書かれた理由。
(1) 信者たちは激しい迫害に耐えていた。
(2)
すでに死んだ者はキリストの再臨の恵みにあずかれないと考えて悲しんでいる遺族もいた。
(3)
ある人たちはパウロの教えを誤解して、キリストは間もなく再臨されるのだから働く必要はないと考え、日常生活の義務を放棄していた。
パウロは、以上のような事柄に対処する必要を感じて、この手紙を書いたと思われる。彼は執筆者の中にシルワノとテモテの名を加えている。シルワノは第二回伝道旅行の同労者シラスであろう。テモテはパウロの霊の子であり、また真実の弟子であった。
本書簡の主題はキリストの再臨である。各章の終わりに、主が再び来られることについて書かれているのに気づく。主の再臨は、パウロがテサロニケで特に力説した教理だったことは明らかである。そして彼は、この真理を実際面からも取り扱い、それを信者の生活と態度に適用している。
主が再び来られることについては、新約聖書260章の中に318回、マタイの福音書からヨハネの黙示録まで20節に一度の割合で記されている。イエス・キリストの再臨は、最も重要なキリスト教教理の一つであると言えよう。
ロンドンのロバート・リー氏による本書の概略。
主の再臨は、
1.初心の信者に霊感を与える希望(1章)
「(あなたがたがどのように)御子、・・・イエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。」(10)
2.忠実なしもべに対して励ましを与える希望(2章)
「私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのはだれでしょう。あなたがたではありませんか。あなたがたこそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。」(19〜20)
3.信者に対して潔めを与える希望(3・1〜4・12)
「(どうか、・・・主・・・ご自身が)あなたがたの互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ちあふれさせてくださいますように。また、あなたがたの心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で、聖く、責められるところのない者としてくださいますように。」(3・12〜13)
「神のみこころは、あなたがたが聖くなることです。」 (4・3)
「落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。」(4・11)
4.肉親を失った者に対して慰めを与える希望(4・13〜18)
「主は、・・・ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次ぎに生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。こういうわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい。」(4・16〜18)
5.眠っているようなクリスチャンに対して目覚めを与える希望(5章)
「いつも喜んでいなさい。
絶えず祈りなさい。
すべての事について、感謝しなさい。」(16〜18)
「平和の神ご自身が、あなたがたを全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨のとき、責められるところのないように、あなたがたの霊、たましい、からだが完全に守られますように。」(23)
「主の再臨のために用意をせよ。なぜなら、主は今日来られるかも知れないのだから。」
![]()
この第二の手紙は第一の手紙のすぐあと、コリントに滞在中のパウロによって執筆された。テサロニケ人への手紙第一、二は、現存するパウロ書簡の最も初期のものと考えられている。
本書の主題は、第一の手紙と同じく主イエス・キリストの再臨。主が再び来られることについては、新約聖書260章の中に318回、およそ20節に一度の割合で記されている。
本書簡が書かれた理由。
(1)
続く迫害と患難とに耐えながら信仰を保っている聖徒たちを慰めるため。
(2)
『主の日』はすでに来た、という意味の間違った教えを矯正するため。
誤った啓示によって、あるいはパウロから送られてきたとされる偽の手紙などから、テサロニケの教会の中には、大患難時代がすでに始まったとして心を騒がせている人々がいた。
(3) 怠惰な生活をしている者たちに、警告を与えるため。
キリストの再臨の教えを誤解して日常の義務を放棄し、教会からの経済的援助を頼りに締まりのない生活をしている人たちがいた。
パウロは第一の手紙で、主の来臨が突然で、思いがけない時に起こると書いた。この第二の手紙では、それが『背教』の後でなければ起こらないと説明している。「突然」は、「ただちに」を意味するものではないことを示しているようである。
〔内容〕
1.迫害の中における慰め(1章)
テサロニケのクリスチャンたちが迫害と患難に耐えながら信仰を保ち、その信仰が目に見えて成長し、相互の愛が増し加わっていることに対する感謝と称賛。
主イエスが再び地上に来られるとき、正しいさばきが行なわれるということ。神は迫害者に報復し、福音のゆえに苦しみを受けた聖徒たちに報いとして安息を与えてくださる。
2.『主の日』についての教え(2章)
主の日とは、神がイスラエルと諸国民を審判をもって取り扱われる特別の期間を指し、それは一大患難の時と考えられている。
ある偽教師たちが、この主の日がすでに来た、と教えて教会を混乱させていた。しかし、神のご計画によれば、主の日が来る前にまず背教が起こり、『不法の人』が現われる。彼は滅びの子、荒らす憎むべき者、反キリスト、獣などとも呼ばれ、自分こそ神であると宣言する。不法の人の到来はサタンの働きによるが、それを引き止めているものがあるという。『引き止めているもの』をローマ帝国であると理解した人々もいたが、直接には聖霊を意味し、間接には御霊が住まわれる教会を指し示すとも考えられている。主イエスはキリストの弟子たちを地の塩だと言われた。塩は保存する要素、腐敗を防ぐ要素である。教会の携挙によって、この要素が取り除かれるとき、不法が地に満ちるというわけである。
不法の人はキリストが地上に来られる前に現われる。しかし、主イエスがご自身の民を天に携え上げるまで、彼は人々の目に見えるようなかたちで来ることはない。しかし、その時になると、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされる。
3.奉仕における実際的勧め(3章)
テサロニケのクリスチャンに対するパウロの祈りの要請。
「終わりに、兄弟たちよ。私たちのために祈ってください。主のみことばが、あなたがたのところでと同じように早く広まり、またあがめられますように。」(1)
私たちとって、主の再臨のための最善の備えは、神のことばの宣教である。
テサロニケの教会の中に、主の来臨について一つの誤った見解があった。ある者たちは、キリストが間もなく来られるという期待を口実に、生活のために働くことを辞め、裕福な人々によって扶養される権利を主張していた。
パウロは、このような怠惰な者たちを非常に厳しく扱っている。彼自身、霊的な務めのゆえに諸教会から経済的な援助を受ける権利があったにもかかわらず、人のパンをただで食べることをせず、だれにも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き、身をもって模範を示してきた。
聖書は、必要のある人々、貧 しい人々に施しをすることを勧めると同時に、働ける体力を持ちながら働こうとしない怠惰な人々に対しては非常に厳しい態度をとるよう命じている。
「もし、この手紙に書いた私たちの指示に従わない者があれば、そのような人には、特に注意を払い、交際しないようにしなさい。」(14)
「パウロの、またはキリストの教えで、物乞いを職業とする強壮な、怠惰な者に対しての愛を奨励する箇所は、聖書のどこにもない。」
「働かざる者、食うべからず。」これは聖書的な原則でもある。
![]()
テモテへの手紙第一、二、およびテトスへの手紙は牧会書簡として知られている。
これらは教会政治について教え、指導する目的で、使徒パウロから若い牧会者たちにあてて書かれた。テモテはパウロにとって信仰の面での息子、弟子、また忠実な同労者であった。
テモテの父はギリシャ人であるが、彼は母方の祖母ロイスと、母ユニケの信仰を引継ぎ、幼いころから聖書に親しんで来た。『使徒の働き』によれば、パウロは異邦人への伝道旅行の途上でテモテに出会い、その霊的資質に魅かれ、以後、彼の旅行に同行させることとなった。
パウロが、彼の関係した諸教会および個人あてに書いた手紙のうち、十三書簡が新約聖書に収められているが、コリント人への手紙第一、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケ人への手紙第一、二、ピレモンへの手紙の六通に、彼は共同執筆者としてテモテの名を加えている。
特に、ピリピ、コロサイ、ピレモンの三書が獄中書簡であることを考えれば、パウロが投獄されていた時、テモテも彼と一緒にローマに滞在したことがあったようだ。パウロは、第一回目の投獄から釈放された後、何かの事情でエペソ教会の牧会の働きをテモテに委ねたと思われる。
エペソは、使徒パウロが第三回目の伝道旅行の途中、約三年間滞在して教会の創設のために最大の働きをした所である。後にローマの獄中からも手紙を書いている。
ここは初代教会の時代、キリスト教の中心的な地域となった。しかし、パウロがエペソ教会の長老たちに告別の辞を述べていたとき、彼は将来に危険を感じていた。
私が出発したあと、狂暴な狼があなたがたの中に入り込んで来て、群れを荒らし回ることを、私は知っています。あなたがた自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分のほうに引き込もうとする者たちが起こるでしょう。(使徒20・29〜30)
このことが現実となっていた。彼はマケドニヤから、この書簡をテモテに送り、彼の職務の権限と責任を教え、偽教師たちについて彼に警告を与えている。この青年は神経質で、控えめな性格であったため、神から与えられた権威を主張することに対して引込み思案になる傾向があった。それで、彼を励ます必要があったわけである。
本書のキー・ワード(鍵の句)。
「私は、近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらも、この手紙を書いています。それは、たとい私がおそくなったばあいでも、神の家でどのように行動すべきかを、あなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は、真理の柱また土台です。」(3・14〜15)
「年が若いからといって、だれにも軽く見られないようにしなさい。かえって、ことばにも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも信者の模範になりなさい。」(4・12)
マイヤー・パールマンによる本書の主題。
「クリスチャンの教役者の資格と義務、ならびに、その教会、家庭、世に対する彼の関係。」
〔内容〕
1.挨拶(1・1〜2)
2.偽りの教えについての警告(1・3〜11)
当時の最も危険な異端の一つはグノーシス主義と呼ばれるもので、果てしのない空想話や系図などについての無益な議論、また律法を無視するような教えが教会内に横行していた。
3.パウロの個人的な証しとテモテへの勧告(1・12〜20)
4.公の祈り(2・1〜15)
祈りの対象
「すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝がささげられるようにしなさい。」(1)
その当時、ローマの皇帝はネロであった。この邪悪な暴君の悪政下でパウロは投獄され、殉教の死を遂げることを知っていた。キリスト者は良い施政者のためだけでなく、悪い支配者のためにも祈るべきことを勧められている。
男子の態度
婦人の態度
5.教会役員の資格(3・1〜13)
監督について
執事について
6.イエス・キリストの良き奉仕者の歩み(3・14〜4・16)
敬虔の奥義
偽りの教理
偽りの教理に対処する方策
七、牧会上の勧告(5・1〜6・19)
年配者についての勧告
やもめについての勧告
長老についての勧告
奴隷について勧告
偽教師についての勧告
金銭についての勧告
神の人(テモテ)に対する勧告
富める人たちについての勧告
8.結び(6・20〜21)
テモテヘの最後の勧告と挨拶
![]()
本書簡の背景には、ローマ皇帝ネロによる激しい迫害があった。この手紙は、使徒パウロが殉教を待っている間に執筆されたものであろう。
紀元64年、ローマに大火が起こった。新しい、より美しいローマを建設するため、ネロ自身が火をつけさせて都を焼いたと言われている。人々は彼に疑いをかけた。皇帝の嫌疑をそらすために、誰かスケープ・ゴート(身代わりの山羊、犠牲)が立てられなければならない。そこで目をつけられたのがナザレのイエスに帰依する新宗教の人々の群れ─クリスチャン─であった。そこで、ローマの内外において多数のキリスト者が捕らえられ、残忍きわまる方法で殺された。
『使徒の働き』は、紀元63年頃のパウロのローマ監禁をもって終わっているが、彼はその後釈放され、テモテへの手紙Ⅰを書いた。そして、このキリスト者迫害に続いて再び捕らえられ、ローマに連れ戻され、66年か67年に処刑されたと信じられている。パウロは、当時のキリスト教世界の指導者であり、大火の直前、二年間ほどローマに滞在していたこともあって、放火の最高責任者という口実で捕縛されたことは想像に難くない。
この二度目のローマ投獄は、使徒の働きに記されている最初の時とは、事情がかなり違っていた。
(1)
最初の時、パウロは同胞のユダヤ人によって捕らえられ、カイザルに上訴したためにローマへ護送されたが、今度はローマ帝国の犯罪人として捕縛された。
(2)
最初の時、彼は自費で借りた家に住むことを許されたが、今度は厳重に監禁されている。
(3)
最初の時、彼は誰とでも自由に会うことができたが、今度は厳しく制限されている。
(4)
最初の時、彼の周囲には大勢の友人がいたが、今度は孤独であった。
(5)
最初の時、彼には釈放される望みがあったが、今度は死を予期している。
パウロは殉教の時が間近いことを知った。激しい迫害のため、殆どのクリスチャンたちが彼を見捨てて離れて行った。このような状況の中で、パウロは彼の信仰の子、テモテに会うことを切に願った。
この書簡は、次のような理由で書かれたと考えられる。
(1) テモテに、ローマに来るよう要請するため。
当時の情勢から、これは実現しなかったようだ。パウロも、それは予期していたらしい。
(2) 偽教師たちについて、彼に警告するため。
(3) 彼に、その義務を果たすよう励ますため。
(4) 来たりつつある迫害に対して、彼を力づけるため。
本書の主題は、「迫害と背教を考慮して、主イエスと真理への忠誠」。
〔内容〕
1.緒言(1・1〜5)
挨拶
祈り・感謝・願望
テモテの信仰の由来
2.来たるべき苦難と迫害を考慮しての勧告(1・6〜2・13)
「私の按手をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を、再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。」(1・6〜7)
「神の力によって、福音のために私と苦しみをともにしてください。」(1・8)
「あなたにゆだねられた良いもの(健全な教理)を、私たちのうちに宿る聖霊によって、守りなさい。」(1・14)
「キリスト・イエスのりっぱな兵士として、私と苦しみをともにしてください。」(2・3)
3.現在の背教についての勧告(2・14〜26)
「あなたは熟練した者、すなわち、真理のみことばをまっすぐに説き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神にささげるよう、努め励みなさい(健全な教理)。」(2・15)
「俗悪なむだ話を避けなさい。」(2・16)
「若い時の情欲を避け、きよい心で主を呼び求める人たちとともに、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい(健全な生活)。」(2・22)
「主のしもべが争ってはいけません。」(2・24)
4.終わりの日の背教を予期しての勧告(3・1〜4・8)
「終わりの日には困難な時代がやって来ることをよく承知しておきなさい。」(3・1)
「見えるところは敬虔であっても、その実を否定する者・・・。こういう人々を避けなさい。」(3・5)
「確かに、キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う者はみな、迫害を受けます。」(3・12)
「私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。」(4・6、7)
5.結び(4・9〜22)
![]()
本書簡はテモテへの手紙Ⅰと同じ頃、多分その直ぐ後、パウロによって執筆されたと考えられている。
テトスもテモテと同様、パウロによる回心者の一人だったのであろう。彼らはパウロにとって霊の息子、弟子、また忠実な同労者だった。
テモテはギリシャ人を父としていたが、母がユダヤ婦人だったのでユダヤ人として育てられ、パウロから割礼を受けた。これに対して、テトスは純粋な異邦人(ギリシャ人)であり、割礼を受けていない。(ガラテヤ2・3)
テトスは、年齢的にも、信仰的にも、テモテの先輩だったようである。テトスに関する新約聖書の記事の要点は次のとおり。
(1)
パウロとバルナバに同行してエルサレム会議に出席した。
(2)
コリントに派遣され、教会内に起こっていた諸問題の処理にあたった。
使徒パウロは、テトスを非常に信頼し、コリント教会の混乱の収拾という、困難で重要な使命を彼に託したのである。テトスが、その使命を立派に果 たしたことについては、パウロの書いたコリント人への手紙Ⅱの中に述べられている。
(3)
パウロはクレテに航行するときにテトスを同行し、そこで未組織の諸教会を整えるために彼を残した。本書簡は、クレテの若き牧師テトスに宛てて書かれたものである。
クレテは島であって、そこの教会の中核となったのは、多分、ペンテコステの日にエルサレムに来ていたクレテ人たちだと思われる。(使徒2・11)
使徒パウロのクレテ訪問に関する言及は、ローマへの航海の途中に彼が立ち寄ったという『使徒の働き』27章の記事のみで、それ以外にはただ、テトスの手紙の中に暗示されているだけである。しかし、クレテの諸教会の設立がパウロの働きによったことは確かであろう。記録されていないパウロの訪問の結果だったかも知れない。あるいは、コリントかエペソにおけるパウロの宣教によって回心した人々による果実だったとも考えられる。これら両都市はクレテに近く、商業上緊密な関係にあった。
当時、クレテ人の道徳的評判は非常に悪かった。パウロは、クレテの哲学者エピメニデス(BC600年)の詩を引用して、そのことについても述べている。
彼らと同国人であるひとりの預言者がこう言いました。
「クレテ人は昔からのうそつき、
悪いけだもの、
なまけ者の食いしんぼう。」
この証言はほんとうなのです。」(1・12〜13)
当時、教会はまだ組織化されておらず、クレテ人の信頼できない不道徳な性格に加えて、教会内には誤った教理を教える偽教師たちがいた。テトスの牧師としての働きが困難なことは明らかだった。そこで、彼を教え励ますためにパウロはこの手紙を書いたわけである。
本書簡は、若い牧師に対する実際的な忠告に満ちており、彼の教会管理に対する指示を与え、当時の異端に関して彼に警告している。
「これは短い書簡であるが、キリスト教教理の精髄のようなものであって、クリスチャンの知識と生活のため必要なものをすべて含むように構成されている。」(マルチン・ルター)
テトスへの手紙とテモテへの手紙第一は、両方とも同じ一般的主題を扱っていて、それはキリスト信者の集会に適当な指導者を任命すること。クレテでのテトスとエペソでのテモテ。共通の問題であった。
主題は、「教会の組織化と、理想的な働き人」
〔内容〕
A.教会の健全な秩序
1.挨拶(1・1〜4)
2.長老または監督の資格(1・5〜9)
「その人が、非難されるるところがなく、ひとりの妻の夫であり、その子どもは不品行を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。」(6)
「監督は神の家の管理者として、非難されるところのない者であるべきです。」(7)
3.偽教師に関する警告(1・10〜16)
B.教会の健全な教理
4.各グループに対する教え(2・1〜15)
「あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。」(1)
老人に対して
若い人に対して
テトス自身に対して
奴隷に対して
キリスト者生活の基盤
C.教会の健全な行動
5.社会人としてのあり方(3・1〜2)
6.良いわざに励むべき根拠(3・3〜8)
7.偽教師に対すべき態度(3・9〜11)
8.結び(3・12〜15)
![]()
本書は、使徒パウロからピレモンへ宛てられた個人的な手紙である。二十五節からなる、わずか一章の書簡にすぎない。また、教理やクリスチャンの行動についての直接的な教えも含まれていない。しかし、この中には、クリスチャンの愛と赦しが、礼儀正しく、また巧みな表現によって強調されている。
「キリスト・イエスの囚人であるパウロ、および兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ。また、姉妹アピヤ、私たちの戦友アルキポ、ならびにあなたの家にある教会へ。」(1、2)
ピレモンはコロサイの教会の重要な会員だった。アピヤは彼の妻、またアルキポは集会の牧会者だったと思われる。ピレモンの家は『家の教会』として使われていて、信者の人たちが定期的に集まり、ここで礼拝が行なわれていたようである。
当時、パウロはローマで第一回目の獄中生活を送っていた。この時期に書かれたのが、いわゆる獄中書簡で、本書は、その一つ。他にエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙がある。エペソ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙は、テキコという人物によって同じ時期に、それぞれの宛先に届けられた。
パウロがコロサイの町を訪問したという記録は、聖書の中には見当らない。彼は、第三回伝道旅行においてエペソに三年ほど滞在した。エペソの教会は、この時に創設されたが、この期間にパウロはコロサイを訪問したらしい。あるいは、文中に名前の出て来るエパフラスがパウロの代わりに遣わされ、コロサイ教会の基礎が築かれたと考える聖書注解者も少なくない。
いずれにしても、ピレモンはパウロによる回心者だったようだ。また、二人は非常に親しい友人でもあったことがうかがえる。
本書の中で、パウロはオネシモという名の奴隷のため、ピレモンにとりなしている。
「年老いて、今はまたキリスト・イエスの囚人となっている私パウロが、獄中で生んだわが子オネシモのことを、あなたにお願いしたいのです。」(9〜10)
オネシモはピレモンの奴隷であった。この手紙が書かれたローマ帝国の時代に、ローマの市民権を持つ主人たちは、十人から数百人、時には千人以上の奴隷を所有していたと言われる。その奴隷たちには、生きる権利も、自由も与えられてはいなかった。オネシモは、そのような奴隷の一人だつたわけで、このことから、ピレモンは非常に裕福な人だったことがわかる。
オネシモは主人ピレモンの金銭を盗み、大都市ローマに逃げて行った。そして、何らかの方法でパウロと出会い、彼に導かれて回心する。こうして逃亡奴隷オネシモは新生したクリスチャンとなり、獄中生活を続けるパウロに献身的に仕える者となった。
オネシモには、このままローマに留まり、自分に仕えてほしい。これがパウロの本音だった。しかし、彼としては、オネシモがピレモンの正当な奴隷であることを知りながら、いつまでも自分のもとにとどめておくことはできない。それとローマの法律によれば、逃亡した奴隷には、それ相応の厳しい、残酷な刑罰が待っていた。一般的には、磔刑が課せられたようである。まして、主人のものを盗んで逃亡したとあっては、極刑は免れ得ない。
そこでパウロは、オネシモの罪を赦し、受け入れてやってほしいと、彼の主人ピレモンに懇願し、その手紙とともにオネシモを主人のもとに送り返すことにした。オネシモの負債は、パウロ自身が代わって償うとも書いている。パウロは、このことをピレモンに対して命じることもできた。しかし、それをせずに、親しい友人としてお願いしているのである。
「彼は、前にはあなたにとって役に立たない者でしたが、今は、あなたにとっても私にとっても、役に立つ者となっています。そのオネシモを、あなたのもとに送り返します。」(11、12)
『オネシモ』には「役に立つ」という意味がある。「役に立たない」奴隷だった者が、今や「役に立つ」者となった。クリスチャンになるということは、他の人の役に立つ者とされることではなかろうか。
パウロは、奴隷制度そのものを問題として取り上げてはいない。しかし、その本質を変えることのできる原則を示している。キリストにある兄弟愛は、奴隷解放運動よりも力がある。
主題は、「社会問題の解決における福音の力」
〔内容〕
1.挨拶(1〜3)
2.ピレモンについての称賛(4〜7)
3.オネシモのためのとりなし(8〜21)
4.結び(22〜25)
![]()
本書の著者については、使徒パウロ説が有力であるが、確定されていない。このことに関連して、アレキサンドリヤの神学者オリゲネスの有名なことばが伝えられている。
「昔から、この書はパウロのものとして伝えられて来た。しかし、誰がこの書簡を書いたか、確かなことは神のみ知り給う。」
著者が誰であるにせよ、ヘブル人への手紙が神の完全な霊感を受けて記されたことについては異論がない。本書は、直接には、おそらくパレスチナに住んでいたユダヤ人のクリスチャンたちに対して書かれたのであろう。その時期は紀元70年のローマ帝国によるエルサレムの滅亡、神殿の破壊以前、65年頃と考えられる。
当時、彼らの信仰は動揺していた。ユダヤ人全体に比べれば、彼らは少数者であり、同国人からは裏切者と見なされ、憎悪と迫害の対象だった。なぜなら、彼らは先祖伝来のユダヤ教から、キリスト教への改宗者たちだったからである。
彼らに霊的進歩は見られず、礼拝出席も怠るような有様だった。多くの者たちは信仰生活に疲れ、以前の荘厳な神殿礼拝に、再び目を向けていた。彼らは、キリスト教を信じたことによって、大祭司、祭壇、犠牲、儀式のすべてを失ったと考え始めていたようである。彼らは、キリスト教からユダヤ教に回帰しようとする誘惑に駆られていたのである。
この手紙は、そのような背教を阻止するために書かれた。本書では、イエス・キリストの卓越性が、あらゆる面で強調されている。このヘブル人への手紙の鍵のことばは「さらにすぐれた」という語であり、十三回使われている。
(1・4、3・3、6・9、7・7、19、22、8・6、9・23、10・34、11・16、35、40、12・24)
キリストを本体とすれば、モーセの律法に含まれる体系─大祭司、犠牲、幕屋等─は、その模型、影にすぎない。
聖書は旧新約合わせて一つの書であり、旧約聖書を理解するためには新約聖書の知識が必要であり、新約聖書を理解するためには旧約聖書の知識が欠かせない。本書は特に、そのことを立証している。
この書は、『第五の福音書』とも呼ばれてきた。四福音書が、キリストの地上における働きを描いているのに対して、本書はキリストの、天の御座の右における働き─とりなしを描写しているからである。
著者はイエス・キリストの卓越性を強調しつつ、読者に対して、目に見えるものに心奪われることなく、目に見えないお方を仰ぎ見つつ、信仰によって歩むよう勧告している。
「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。」(12・2)
〔内容〕
1.キリストの人格の卓越性(1・1〜4・13)
イエス・キリストは、
2.キリストの祭司職の卓越性(4・14〜10・18)
キリストの祭司職は、レビ系の祭司職よりも偉大である。
新しい契約は、古い契約よりも 偉大である。
キリストは、
ご自分の血によって永遠の贖い を成し遂げられた。
永遠に生きておられる。
神の御座の右に着座され、とり なしの務めをしておられる。
私たちは、おりにかなった助け を受けるために、大胆に恵みの 御座に近づくことができる。
3.実際的勧告(10・19〜13・25)
「そのようなわけで、・・・全き信仰をもって、真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。」(10・22〜23)
信仰の定義
「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。」(11・1)
「信仰がなくては、神に喜ばれ ることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです。」(11・6)
信仰によって称賛された人々のリスト。
「こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競走を忍耐をもって走り続けようではありませんか。」(12・1)
神の訓練、その目的と結果
揺り動かされない御国への望み、その他、具体的な勧め
祈りの要請
終わりの挨拶
![]()
ヤコブ、ペテロ、ヨハネ及びユダによって書かれた七つの手紙は、公同書簡として知られている。この用語は一般的、または普遍的という意味で、パウロが個々の教会あるいは個人に宛てたパウロ書簡とは区別されている。ヨハネの第二、第三の手紙は例外と見られるが、第一の手紙に属するものとして、また一般読者に対して価値あるものとして、公同書簡のうちに数えられてきた。
新約聖書には、ヤコブという名で呼ばれている人物が少なくとも三人いる。十二使徒として選ばれた、ゼベダイの子、ヨハネの兄弟、ヤコブとアルパヨの子、ヤコブ。そして、主イエスの兄弟、ヤコブである(マタイ10・2、3、ガラテヤ1・19)。一般的な教会の言い伝えは、最後にあげたヤコブを本書簡の著者としている。
主イエスには、母マリヤから生まれた兄弟たちがいた。
「この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリヤで、彼の兄弟は、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。」(マタイ13・55)
ヤコブは、後にエルサレム教会の指導者となり、最初の教会会議の議長を務めた(使徒12・17、15・13〜29)。言い伝えによれば、彼は、聖い生活のゆえに当時のユダヤ人たちから名声を得ており、『義人』というあだ名をつけられ、彼らの多くをキリストに導いた。彼のひざは、人々のための絶えざるとりなしの祈りの結果、らくだのようにかたくなっていたという。ユダヤ人の歴史家ヨセフスは、ヤコブが大祭司の命令によって石で打ち殺され、殉教の死を遂げたと記している。
この手紙の宛先は、国外に離散しているユダヤ人クリスチャンで、彼らは激しい迫害に遭っていた。
書かれた理由は、
(1)
試練の中にあるユダヤ人のクリスチャンたちを慰めるため。
(2) 彼らの集会の混乱をただすため。
(3) 信仰と行ないを切り離そうとする風潮と戦うため。
本書は、新約聖書各書巻の最も初期の文書で、紀元50年以前に書かれたものであろう。
箴言が旧約聖書中の実際的な書であるのに対して、ヤコブの手紙は新約聖書中の実際的な書であり、新約聖書の箴言とも言われてきた。内容は、道徳的戒め、キリスト教の倫理について記され、クリスチャンの生活と行動の実際的な指導書となっている。
同じユダヤ人クリスチャンに宛てて書かれたものでも、ヘブル人への手紙が教理を示しているのに対して、ヤコブの手紙は行動を示している。ヤコブは、特に信仰と行ないを分離させようとする傾向が見られた、ある階層のユダヤ人クリスチャンたちを念頭においていたようだ。彼らは信仰を持っていると主張していたが、なお、彼らの間には試練の中で忍耐に欠けていること、争い、人間尊重、悪口、世的なことなどが見られた。
著者は、聖い生活をもたらさない信仰は死んだもので、教理に対する単なる同意にすぎないと指摘している
「人は行ないによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではない・・・。」(2・24)
「人が義と認められるのは、律法の行ないによるのではなく、信仰による・・・。」(ローマ3・28)
一見、パウロの手紙とヤコブの手紙は、互いに矛盾しているように思われる。しかし、両者の間に対立はない。最初、本書簡を『わらの手紙』と呼んだマルチン・ルターも後に認識を改め、ヤコブの手紙を実際にパウロの手紙を補足するものと考えるようになった。
「私が信仰によって義とされていることは、私の行ないによって証明されるのである。」
主題は 「実際的キリスト教」
〔内容〕
1.あいさつ(1・1)
2.試練と誘惑について(1・2〜18)
試練の価値を計算すること
「私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。」(1・2)
3.みことばについて(1・19〜27)
「みことばを実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの者であってはいけません。」(1・22)
4.差別について(2・1〜13)
5.信仰と行ないについて(2・14〜26)
「信仰は行ないによって全うされ、・・・。」(2・22)
6.舌を制御することについて(3・1〜12)
「私たちは、舌をもって、主であり父である方をほめたたえ、同じ舌をもって、神にかたどって造られた人をのろいます。」(3・9)
7.真の知恵について(3・13〜18)
上からの知恵の特徴
8.その他の教え(4・1〜5・20)
性格のきよさ
祈りの重要性
![]()
シモン・ペテロは、イエス・キリストの十二使徒の代弁者。ガリラヤの漁師だったが、後にイエスの弟子となる。『ペテロ』(ギリシャ語)、または『ケパ』(アラム語)は、師からもらった新しい名で、いずれも『岩』を意味している。
ペテロは、性急、且つ衝動的な性格で、典型的な多血質だったようだ。福音書を読むと、失敗も多かったが、その一面、人間味豊かな、愛すべき人物というイメ−ジが伝わって来る。
主イエスが捕らえられたとき、三度も主を否む大失敗をしたが、その直前、主はペテロに重要な任務をお与えになった。
「しかし、わたしは、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」(傍線は筆者)(ルカ22・32)
五旬節(ペンテコステ)の日以来、聖霊の力を受けたペテロは、その名の通り、イエス・キリストの不動の証人へと変えられた。彼は、後に回心したパウロとともに、初代教会の草創期を指導した。したがって、ペテロの手紙は、彼が主イエスから与えられた任務の成就だったと言える。
彼は、本書簡の中で、苦難の中にいるクリスチャンたちを励まし、力づけている。当時─紀元60年〜65年頃─、教会はローマ皇帝ネロによる迫害の下にあり、最初の大きな試練を経験していた。キリスト者は毎夜、ネロの庭園で火刑に処せられ、猛獣の餌食ともされていたという記録が残されている。また、皇帝のこのような実例を口実に、教会に敵対する人々は、ローマ帝国内のいたる所でキリスト者を迫害した。クリスチャンたちは、異教的な隣人と、偶像礼拝や、酒を飲むことや、快楽を楽しむことを、共にしなかったので、冷笑され、嫌われていた。悪意から、国家に対する不誠実という非難さえも受けていたようである。
ペテロは、文字通り火のような試練の中にいるクリスチャンに宛てて、この手紙を書いた。執筆場所としては、終わりにバビロンということばが記されている。彼は、ユーフラテス河畔の都市バビロンにいたらしい。ただし、黙示録の例に見られるように、これを象徴的にローマと解釈する人もいる。
教会の伝承によれば、パウロもペテロも、皇帝ネロの時代に殉教の死を遂げた。『クォ・ヴァディス』の伝説に次のような話がある。ペテロを救おうという友人たちの切なる願いに逆らえず、彼がローマから逃げた夜半のこと。アッピヤ街道で幻の中に主イエスに会った。
「主よ、どこに行かれるのですか(クォ・ヴァディス)?」
「ふたたび十字架につけられるためにローマに行くのだ。」
ペテロは恥じてローマに引き返し、主のように十字架につけられるのはおそれおおいと言って、逆磔刑(さかさはりつけ)に処せられたという。ペテロの殉教は、主イエスが彼に語られたことばからも推測される。
「『 まことに、まことに、あなたに告げます。あなたは若かった時には、自分で帯を締めて、自分の歩きたい所を歩きました。しかし年をとると、あなたは自分の手を伸ばし、ほかの人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくない所に連れて行きます。』 これは、ペテロがどのような死に方をして、神の栄光を現わすかを示して、言われたことであった。こうお話しになってから、ペテロに言われた。『わたしに従いなさい。』」(ヨハネ21・18、19)
この手紙の背景に流れるモチーフは『苦難』であり、キリストの苦難、およびキリストに従う者の苦難について語られている。しかし、本書はまた、『希望』、『喜び』、『恵み』、『栄光』についても、重ねて言及している。ヨハネが『愛の使徒』、パウロが『信仰の使徒』と言われるように、ペテロは『希望の使徒』と呼ばれてきた。
クリスチャンが、厳しい苦難の中にあっても喜び、希望を持つことのできる最大の根拠はイエス・キリストの現われ、すなわち主の再臨である。キリスト者は、この地上では旅人、寄留者にすぎない。だから、好い加減な生活を送ってもよいと言うのではない。むしろ逆に、主イエスが再び来られるときに与えられる栄光を望み見て、聖別された歩みをするよう、聖書は勧めている。
私たちは、現在、異邦人の皇帝によって迫害されてはいない。しかし、真の敵である悪魔の誘惑に絶えずさらされている事実を自覚している必要があろう。また同時にキリスト者は、信仰により、恵みの中で、神の御力によって守られていることをも忘れてはなるまい。
〔内容〕
1.挨拶(1・1〜2)
2.偉大なる救い(1・3〜2・10)
3.キリスト者の行ない(2・11〜4・11)
4.苦難を通しての務め(4・12〜5・11)
5.結び(5・12〜14)
![]()
ペテロの第一の手紙は、教会外の危険—迫害—を扱っており、外部から激しい迫害を受けているクリスチャンたちを励ますために書かれた。主イエスは、十字架の死の直前にペテロに言われた。
「あなたは、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」(ルカ22・32)
この任務は、第一の手紙において成就した。
第二の手紙は、教会内の危険—偽りの教理—を扱っており、彼らに対する警告のために書かれた。主はまた、死からよみがえられた後に、ペテロに三度命じられた。
「わたしの羊を養いなさい。」(ヨハネ21・15〜17)
この命令は、本書簡において成就している。
ぺテロは、自分に割り当てられている群れが、真理からそれて道に迷うことのないよう、第二の手紙を書いたのである。
本書には殉教を待つ雰囲気が漂っている。この点に関しては、使徒パウロによるテモテへの第二の手紙と共通している。恐らく、ペテロもパウロも、ローマ皇帝ネロの迫害の下にあって、殉教の直前にそれぞれの書簡を書いたのであろう。
終わりの時代になると、偽りの教えがはびこり、背教が起こることが予告されている。誤った教理についての厳しい警告が記されている点では、本書はユダの手紙と類似しており、ヨハネの第一、第二の手紙にも同様の記述が見られる。
偽教師によって人々の間にもたらされたものは、不敬虔な生活であり、その結果は滅び以外にはない。偽りの教理に打ち勝つ最善の武器は、神と主イエスを知る真の霊的知識である。
ペテロの第二の手紙のキー・ワードは『知識』であり、『知る』または『知識』という語が十六回以上も出て来る。ただ、この知識(グノーシス)とは、決して観念的なものではなく、体験を通して把握した実際的知識を指す。
マイヤー・パールマンによる本書の主題。
「キリストについての十分な、経験に基づく知識は、偽りの教えと汚れた生活に対する砦(とりで)である。」
〔内容〕
1.挨拶(1・1〜2)
「神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安が、あなたがたの上にますますゆたかにされますように。」(2)
2.神の恵みと知識における成長(1・3〜21)
(1) 神の約束(3〜4)
「その栄光と徳によって、尊い、すばらしい約束が私たちに与えられました。それは、あなたがたが、その約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質にあずかる者となるためです。」
(2)霊的知識の成長(5〜9)
「あなたがたは、あらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。」
「どうか、あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知識に満たされますように。また、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。」(コロサイ1・9〜10)
(3) 信仰の確立(10〜11)
キリストの威光の目撃者
確かな預言のみことば
3.偽教師に対する警告(2・1〜22)
(1) 偽教師の出現と行動(1〜3)
「あなたがたの中にも、にせ教師が現われるようになります。彼らは、滅びをもたらす異端をひそかに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身にすみやかな滅びを招いています。」
(2)偽教師に対する神の審判(4〜9)
(3)偽教師の性格(10〜22)
4.主の再臨の約束と訓戒(3・1〜18)
(1)この手紙の目的(1〜2)
(2)来臨の約束に対する嘲笑(3〜4)
「キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこのかた、何事も創造の初めからのままではないか。」
(3)来臨の約束の確証(5〜10)
「主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。」
(4)永遠の希望と敬虔な生活への訓戒(11〜17)
(5)結びの勧めと祈り(18)
「私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに、栄光が、今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。」
![]()
ヨハネの第一、第二、第三の手紙は、一般に使徒ヨハネによって書かれたと信じられている。これらの手紙は、おそらくAD90年頃に書かれたものであろう。伝承によれば、ヨハネは晩年を、エルサレムを去ってエペソで過ごした。
宛先については何も記されていないが、エペソを中心とした小アジヤの諸教会にあてられたものであろう。また、読者がヨハネの福音書について知っていることを前提に書かれているようだ。
第一の手紙は、当時のクリスチャンたちが偽りの教え、特にグノーシス主義の危険にさらされていたことを暗示している。これは二世紀においては更に深刻な問題となっていく。この教えの背景には、物質は悪、霊は善という二元論がある。
グノーシス派の人たちは、「人が世俗的なものから霊的なものへと高められるためには、聖書に啓示された知識よりもさらに深い特別な知識(グノーシス)が必要であり、これはごくわずかの選ばれた者だけに与えられる。」と主張して、自らを誇示した。そして、この宗教哲学はキリストの人格について二つの間違った教理を生み出したのである。
(1) キリスト仮現説
キリストの神性を偏重し、人性を軽視した。キリストは神より遣わされた霊であるゆえ肉の外見を顕示したにすぎない。その人性—肉体・成長・飲食—と死(受難)とは真実でなく、たんなる幻影・仮象にすぎない。
(2) キリスト養子説
イエスはたんなるひとりの人間であるが、洗礼に際して、『キリスト』すなわち高次の神的力が降った。しかし、その神的力は十字架にかかる直前、天界に復帰したのであって、結局人間イエスだけが受難し、復活したのであり、このイエスは単なる偉人にすぎない。イエスは他の人々よりも善良であり、賢明であった点において、また神的キリストが洗礼の時にイエスの上に下り、十字架の時に彼を離れ去ったという点において、他の人々と異なっていただけである。
結局、グノーシス主義に立つ教師たちは、イエスがキリスト(メシヤ)であること、肉体をとってこの世に来られた神であることを認めず、全人類の救いの根本にかかわる神の御子の受肉と贖罪とを否定し、当時の教会に対して最も危険な異端となった。使徒ヨハネは、この教えを反キリストの霊によるものと断定している。
更に、これらの偽教師たちは道徳的にも堕落した生活をしていた。誤った教理は罪の生活をもたらす。この危険に対処するため、ヨハネは、この手紙の中で福音の真理を示し、異端に対する警告を与えている。福音の正しさは、神の子たちの日常生活の中に表わされねばならない。
本書はまた、霊の父から信仰の子どもたちへの、情愛に満ちた家族的な手紙とも言える。クリスチャンの罪は、父親の命令に対する子どもの違反、そして家族の問題として扱われている。律法に対する違反としての子どもの罪は十字架で処理され、義なるイエス・キリストは、今や、御父の御前で弁護してくださるお方である。
或る聖書注解者は書いている。
「ヨハネの福音書は、私たちに、御父の家の敷居をまたがせ、第一の手紙は、私たちをそこでくつろがせてくれる。」
この手紙の中には、「子どもたちよ」という呼び掛けが七回使われている。原語は『テクニア』で、優しい響きを持つ親愛語だ。ヨハネの福音書で主イエスが十一弟子に語られた一回を除けば、新約聖書中、本書にだけ出てくる。
使徒パウロは、クリスチャンの、神の子(相続人)としての公の立場を強調し、使徒ヨハネは、信者の、御父から生まれた者としての神との親密さを特に念頭に置いているとも言われる。
全般的に見て、本書の書かれた理由は五つほどある。
(1)
神の子が、御父と御子、ならびに互いに交わりを持つようになるため(1・3)
(2) 神の子が満ちあふれた喜びを持つため(1・4)
(3) 神の子が罪を犯さないようになるため(2・1)
(4) 神の子に偽りの教えに対して警戒させるため(2・26)
(5)
神の子に永遠のいのちを持っていることを確信させるため(5・13)
〔内容〕
1.序文(1・1〜4)
2.神との交わり—光—(1・5〜2・29)
交わりの断絶
罪の告白と交わりの回復
弁護者イエス・キリスト
神の命令を守ること
3.神の子たること—愛—(3・1〜4・21)
神の子どもとしての身分
清い生活
兄弟愛
祈りの特権
真理の霊と偽りの霊との区別
神の愛
4.信仰と確信(5・1〜21)
「世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。」(5・5)
![]()
使徒ヨハネは、自らを長老と呼んでいる。他の使徒たちは、皆この世を去り、イエスの伴侶の中で彼だけが生き残っていた。たぶん彼は90歳を超え、当時のキリスト教界の監督的な役割を果たしていたに違いない。
宛先は、「選ばれた夫人とその子どもたちへ」となっている。
『夫人』と訳された『キュリア』という語は、二通りに解釈され得る。(1) 特定の個人
ある人物なら、おそらくエペソ近辺に住む名の知られた婦人で、彼女の家が教会となっていたのではないか。
(2) 彼女の名をもって象徴的に呼ばれた特定の教会
この場合、「その子たち」とは教会員を指すのであろう。
ここでは、前者としておく。だとすれば、本書は、聖書の中で、一婦人にあてられた唯一の手紙である。
初代教会の最も深刻な問題の一つは、にせ教師の存在だった。第一の手紙で言及されている同じ一派—主としてグノ−シス主義—の人々が、偽りの教理を持って各地を巡回していたのである。グノーシス主義は、イエスがキリスト(メシヤ)であり、肉体をとってこの世に来られた真の神であることを認めず、救いの根本にかかわる神の御子の受肉と十字架の贖いを否定するもので、当時の教会にとって最も危険な異端となっていた。ヨハネは、それを反キリストの霊と断じている。
「愛する者たち、霊だからといって、みな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを、ためしなさい。なぜなら、にせ預言者がたくさん世に出て来たからです。
人となって来たイエス・キリストを告白する霊はみな、神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。
イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。
それは反キリストの霊です。あなたがたはそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。」(Ⅰヨハネ4・1〜3)
この手紙の宛先となった婦人は、親切心から、このような偽りの巡回教師たちをもてなしていたようだ。そこで、ヨハネは長老として、彼女に警告の書簡を書いた。
本書のかぎの言葉は『真理』であり、クリスチャンに、真理に従う義務と真理の敵との交わりを避けるべきことを勧告している。真理は万難を排して、受け入れ、服従し、固守しなければならない。本書を読むと、二つの言葉が目につく。この短い手紙の中で、『愛』が四回、『真理』が五回使われている。これらは、『いのち』とともに、ヨハネが特に好んで用いた言葉のようだ。
四福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)の中に『愛』が合計七十回、『真理』が十八回、そのうちヨハネの福音書だけで『愛』が三十九回、『真理』が十五回。また、ヨハネの三つの手紙には、『愛』が三十九回、『真理』が十八回出て来る。(新改訳聖書による)』
愛と真理は切り離すことができない。愛のない真理は人を生かさず、真理のない愛は人を惑わせてしまう。
「キリスト教の愛の実践は、真理に対する敵の激励ではない。」(ヘンリー・ハーレイ)
「愛をもって真理を語り・・・。」(エペソ4・15)
〔本書の主題〕
「ヨハネの第一の手紙は、全体としてクリスチャンの家族への手紙で、にせの教えに対して警告し、実際的信心を勧めている。第二の手紙は、その家族の特定の人(婦人)への手紙で、にせ教師たちに対する彼女の態度について、彼女を教える目的で書かれた。彼女はこのような者たちに対して、親切なもてなしをなすべきではなかった。
こうした命令は苛酷にひびくかも知れないが、それは、これらの教師たちの教理がまさにキリスト教の根本問題をおかし、多くの場合、きよい行ないをおびやかしていたという理由から当然なことであった。
こうした者を彼女の家に迎えることにより、ヨハネが書いている相手の信者は、彼らの誤りに自分もあずかることになった。
ヨハネは、たまたまちょっとしたことでわれわれと教理的に違っているクリスチャンや、あるいは、誤りにとらわれている人たちに対しての不親切な取り扱い方を教えようというのではなかった。
彼が書いていた当時は、無律法主義者やグノーシス派のあやまちを犯した者たちが、信仰ときよめを根本から根こぎにしようとしていた時であり、こうした状態のもとでは、クリスチャンたちが言葉と態度の両面から彼らの教えを否定してしまうことは、差し迫って必要なことであった。この主題は次のように約言できよう—真理に従う義務と真理の敵との交わりを避けること。」(マイヤー・パールマン『聖書概論』より)
![]()
著者ヨハネはキリストの十二使徒の一人で、主に最も愛された弟子。福音書、第一、二の手紙、黙示録も書いている。紀元90年頃、おそらく彼は90歳を過ぎ、当時のキリスト教会において長老的な存在であった。
本書からは、第一世紀の終わり頃の小アジヤにおける教会生活の一面がうかがえる。当時、教会には巡回教師としての働きに召された人々がいた。彼らには、特に決まった報酬はなく、食事とか宿泊などは、行った先々のクリスチャンたちのもてなしにたよることが多かった。お世話する側から言えば、もてなしはキリスト信者にとって重要な奉仕の一つであった。
「聖徒の入用に協力し、旅人をもてなしなさい。」(ローマ12・13)
これらの巡回伝道者たちが地方の教会に赴くときは、一般に信頼されている人物なり教会の推薦状を携えていくことが慣例となっていたようである。たぶん、長老のヨハネは地方の諸教会に、彼の推薦状を持たせて一団の巡回教師たちを遣わしたのだろう。本書に名前の記されているデメテリオは、その一人だったと思われる。巡回する伝道者の中には偽教師などもいたが、彼は信頼すべき人物であった。
「デメテリオはみなの人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。・・・・。」(12)
ところで、巡回教師たちが旅から帰ってくると、自分たちを派遣した母教会の集まりで、巡回中に彼らが受けたもてなしについての報告などもなされていたと思われる。
或る地方の教会にガイオという人がいた。彼が、どのような立場にあったか、はっきり記されていない。けれども有力な会員、または指導者だったのかも知れない。ガイオは、経済的には貧しい巡回伝道者たちを、いつも親切にもてなしていた。その愛については、多くの旅人があかしし、そのことはヨハネも知っていたようである。
実は、この第三の手紙は、このガイオに宛てて書かれたものである。
そのガイオの属していた教会に大きな問題が起こった。ヨハネが遣わしたと思われる巡回伝道者たちが教会を訪れた時に、デオテレペスという有力者がヨハネの使徒的な権威を認めず、彼に遣わされた教師たちを受け入れることを拒んだ。デオテレペスは、教会管理に絶対的な権力をにぎる専制的な人物だったのではないか。それで、巡回伝道者たちをもてなしたり、彼らを教会に迎えることを傲慢な態度で拒否したばかりでなく、彼らをもてなした教会員を除名さえもした。(10)
その理由については何も記されていない。ただ、この事実についてはヨハネの耳にも入っていたようで、心を痛めたヨハネは直接デオテレペスに手紙を書いたが、それはどうも無視されたらしい。このような状況の中でヨハネはガイオに手紙を書き、彼の愛の行ないを喜ぶとともに、デオテレペスの暴君的な脅迫にもめげず、彼が続けて真理に歩むよう励ました。また、機会を得て、その教会を訪問し、使徒としての立場から、独裁者デオテレペスを断固処分する意向を表明している。
この短い手紙の中に表わされている三人の人物の性格は非常に対照的である。
(1) ガイオ。真実の愛をもって旅人をもてなす人
(2) デオテレペス。傲慢な教会の指導者
(3) デメテリオ。評判の良い巡回教師
ヘンリー・シーセンの新約聖書緒論は、本書を次のように要約している。
「ヨハネはこの書簡によってガイオに対するその愛を表わし(1)、彼の繁栄と健康に対する彼の祈りを告げ知らせ(2)、彼が真理のために立っていることを喜び(3、4)、彼が巡回伝道者に協力したことをよしとし(5、6)、彼らが帰って来る時にもまたそうすることを奨め(6〜8)、彼が間もなくそこを尋ねて、わがもの顔にふるまうデオテレペスを言い伏せることを告げ(9〜10)、多分この書簡を携行した人であろうデメテリオを推薦し(11〜12)、かつまたヨハネがまもなく彼を訪れ、顔を合わせて親しく語るべきことを伝えている(13、14)。そして、最後の挨拶(15)。」
本書の中で、ヨハネはガイオの幸せと健康を祈っている。
「愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。」(2)
キリスト者が、霊的な祝福とともに、この世の繁栄と肉体的な健康を期待することは、決して間違ってはいない。しかし、ヨハネが何にも増して喜んだのは、神の子どもたちが真理に歩んでいるのを聞くことだった。同じヨハネが、第一の手紙の中では、クリスチャンがこの世のものに執着することに対しても厳しく警告している。(Ⅰヨハネ2・15〜17)
![]()
著者は、「イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダ」。一般に受け入れられている見解によれば、主の兄弟ユダと推察される。
イエスには、母マリヤと彼女の夫ヨセフの間に生まれた弟たちがいた。
「この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリヤで、彼の兄弟は、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。」(マタイ13・55)
なお、ヤコブは彼の名の付けられた手紙の著者であり、初代教会の柱として重んじられた人物であった。ユダが冒頭に彼の兄弟の名を引き合いに出したことは、ヤコブが、これから彼が書き送る書簡の読者—多分、小アジヤにいる人々—の間で非常に有名だったという事実を示していよう。使徒の働きを読むと、彼が初代教会の柱として重んじられ、主の兄弟ヤコブとして名が通っていたことがわかる。
ユダは、他の兄弟達と共に、復活以前のイエスをキリスト(メシヤ)として信じてはいなかった。しかし今は、自らを「イエス・キリストのしもべ」と呼んでいる。しもべとは、文字通りには、『奴隷』を意味している。
当初、ユダは諸教会に宛て、共通の救いの問題について教理的なことを書く積もりだったらしい。ところが、緊急の必要が生じ、最初に意図したのとは全く異なる、かなり激しい論調の手紙となっている。
本書は、ペテロの第二の手紙と同様に、クリスチャンの間にひそかに忍び込んで来た偽りの教師のことを主として扱っている。この誤った教会指導者についての本書の厳しい表現に注意!
「不敬虔な者」、「神の恵みを放縦に変え」、「主イエス・キリストを否定する人たち」、「好色にふけり」、「不自然な肉欲を追い求める者」、「夢見る者」、「肉体を汚し」、「権威ある者を軽んじ」、「栄えある者をそしり」、「理解もできないことをそしり」、「わきまえのない動物のよう」、「愛餐のしみ」、「自分だけを養う者」、「水のない雲」、「実を結ばない秋の木」、「自分の恥のあわをわき立たせる海の荒波」、「さまよう星」、「不平を鳴らす者」、「自分の欲望のままに歩む者」、「口は大きなことを言い」、「利益のために人をへつらってほめる者」、「自分の不敬虔な欲望のままにふるまう者」、「あざける者」、「御霊を持たない者」、「分裂を起こし」、「生まれつきのままの人間」。
ユダは、彼らを、出エジプト後に荒野で滅ぼされた不信の人々、堕落した天使、永遠の火の刑罰を受けたソドムやゴモラの町々、弟を殺したカイン、不義の報酬を愛したバラム、指導者に対する反逆者コラに類比させている。
本書によれば、神とともに歩み、神によって天に移されたエノクは、また預言者であり、人類の始祖アダムがまだ生きていた時代に、キリストの終局的来臨(再臨)と不敬虔な者たちに対するさばきを預言している(14、15)。また、主イエス・キリストの使徒たちによっても、終わりの時代の背教は語られてきた。
「終わりの時には、自分の不敬虔な欲望のままにふるまう、あざける者どもが現われる。」(18)
そこで、ユダによるこれらの記述は、すでに起きている事実であると同時に、また終わりの時代についての預言とも考えられよう。
「ペテロの第二の手紙も、ユダの手紙も、既に当時存在する状況を問題にしていることは同じであるが、また共に末の時にひろがるべき状態に関する預言とみなすべきであろう。この立場から見て、これらはいずれも黙示録に対する最も適当な序文であるといえる。」 (ヘンリー・シーセン)
堕落した御使いについては、ペテロの第二の手紙(2・4)と本書(6)だけが言及している。
また、モーセのからだについての天使長ミカエルと悪魔の論争云々の節(9)は本書のみに記されている難解な箇所であるが、それは「ののしる」という罪についての例証を示すものであろう。すなわち、「最高の被造物である天使でさえも、最も堕落した被造物である悪魔をののしらなかった。」。
「聖霊によって祈り」(20)は、祈りに関してよく引用される。
同様の聖句は、「御霊によって祈りなさい。」(エペソ6・18)
これらは異言の祈りとして強調される場合もあるが、限定しないほうがよいだろう。知性の祈り、霊の祈りを問わず、聖霊に導かれた祈りの生活は、クリスチャンの成長の鍵である。
〔内容〕
1.挨拶(1、2)
2.信仰のために戦うべき一般的勧告(3、4)
3.神が悪人共を審き給うた歴史上の先例(5〜7)
4.偽りの教師と彼らの教えに対する厳しい拒否(8〜13)
5.神が悪人共を審き給うことの権威ある確証(14〜19)
6.霊の成長と人の霊を救うことについての熱心なる勧告(20〜23)
祝祷(24、25)
(ヘンリー・シーセン著『新約聖書緒論』による。)
![]()
本書は、使徒ヨハネによって書かれた。教会史家エウセビオスによれば、ローマ皇帝ドミティアヌスによる迫害下、ヨハネはパトモス島に流されていた。ここで彼は、キリストご自身の直接の命令により、本書を書いた。直接には、何回か名前の出てくるアジアの七教会にあてられたものだが、同時に、すべての時代の全教会に対するメッセージが含まれている。その背景には、当時の激しい迫害に苦しんでいた教会と、その後のあらゆる時代における教会の必要があった。終末におけるキリストの教会は、警告され、励まされ、来るべき迫害に対して備えられねばならない。
七つの教会の御使いとは、それらの教会に仕えていた指導者たちであろう。彼らが、島流しになっていたヨハネを尋ねて諸教会の様子を報告したとも考えられる。そのことが、黙示録の書かれる一つの機会となったのかも知れない。
有力な説によれば、本書は紀元95年または96年に書かれた。
黙示録は、新約聖書において唯一の預言書である。人間に対する神の真理の啓示は、創世記に始まり、黙示録においてクライマックスに達する。このどちらの書を欠いても、聖書は完全とはならない。
「もし、創世記が省略されて、物事の始まりについてわれわれを無知の中に取り残してしまうとするならば、黙示録の省略は、万物の完成について、われわれから多くの光を奪い取ってしまうことだろう。」(マイヤー・パールマン)
ある聖書学者は、両者を対比させて次のように述べている。
「創世記には、創造された地が記され、黙示録では、それが過ぎ去っている。創世記では、月と太陽があらわれるが、黙示録には、太陽も月も必要ないと書かれている。創世記には、人間の住家の園がある。黙示録には、国民の住む都市がある。創世記には第一のアダムの結婚があり、黙示録には第二のアダムの結婚がある。創世記には大敵サタンが初めて姿をあらわしており、黙示録には、そのサタンの滅亡がある。創世記では、悲哀と苦難とが、そのとばりを開いて、初めて人にのぞみ、はじめの、むせび泣き、涙があるが、黙示録ではもはや悲嘆も苦痛もない。涙はことごとくぬぐい去られている。創世記では、罪のため降ったのろいのつぶやきが聞こえるが、黙示録では、『のろわれるべきものは、ひとつもなくなる』と記されている。創世記では、人間が生命の木のある園から追い出されたが、黙示録では、その人が、だれはばかることなく帰って来て、好きなだけ生命の木の実を食べられるようになっている。」(「ロバート・リー著『輪郭的聖書』より)
本書の最初の節に、「イエス・キリストの黙示」と書かれている。これは、「キリストの人格と事業の啓示」を意味している。
ヨハネは、神の御子イエスを、人間の罪の身代わりとして犠牲となられたお方という意味で、何度も『小羊』と呼んだ。この言葉はヨハネ特愛の用語だったようで、福音書に二回、黙示録に二六回も記されている。そして、ほふられた小羊イエスが、本書においては、栄光に輝く勝利者キリストとして描かれており、このお方が時代の絶頂として栄光のうちに再び来られる(再臨される)のである。
黙示録の中心的事柄は、来るべき患難と審判、栄光のうちにキリストが来臨されること、キリストの御国の建設などであるが、本書は聖書の正典の中で最も難解な書である。理解できない箇所は無理な解釈をするよりは、そのまま残して、さらに光が与えられるまで忍耐して待つほうがよい。
本書には価値ある教訓、警告、励ましを与える約束等があるので、難解な事柄については無益な議論を避け、理解できる事柄を実行するように心がけるべきだろう。
また、黙示録は旧約聖書の預言の完成であり、旧約聖書の預言や象徴を多く引用しているので、特にイザヤ書、エゼキエル書、ダニエル書、ゼカリヤ書等の研究は、その解釈のために有益だと思われる。
本書は、1章19節のことばによって分解することができよう。
「そこで、あなたの見た事、今ある事、この後に起こる事を書きしるせ。」
1.あなたの見た事ーキリストについて
(1) 序文
(2) キリストの黙示(啓示)
2.今ある事ー教会について
七つの教会へのメッセージ
(1) エペソの教会へ
(2) スミルナの教会へ
(3) ペルガモの教会へ
(4) テアテラの教会へ
(5) サルディスの教会へ
(6) フィラデルフィヤの教会へ
(7) ラオデキヤの教会へ
3.この後に起こる事ー御国について
(1) 審判者(神)
(2) 大患難の預言
(3) キリストの再臨の預言
(4) 千年王国の預言
(5) 永遠の状態の預言
(6) 結び
「しかり、わたし(イエス)はすぐに来る。」アーメン。主イエスよ、来てください。(20)
![]()